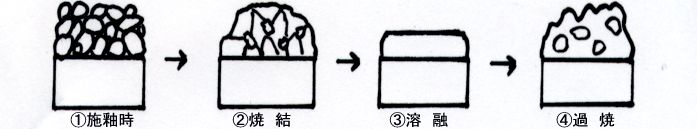
柤丂徧 |
SiO2 |
Al2O3 |
Fe2O3 |
TiO2 |
CaO |
MgO |
K2O |
Na2 O |
拞崙棿愹梣惵帴缰 |
69.16 |
15.40 |
0.95 |
- |
8.39 |
0.61 |
4.87 |
0.32 |
撶搰梣屆摡帴婍缰 |
66.70 |
18.85 |
0.67 |
- |
8.41 |
0.77 |
3.50 |
1.77 |
僗僐乕僞僀堚愓屆摡帴缰 |
57.17 |
13.84 |
0.99 |
0.07 |
19.66 |
2.43 |
2.41 |
1.45 |
傃傫僈儔僗 |
72.90 |
2.00 |
0.04 |
- |
10.95 |
0.14 |
1.40 |
12.30 |
斅僈儔僗 |
72.60 |
1.83 |
0.10 |
- |
7.91 |
3.80 |
12.19 |
|
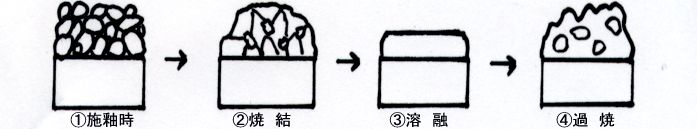
暔丂幙丂柤 |
梈揰(亷) |
|
丂丂僇儕挿愇 |
1170 |
偙傟傜偑崿崌偝傟傞偙偲偵傛傝丄掅壏偱梟梈偟丄缰傪宍惉偡傞丅 |
丂丂僜乕僟挿愇 |
1120 |
|
丂丂愇丂丂丂丂塸 |
1723 |
|
丂丂僇僆儕僫僀僩 |
1770 |
|
丂丂愇丂奃丂愇 |
2570 |