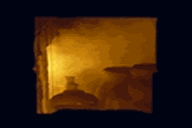時 代
|
区 分
|
年 号
|
関 連 事 項
|
奈
良
平
安
鎌
倉
室
町
|
前
期
伊
賀
|
天平年間
(729~749)
|
●種壷時代・・・・・種壷は昔、農家で米、麦、大豆等の種子を貯蔵する農具であり、浸種壷は貯蔵した種子を蒔くときに一週間程水に浸しておく必要から生まれたものである。これらは農具であり農耕のかたわら焼かれたもので出発は技巧からでなく実用から踏み出されたものだと思われる。これら種壷、浸種壷は何時代の産物であるか詳かでないが布目瓦の出来た天平時代からみて、これら農家の必需品は同時代もしくはあまり隔たりのない時代から出発されているものと想像される。
●丸柱窯は、天平宝字年間に創起されたものであります。天平宝字より140余年後、延喜大神宮式に伊賀より神酒2瓶年2回大神宮に献ずる式あり、この酒を盛る瓶は此れにて造られてと記録があります。
長く文化の中心であり、日本美術の源であった奈良朝の歴史的影響を受け、又この環境の間に伊賀丸柱窯は発展を遂げる。
|
安
土
桃
山
|
永亨12年
(1440)
|
●丸柱村割谷に鎌倉から室町にかけての窯跡があった。
●堺の豪商茶人、津田宗及の自会記の天正9年(1581)10月27日の条に、伊賀焼の壷の事が記されている。
|
筒
井
伊
賀
|
天正13年(1585)~
慶長13年(1608)
|
●初期伊賀と比べて、作風に画然と違いのある茶陶伊賀焼(花生や水差)が造られるようになったのは、筒井定次が伊賀に封じられた1585年頃からと推定される。・・・・・『三国地誌』に「筒井定次ノ時焼」と記されている。
|
江
戸
|
藤
堂
伊
賀
|
慶長13年(1608)
~
|
●藤堂高虎(1556~1630)伊賀の領主とる。
●高虎在世中、伊賀焼そのものの消息が判然としないが、元和9年(1623)銘の沓(くつ)茶碗が現存しているので、在世中に丸柱焼かれていたのは確かであり、それがすでに灰釉が施されているので、高虎時代に古伊賀と同類のものを焼きつつ、作風が変化していったものと思われる。
|
寛永年間
(1624~1644)
|
●『遠州伊賀』・・・・・高虎にとって娘婿であり、二代目高次にとって義兄弟である遠州の時代であるから、伊賀窯の茶陶については、遠州の指導的な関わりがあったであろう。この時代の作は、藤堂伊賀の後期にあたる。
●二代目高次は京都より陶工を招き、伊賀人に火加減等学ばせる。(1630)
●藤堂高次は、寛永12年(1635)京都より孫兵衛、伝蔵を招き丸柱で茶器水差を焼かせる。
|
廃
窯
|
寛文9年
(1669)
|
●藤堂高久、丸柱窯で用いられていた伊賀独特の白土山の陶土は採掘禁止とする。いわゆる御留山となったことが記されている。
|
復
興
伊
賀
|
宝暦年間
(1751~1764)
|
●丸柱窯に瀬戸の陶技を導入し、伊賀焼の復興をはかる。
|
明和元年(1764)
|
●七代藩主高豊の時代、主に焼かれていたのは日用の雑器で、従事した陶工のなかでは弥助・久兵衛・定八などの名が知られている。古伊賀とちがってほとんどが施釉の陶器でなかには藍オランダ風のものも焼いていた。
|
明和7年(1770)
~
|
●初代弥助は九代藩主(たかさと)から「伊賀国」「丸柱制」の印を拝領して作品に捺印している。その後定八に与えられる。
|
文化~文政年間
(1804~)
|
●丸柱で開窯するもの多く、十件程あり。
|
天保年間
(1830~1843)
|
●徳利や土瓶などの雑器に、白濁色の釉地に銅緑釉や藍釉を流したものなどの生活必需品を大量に焼くようになる。
|