|
でもくらしちずん 通信 vol.3 1997年9月15日発行 |
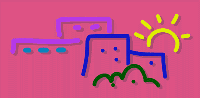 |
|
でもくらしちずん 通信 vol.3 1997年9月15日発行 |
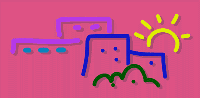 |
|
■でもくらしちずんな皆さんへ!■ 次回は9月24日です。 暑かった夏も終わり、ときおり秋風を感じる季節になりました。すごしやすい季節の到来ですが、鳥羽市にたくさんの人が来てくれる夏の終わりに、少し寂しさを感じてもいます。 しかしその気持ちとは全く逆に、道が混雑し喧噪にむせ返る鳥羽は嫌いだと、感じている方もいらっしゃるでしょう。 あるご夫婦の車に同乗させていただいたときのことです。前を走っていた県外ナンバーの車がのろのろ運転の上に、交差点で考え込んでしまい、信号が赤になりかかってしまいました。 こちらは急いでいましたから、助手席の奥さんは、『もう、とろくさい。クラクション鳴らしたんない!』とご主人に言いました。私も正直そう思いました。 しかしご主人は、『あの車、よそから来とるから道がわからんのや、あの人らが来てくれるから、うちら食べさせてもらっとんのやぞ。ボクは降りてって道案内したりたいくらいや』とおっしゃったのです。 私は自分が恥ずかしくなりました。まちづくりを叫び、観光業を営む自分が、一住民となると違うことを考えていたのです。もてなしとは、訪ねてきてくれた人に感謝をすること…分かっているつもりのことでしたが、ご主人の言葉を聞いて目から鱗が落ちたような気分になりました。 住民の自己責任とは、そんな日々の考え方にもあると思いませんか。 |
|
■講師の話■ 『江戸・平成比較論』北原 良彦氏 9月の講師、北原氏は、石川県で「地域みらい」という会社を経営し、日本各地の地域開発や地域政策のアドバイザーをしながら、金沢大学の講師を勤めています。私の友人の中では、最も専門的にまちづくりの研究をしている人物です。 個性あるまちづくり、コミュニティーの息づくまちづくり、NPOに関してなど、どれをとっても、非常に詳しい知識を持っていますが、今回は特に「江戸・平成のまちづくりの比較論」という切り口で話しをしていただきます。 実はこの話し、私もまだ聞いたことの無い話しで、このコーナーで、ちらっともご披露できないのが残念なのですが、逆に日々勉強と考えている私も、受講を楽しみにしているところです。 |
|
■最近思うこと■ ナイター村議会 パソコン通信で東北の友人に教えてもらった話しです。地元の朝刊にでていたらしいのだけど、もしかしたらこちらでも掲載されていて皆さんはすでにご存知の話しかもしれません。(私、あんまり新聞読まないから……お恥ずかしい) きっと山形県のことだと思うのですが、戸沢村というまちでは、村議会を夜間に開催する「ナイター村議会」を実施しはじめたのだそうです。 つまり平日の昼に議会を傍聴するのは、仕事をかかえる村民には行きたくても行けない困難なことなので、夜に議会を開催することによって、傍聴にきてもらい、村政に興味をもってもらおうとの発想です。 実施してみると、傍聴席は多くの村民で満席になったそうです。村民の感想として、「村政に参加している、という思いを強くした。」のコメントが新聞に掲載されていたという話しでした。 戸沢村の議会や行政が開かれているのか、それとも戸沢の村民が開かれた議会・行政を望んでいたのかは分かりませんが、いずれにせよもともと議会は傍聴という手段によって万人に開かれているものです。 時間帯を変えることによって傍聴がしやすくなったというだけで、満席になるほどの村民が集まったというのは、多くの村民が民主主義におけるそれぞれの責任をよく理解し、また、自ら村政に参加したいという意欲を持った方が多かったということに他なりません。 どこかの田舎の小さな村で、そんなことが起こってきているこの時代というものに、私はずいぶん勇気づけられました。 でもくらしちずんも、もう少し呼びかければ、同じ思いの仲間がまだまだ見つかりそうな気がしてきました。 |
|
■ 人 ■ 世界の御木本幸吉翁 私が鳥羽に来たのは、今から16年前のことでした。鳥羽がどんなところかもまったく分からずにやってきたのですが、それでもよく知っている有名人がいました。 それはもちろん、御木本幸吉翁のことです。(私の場合中村幸昭館長は別の話しですね) 昔は必ず、学校図書館の偉人伝コーナーに、「真珠王 御木本幸吉」の名前がありましたものね。 確か私は、エジソン、野口英世、御木本幸吉の順で伝記を読んだように記憶しています。まさかそれが三重県の人だとは知る由もなかったと思うのですが、子供ながらに感動したことを覚えています。 幸吉翁のすごいところは、まず、世界を知りたいと東京に行き、そこで生まれ育った海に関わりのある真珠に目を付けたこと。 次いで、それを作ろうという発想と、絶対にできるという信念を貫いたこと。 そしてそれに成功すると、再び世界を見て、世界中の女性の首を真珠で絞めることを追い求めたこと。 そんな3つの器だと思うのです。 彼の業績が、真珠と観光のまち鳥羽を生んだことも郷土の誇りですが、彼の偉大さはそれだけではありません。 彼の3つの器は今の時代のまちづくり人に、必須の条件であると思うのです。 鳥羽の海という地域特性を大切にし、しかし常にグローバルに考え行動し、いかなる困難にも希望と信念を持ってあきらめずぶつかっていく。 今までの講師の皆さんからも、同じような言葉を何度か聞くことができましたね。 身内のことで恐縮ですが、実は中村館長を見ていても同じような器を感じるのです。 もしかすると幸吉翁の偉大な器は、鳥羽の人たちが潜在的に持っている素地なのではないでしょうか? 私は幸吉翁の偉業を称えるとともに、その行動の原点である、鳥羽の民の素地を持った人を新たに発掘し、鳥羽のまちづくりに活かすべきだと思っています。 そんな思いから最近は、水族館関連の本や番組づくりだけでなく、幸吉翁や真珠に関する本や番組のプロデュースにも力を入れているところです。 |
|
■NEWS■ 「伊勢・鳥羽・志摩」の名称を定着させたい。 みなさんはご存知でしょうか?東海や近畿地区外では、誰もが伊勢志摩と鳥羽は離れていると信じていることを…。 また県政では、鳥羽を含んで「伊勢志摩」と呼びならわし、ちょっと親切な旅行雑誌などでは「伊勢志摩・鳥羽」と紹介されたりしていることを……。 東京では、多くの人に「鳥羽って有名ですけどどこにあるのですか?」と訪ねられ、 少し知っている人には「伊勢志摩の奥が鳥羽ですよね」と言われてしまうのです。 それは、鳥羽にとってだけではなく、伊勢にとっても志摩にとっても損な話しです。 県のさまざまな会議でも、伊勢鳥羽志摩と明記して欲しい言っているのですが、「伊勢志摩地域」という呼び名があるからダメだという返事です。 そこで、非力ながら自分のできるところだけでもと思い、「伊勢・鳥羽・志摩」のロゴを作り、自社のポスターや関連する雑誌などに入れていくことにしました。 またとりあえずは観光産業ということで、私から、ミキモト真珠島、志摩スペイン村、おかげ横町に呼びかけて、来年早々より「伊勢・鳥羽・志摩」キャンペーンを始めることに同意を頂きました。 ロゴは、伊勢で使うときは伊勢の字が、鳥羽で使うときには鳥羽の字が大きくなるという、けっこう考えて作りました。 みなさんのところで使う機会があれば、ぜひご一報下さい。自由に使用いただければと思います。 ☆う〜ん、今回はなんとなく観光に関わるような話しばかりだったですね。反省。 |

 でもくらしちずん通信 表紙へ戻る
でもくらしちずん通信 表紙へ戻る  でもくらしちずん 表紙へ戻る
でもくらしちずん 表紙へ戻る
 HAJIME'S PAGEへ
HAJIME'S PAGEへ