|
でもくらしちずん 通信 vol.7 1998年2月2日発行 |
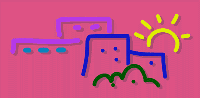 |
|
■でもくらしちずんな皆さんへ!■ 次回は公開講座 2月22日(日)の午後です。 昨年4月から始めてきた、まちづくり塾『でもくらしちずん』の本年度最終日は、前回お知らせしましたとおり2月22日となりました。 今回は、次年度へのステップとして公開講座にし、少しでも多くの皆さんに「市民参加のまちづくり」「まちづくりワークショップ」を体験していただこうと思い、日曜の午後をつかって、いつもの通り講義と、そして100人規模の大ワークショップに取り組みます。 講師は、地方分権やNPOに詳しい「構想日本」の代表加藤秀樹氏をお招きして、今後の国の方向を平易に解説していただくとともに、なぜ住民が主体性をもってまちづくりをしなくてはならないのか、ということのおさらいをしようと思います。 問題なのは、「まちづくりワークショップ」の体験です。100人来てくれるかどうかは、塾生のみなさんそれぞれが、仮に2人をお誘いいただければ大丈夫。 ただ仮に100人の参加者とすると十数テーブルが必要になり、当然それだけのファシリテーターも用意しなくてはなりません。 そのために、現在、全国のファシリテーター仲間を集めているところです。 みなさんも是非、お知り合いの方々をお誘いあわせの上お越し下さい。 |
|
■講師の話■ 『新しい社会の仕組み』 構想日本代表 加藤秀樹氏 加藤秀樹講師は、まちづくり読本『大変革、夜明け前』に何度か登場する人物で、今までの講師、村岡氏、白石氏とともに、私たちと「メダカネット」を組んでいる仲間です。 元大蔵官僚という、国家システムの中心にいた経歴があり、行政の仕組みや世界の未来を、非常にリアルにとらえておられるので、メダカネットにとっては、常に相談役のような役目を負っていただいています。 大蔵省のエリート官僚であった加藤氏が、あっさりとその仕事を捨てたのは、国の仕組みが見えてくるにつれ、国家行政の中にいては、社会は変わらないと思ったからだそうです。 さまざまな国家行政の行き詰まりの中で、その思いを強めた加藤氏は、結局大蔵省を辞しました。そして日本の将来を憂い、氏の政策力に期待するいくつもの企業スポンサーを得て、政策シンクタンク「構想日本」を立ち上げたのです。 「構想日本」は、特定の政党、団体のためでなく、自らの理念に基づいて政策を作る独立した機関で、理念を共有できる政治家や地方自治体の首長の政策支援を行っています。 つい最近も、NPO法案を地方自治体から作ろうという運動をし、高知県や宮城県などの知事や市長を集めて、「NPO支援宣言」を記者発表されました。 構想日本のホームページ http://www02.so-net.or.jp/~j_init/ |
|
■NEWS■ 二丁目大里本町の都市計画でワークショップ始まる。 前号でご紹介した、『でもくらしちずん』からファシリテーターを派遣することが決まっていた、大里本町のまちづくりワークショップが、先週から本格的に始動を始めました。 今回ファシリテーターとして派遣したスタッフは、川村君、岩佐君、村瀬君、コーディネーターに柿木君という、おなじみの布陣です。 私は大里の住民なので、『でもくらしちずん』とワークショップの紹介をした後は、意見を言う側として参加していたのですが、参加しながらも、もうドキドキ、ハラハラで、他のテーブルに耳を傾けていました。 だって、実践をするのはこれが初めてだし、塾生としてお越しいただいている皆さんのように、市民参加のまちづくりに積極的な方とは違う方々を相手にするのですから…。 しかし案ずるより産むは安し、でもくらしちずんスタッフの巧みな進行で、あっという間に時間は過ぎていったのでした。 また、初めて参加する方からの、「こんなことして何になる?」とか「とにかく行政の案を出してくれ」という発言に対して、 私たちが答えるまでもなく、前回試験的にやってみた時に参加していた方から「いやいや、わしらも最初はそう思とったんやけどな、やってみると自分らのまちは自分らで最初から考えるこの方法がいちばんええてわかったんや」と説明されたのを聞いて、たいへん心強く感じました。 今回は、まちづくりワークショップで伊勢市の都市マスタープランを作るなど、全国各地で実績を上げられている、三重大の浅野助教授に総合アドバイザーとしてお越しいただき、ワークショップについて説明をいただいたのですが、浅野先生曰く、「今までいくつものまちでワークショップを行ってきましたが、すでにファシリテーターがいるまちは初めてです。これからの進展にワクワクします」とのこと。 改めて、『でもくらしちずん』をやっていてよかったと思うと同時に、ワークショップを受け入れた鳥羽市の都市計画課の、勇気に感謝をした次第です。 |
|
■ 本 ■ 星の王子さま 人のコーナーで、サン・テグジュペリを出そうかと思ったのですが、それよりも彼の著書「星の王子さま」の方が、なじみがありますね。 星の王子さまは、今でも時々読み返す、私の心の本です。 物語の中で、王子さまは「砂漠が美しいのは、どこかに井戸を隠しているからだよ」と言い、キツネは王子さまに「本当に大切なことは目に見えない」と言うように、サンテグジュペリはこの本の中で、人にとって本当に大切なもの、つまり本当の幸福とは何かを、一貫して私たちに問い続けています。 王子さまが会ったあきんどが売っているのは、喉の渇きをいやす薬です。それを飲めば一週間、井戸の水を汲み飲む時間が節約でき、その節約した時間で好きなことができるのだと説明します。 とこどが王子さまは、「僕だったらその時間を、おいしい井戸の水を飲む時間に使うのだけど…」と思うのです。 このあきんどの薬にこそ、今の時代のはまり込んでしまった袋小路の姿を見ることができないでしょうか? 何のための便利さなのか?何のための経済発展なのか?何のための社会システムなのか? 私たちは今こそ、星の王子さまの気持ちになって、本当に大切なものを、自分たちの手で守り、育て上げなくてはなりません。 (星の王子さま:サン・テグジュペリ作、内藤濯訳、岩波書店刊) |
|
■最近思うこと■ NPO法案とコンドーム NPO法案が、遅々として進みません。しかもその中身は、NPOの奨励とはまったく意を別にした、枠組みだけのもの。 これを見るにつけ、自分がかつて県の審議会でコンドームの自販機廃止案に、抵抗したときのことを思い出します。 その審議会の事務局案はこうでした。コンドームの自販機は、青少年の不純異性交遊を助長するので、三重県内での設置を禁止する条例を作る…と。 しかし私は、コンドームが無くてもセックスする青少年はいるのだから、誰でも買える環境を作るべきで、逆に学校内に置くべき(欧米では、購買に置いてある)。という主張で、反対しました。 最終的には、性的弱者である女性の委員が全面的に私の意見を支持し、少数派ながらも、設置禁止案は見送られました。 はたしてどちらが正しいかというつもりはないのですが、その時に、現在の社会では、行政は「規制をすることで社会づくりができる」と考えているのだと実感したのです。 私は個々に責任を持たせることで、社会づくりができると考えたいのです。 |

 でもくらしちずん通信 表紙へ戻る
でもくらしちずん通信 表紙へ戻る  でもくらしちずん 表紙へ戻る
でもくらしちずん 表紙へ戻る