笹ヶ峰--美濃俣丸スキー縦走 '04.3
--ちょっぴり会心の山--
笹ヶ峰本峰から南西、美濃俣丸方面を望む。右手奥の方へへなだらかに続くのは江美国境稜線
前週のカイドウノ尾下見の結果、スキーは70cmのものを持参する。
珍しく満を持して、日野川最奥部、笹ヶ峰、美濃俣丸間スキー縦走に取り組む。
予定では前日に笹ヶ峰旧ロボット雨量計ピーク尾根の取付を調べるはずだったが、車の都合で広野ダム着は日没のあとだった。
翌日、目がさめると6時をまわっていた。ズッコケた。やってしまった朝寝坊。下山地点の鈴谷出合に車を置いたら、
ロボット峰尾根への取付きが遅れるので、仕方なく3キロ弱ほど大河内へ入った地点に置車。帰りはここまで戻らないといけない。
6時40分発。
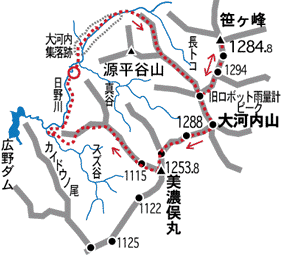
日野川源流の桃源郷ともいうべき大河内をすぎ、林道から見える丸木橋を渡って尾根に取付く。
しばらく雪の積もった山腹の植林帯を行くが、左へ横断気味に急な尾根へ出ると、雪はいったん消える。
しかし、短い板を選んだので、薮漕ぎがあっても消耗することはないし、尾根が狭いのでルートははっきりしている。
右手に源平谷山がよく見え、標高の確認もしやすい。標高600m付近から緩傾斜部分では雪が続きはじめ、
900mではスキー可能となるが、雪は締まっているので、ツボ足の方が早い。
1080mの台地に出ると、一気に笹ヶ峰西面の景観が開ける。
しかし、依然として雪は堅くしまっているので、スキーはつけない。
ピークへの最後の登りは、板を履いた方がやっかいそうだ。
|
大河内集落手前。道路の雪はなくなって、集落跡まで車は入ることができる
|
ロボットJPへ続く尾根の起点の丸木橋。ここから植林帯へ入る |
標高600m付近。尾根は斜面の傾斜が一様ではなく階段状にせりあがる。このあたりの薮は穏やかだ
|
取付きから2時間半強でピークに立つ。快晴。一気に奥美濃最奥院の山々のパノラマが目を射る。
何と素晴らしい眺めなんだ。ふだんならこの季節は黄砂で靄っているのだが、幸運にも空は澄み切っている。
360度さえぎるものがない景観をほしいままにして、しばし言葉が出ない。
|
|
|
| ロボットJ峰から北、笹ヶ峰本峰(中央左)への稜線。中央が最高標高点p.1294m。その右の尾根が不動山への尾根 |
同南望。左はp.1288m。中央右が美濃俣丸。その左手コル状の向こうのピラミッドは三周ヶ岳
|
アップダウンがあるので、依然ツボ足で行く。JPから35分ほどで本峰着。
ここでも高倉峠や釈迦嶺の雄大な眺めを楽しむ。
笹ヶ峰から北、釈迦嶺、高倉峠、金草岳方面の大観。その向こうに銀杏峰、部子山、そのまた向こうに加越国境、白山が見える
本峰でスキーを履く。50m前後のアップダウンがあるので、シールは着けたまま滑る。
雪がゆるんできたのでシールの抵抗はあまり気にならない。
70cmの板は小回りが効くので、ある程度傾斜があれば快適だが、急斜面の斜滑降には適さない。
金ヶ丸谷側クレバスの上辺を行く時は、足元をすくわれないか心配になる時もあるが、他に問題はない。
ロボットJPで再度大休止。ロボット尾根を今日登ってくる人はいないようだ。
さて、気分的にはえらく遠くに見える美濃俣丸へ向かう。
JPから50mほどは雪が崩れて薮が激しいので、これをやりすごしてから板を履く。
シールは依然つけたままである。下の雪が締まっているので、短い板でも不安定にはならない。急な斜面でも小回りが良く効く。
さすが、長い下降ではツボ足よりも効果的だ。JPの下で一人、次の大河内山(1288m)の下りで2パーティーと行き違う。
この南斜面は120mほど一気に下れるので最も気持ちよい部分だった。
美濃俣丸手前のピークの下りは、雪が崩れてクレバス帯となっている。落ち込むと厄介なので慎重に下る。
美濃俣丸への最後の斜面は80mほど一気に突き上げている。ここはスキーを脱いでツボ足で登る。美濃俣丸着13時15分。
笹ヶ峰本峰から大休止3回(一度は靴紐の締めなおし)を含んで所要2時間40分であった。
歩いていないので、スキーを使うのと、歩くのとどちらが早いのかはわからないが、気分はスキーの方が遥かに勝る。
| 大河内山-美濃俣丸間のなだらかな鞍部からp.1288の大斜面を振り返る | 手前のピークから美濃俣丸北面。スキーを履くのはどうも嬉しくないのであっさり脱ぐ | 美濃俣丸から、たどってきた笹ヶ峰の国境稜線。お昼をすぎて雪はくさり、空はやや靄ってきたようだ |
上から見るとあまり快適な滑降は望めないが、これは朝寝坊の罰である。
下り始めると、見かけどおり尾根はすぐ小薮が立ちふさがり、右手スギ谷側の斜面に追い込まれる。
転倒すると谷底まで一気に持って行かれる斜面なので緊張するが、すぐ傾斜のない尾根に乗り上げ、登り返しになる。
小薮が所々出てきて歩いた方が早いので、あっさりスキーを脱ぐ。もう稜線で十分堪能した、と自分に言い聞かせる。
このあとの尾根は長かった。
912mの広い標高点を越え、左手の枝尾根に入ると、雪も消えぎえになり、700mくらいで完全に雪はなくなる。
踏み跡のはっきりしない広い尾根を赤い標識布を辿りながら、かなり厳しい薮漕ぎになる。最後に植林帯の中を急降下し、
ポンと荒れた鈴谷林道に出た。15時。この尾根はスキーには使えない。下部の薮が濃すぎる。
あとはひたすら鈴谷林道を歩き、堰堤工事現場を経て、日野川本流出合着15時33分。ここに荷物をデポし、置車地点帰着16時。
途中で大河内山付近で出合った歩きパーティーと行き違う。彼等は鈴谷林道に置車していた。('04.3.28)
置車地点発6.40--大河内6.52--尾根取付7.10--旧ロボット雨量計JP9.45-10.10--笹ヶ峰10.45-10.55--旧ロボット雨量計峰
11.30-11.40--美濃俣丸13.15-13.30--北西尾根登山口(林道)15.00--鈴谷出合15.33--置車地点着16.00
| 美濃俣丸西北尾根p.912から振りかえる。執拗なシュプールも見かけたが、私はこの尾根のスキーは願い下げだ | 最後は汗だくの猛烈なブッシュこぎの末、ポンと鈴谷林道へ出る。踏み跡は両隣の尾根にくらべ、遥かに薄いので、下りは注意を要する。林道の上で、しばらく大の字にのびてしまった |
長い間暖めていた計画は、素晴らしい好天に恵まれてあっけなく終わった。
笹ヶ峰のスキーは予想通り登り下りの尾根は期待できないが、国境稜線では加越国境と遜色ない味わいがあった。
天候という自助努力では何ともしがたい要素も含めての上ではあるが、自分にとって近来にない、ちょっぴり会心の山であった。
これだから山はやめられない。八百よろずの神に心から感謝。
*国境稜線までの尾根を、あくまでスキーによる登下降にこだわるのなら、登路はロボット峰尾根とカイドウノ尾に選ぶべきだろう。
美濃俣丸西北尾根は--滑った猛者もあるようだが--薮が濃すぎて、余程でないと苦行以外の何ものでもないだろう。
また、ショートスキーも普及してきた現在、2月後半以降の雪が締まりはじめた時期に行く場合は、
100センチ以下の板を使うのが賢明だと思われる。
(ただし、シールは間に合わせではなく、板幅にフィットさせること。
今回間に合わせの幅細いシールを用いたが、ざら目雪には無力で、登りの部分でえらく苦労した。)
