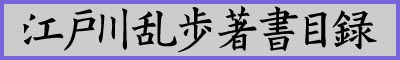|
【 目次 】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 番犬敬白 】1999年10月21日
|
|
このページでは、大正14年発行の『心理試験』に始まって現在に至るまで、乱歩の著書を刊行順に目録化する作業を進めております。不備や遺漏のご教示をいただければ、たいへんありがたく存じます。 【 番犬追記 】2003年8月10日 ──と記しましてから早くも四年近くの日月を閲してしまいましたが、おかげさまにて『江戸川乱歩著書目録』、近々上梓の運びとなりました。同書に準じて本ページでも記載スタイルを全面的に改めましたので、同書の凡例にあたる文章をここに「凡例」として転載する次第でございます。 |
|
【 凡例 】
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
本書には、大正十四年から平成十三年まで七十七年のあいだに刊行された江戸川乱歩の著書を記載した。乱歩の著書目録はこれまでにも編まれているが、本書は次の三点を参考に編纂した。
本書では、対象となる乱歩の著作を著書と収録書に大別し、著書は次の四種類に分類した。
収録書は、乱歩が序文や解説を寄せた他人の著書、乱歩作品が収録されたアンソロジーなどを拾った。作品の抄録や抜粋も採ることとし、註記にその旨を記した。 著書と収録書は、それぞれ次のデータを記載した。
記載は刊行順とした。同日発行の場合は自著、共著、翻訳書、編纂書、収録書の順とし、さらには書名の五十音順に拠った。全集や叢書に巻数またはシリーズ番号などが附されている場合はそれに準じた。 記載データの概要は次のとおり。 書名 表紙や扉、奥付から総合的に判断した。副題や全集名、シリーズ名は書名のあとに記した。書名の行末には、自著には刊行順に通し番号を入れ、それ以外の著書は「共著」「翻訳」「編纂」の別を明記した。収録書には「収録」と記した。 発行日 不明の場合は「―日」とした。 発行所 海外の発行所には所在都市名を附記した。文庫、新書などの叢書は発行所名のあとにその名称を掲げた。 判型 表紙のサイズに拠り、昭和十六年四月の用紙規格改定を境として、それ以前は旧称の菊判(21・8cm×15・2cm)、四六判(18・8×12・7)、三六判(18・5×10・5)、菊半截判(15・1×10・9)で、それ以後はB5判(25・7×18・2)、A5判(21・0×14・8)、B6判(18・2×12・8)、新書判(18・2×10・3=B40)、小B6判(16・8×11・2)、A6判(14・8×10・5)、B7判(12・8×9・1)で示した。変型判や著しく規格外のものは縦×横のサイズをセンチメートル単位で記した。 外装 函、カバーの別を示し、ない場合は「なし」とした。 頁数 ノンブルの最後の数字を採り、巻末の索引などが別建てとなっている場合は本文頁数のあとに「+」で併記した。巻頭の序文や目次が別建ての場合は記載の対象としていない。 別丁 本文と異なる用紙に刷られた口絵などの別丁があれば、その枚数を「丁」を単位として記した。 定価 戦前の予約出版などで価格が明記されていない場合は予約定価を掲げた。 編著データ 著、編、共著、共編、訳などの名義を記した。自著の「著」は省いた。共著には「共著」として乱歩以外のすべての共著者名を挙げ、奥付などに示された名義を「著」として記した。翻訳書では乱歩が著者となっている場合もあるが、一般の書籍は「著」、児童書は「作」として原著者名を記した。 意匠データ 装幀、挿画などの担当者名を記した。海外で出版された著作では、担当者が日本人の場合のみ名義を記した。 収録作品 原則として収録順に記載し、序文や解説など執筆者の記されている文章はその名義も掲げた。内容に応じて適宜改行を設けた。複数の収録作品に統一したタイトルが設けられている場合はゴシック体でそれを示した。〔 〕を用いて当該作品の章題などを記した場合もある。初刊作品は右肩にアステリスクひとつのルビを、初刊以降に改題された作品は最初の収録時にアステリスクふたつのルビを附した。無題の場合は便宜的にタイトルをつけ、末尾にアステリスクひとつのルビを附した。海外で出版された著作は収録作品に原題を附記した。 別冊附録 タイトルと頁数を示し、収録作品と執筆者名を記した。 典拠 記載データを確認した原本、ないしは依拠した資料を掲げた。名張市立図書館が当該書籍を所蔵している場合は■に、未所蔵の書籍でも公共図書館や個人の蔵書で確認できたものは●にその版数を記し、初版でない場合は発行年月日を附記した。■が重版だった場合、定価などの初版データを確認するために参照した版を●に記した。初版、第一刷などの呼称は原本に従ったが、版数が記されていない場合はすべて「初版」と表記した。目録A、B、Cに記録されている著作は▼にその目録の略号を示した。原本を参照できなかった場合は依拠した目録などの資料名を▼に掲げた。重版しか確認できなかった書籍も目録A、B、Cとそれらの資料に拠って初版のデータを記載し、▼に略号または資料名を記した。参照した資料は次のとおり。
註記は▼に先がけて記したが、最小限にとどめた。 表記は現代仮名遣いと新字体に統一したが、それらを採用した書籍で敢えて歴史的仮名遣いや旧字体が使用されている場合はそれを踏襲した。中国語の簡体字は繁体字に改めることとし、国内の書籍と同じく新字体によった。乱歩作品のタイトル表記の異同はそのまま記載したが、他の作品名や人名などの明らかな誤記は訂した場合がある。 著作総数は千四百二十四点。内訳は次のようになる。
編纂書には自作を採ったアンソロジーが収録書七点として含まれるため、著書と収録書の合計は延べ千四百三十一点となる。編纂書に乱歩の序文や解説など編纂に伴って執筆された文章が収録されている場合、その書籍を収録書とは見做していない。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
【 番犬追記 】2003年10月26日
|
| 『江戸川乱歩著書目録』刊行後に新たに確認された著書は、書名横の通し番号の欄に「▲」を記載して書誌データを掲げることにいたします。
2007年5月10日現在の著作総数は千四百三十一点。内訳は次のとおりです。
|
|
掲載●1999年10月21日
|