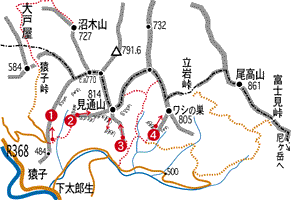|
'04、年の瀬にホームで遊ぶ |
||||||||||||||||||||||||||
|
倉骨林道から見る見通山(左)、鷲の巣(右)南面。この右手、尾高山にも岩場がある
|
||||||||||||||||||||||||||
| 年末、雪待ちの季節に見通山の周辺でうろうろ遊んだ。10月に南西尾根を登ってから、薮だらけの南面の壁を見上げて、できるだけロープなしで上まで登れないものだろうかと、いくつかのコースを考える。見通山には西と南東に明瞭な稜があり、隣の鷲の巣ピークにも南に稜が派生している。岩場を薮が覆っているので、行き詰まるかもしれないが、そこは出たとこ勝負と考えるしかないだろう。何はともあれ、自宅から30分のところで遊べるのだから、薮だらけだとかあれこれ文句言っていたら、バチが当たるってものだ。一緒におもしろがってくれたTYさん、Sさんはじめ、みなさま方に感謝。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (1) 見通山南西尾根('04.10.22、既報)
(2) 見通山西稜('04.11.29、TYさんと登る) |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (3) 見通山南稜('04.12.16、TYさんと登る) 大谷の倉骨林道分岐点の橋から眺めると、見通山南面の傾斜は、なんで薮だらけなのか分からないほど、ものすごく急に見える。しかし、岩が露出している部分には何本かの松の木が生えていて、なんとかルートが開けそうな気がする。 橋のたもと近くから、荒れた植林帯の中を行くと、だんだん右手へ振ってしまうので、適当な所で左の稜に乗る。ここもなんとなく踏みあとらしいものがあるが、西稜のようにハイカーは来ていないようだ。稜の左手(南壁側)と稜上を縫うようにたどって行くと、最後の50mほどが急になるが、露岩をブッシュを頼りに左右に捲くことができる。ここも南側は尼ヶ岳から大洞山にかけて眺めがたいへん良い。笹薮に突入すると、西稜ルートに出る。所要、1時間。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (4) 鷲の巣南西稜('04.12.10) 倉骨林道分岐から大谷の林道を300mほど行くと左手に涸れた谷がある。この左岸の植林帯を、鷲の巣下の林道まで 登って尾根に取付く。見通山の稜ほど明瞭でなく、丸い形状の斜面になっているが、右手のルンゼ側が切れ落ちているので、これを目当てにケモノ道を伝う。2ケ所ほど薮の覆われた露岩があるが、ジグザグブッシュ伝いに乗り越えると、急な斜面になり、ケモノ道が縦横に走っている。シカの糞だらけで、座る場所もないほど。この稜はシカの遊び場だから、なるべくならそっとしておきたい。天気がよく、汗だくになって鷲の巣ピーク着。(所要、1時間ほど) 下りは北のコルまで尾根を行き、西側の沢へ降りる。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| (5) 見通山南壁下降('04.12.26、K、TY、THさんと) 冬のアイゼン訓練とばかり、いくつかの稜を登降する、最後にTYさんが、ここなら早いと、見通山南稜の終了点近くから西稜へ向かって横断しはじめる。みんな何も考えずにゾロゾロついて行くが、当然大きな壁に出くわし、面倒だとばかり懸垂下降することにした。急なのは30mほどだと皆が思っていたが、薮の中から次々壁が現れ、結局4ピッチの複雑な下降をさせられた。岩の部分は外傾しており、トップのKさんが見通しのきかない、苦しいルート探しを強いられる。南壁の高距はロープで120mばかりあると考えてよい。とんでもない下降におびき寄せていただいたTYさん、心からありがとう。8環を持っていなかった私はおかげで首筋擦りむきました(><)/(南壁の岩を登るなら、西稜側の方が短いが比較的スッキリしているようだ) |
||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||