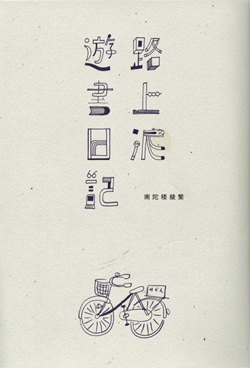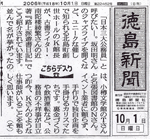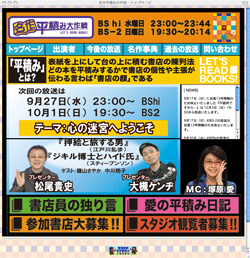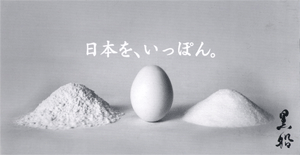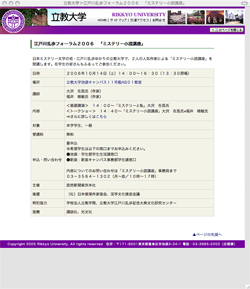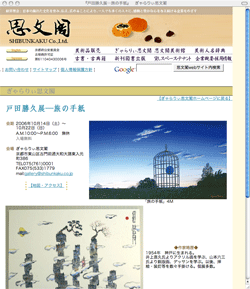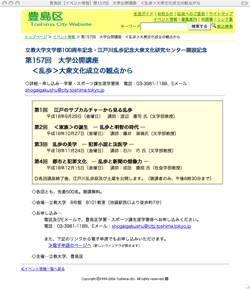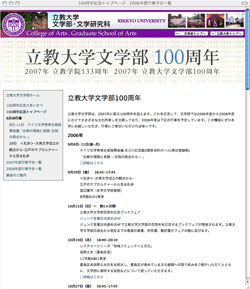|
2006年10月上旬
|
|
10月を迎えました。きょうもお知らせを一件。地域限定のご案内ですが、先日来お伝えしておりますとおり伊賀市のお寺で歴史講座が開かれます。本日は2006年度の全容をどうぞ。日々いがみあって生きてる伊賀地域住民のみなさんは、お暇でしたらお寺へ行きゃれ。いきなり仏罰がくだるようなことはありますまい。
ついでにもうひとつ、中国広東省の天川体育館で開かれているレスリング世界選手権は昨30日に六日目を迎え、わが遠縁の娘にしてアテネ五輪金メダリストでもある吉田沙保里選手が女子五十五キロ級で優勝、国際大会における連勝記録を「100+1」に伸ばしました。写真を二点も載せてくれてるサンスポの記事をどうぞ。 私もきのうテレビで観戦しておったのですが、はっきりいってこの子は強い。応援の必要がないくらい半端なく強い。わが必殺のスリーパーホールドも通用せんかもしれん。というよりあの鎧袖一触のタックルで速攻おだぶつか。ともあれ今後ともご支援ご声援をいただければ幸甚です。 きのうの夜は外で飲んで帰ったあとまた飲みながらテレビの格闘技番組とスポーツニュースをずーっと見つづけておりましたので、つまりずーっと飲みつづけておりましたので、けさの私はいつもの朝よりさらにぼーっとしているようです。
| ||||||||||||||||||||||||||
本日もまたお知らせから。南陀楼綾繁(なんだろうあやしげ、とお読みください)さんの新刊『路上派遊書日記』が出ました。版元のオフィシャルサイトではいまだ「近刊」の扱い、書影も掲載されていないようですからここに掲げておきましょう。画像をクリックすると別ウインドウに版元である右文書院のサイトが現れ出でます。 ブログ「ナンダロウアヤシゲな日々」に発表された2005年の日記を一冊にまとめた(とはいえ紙幅の都合によりおよそ三分の一の抄録だそうですが)四百ページを優に超える一冊。ご恵投をいただきましたのでぱらぱらひもといてみましたところ、2005年の4月に南陀楼綾繁さんが、というよりはご本名の河上進さんが季刊「本とコンピュータ」誌の取材でわざわざ名張市立図書館においでくださったときのことも記されております。むろん私の名前も出てきており、しかも私のことは本文のみならず脚註でも紹介していただいてありまして、えへん、まことにありがたいことであると思いつつ昨日したためたお礼のはがきがまだ机のうえにある。きょう投函してこなければ。 そうこうしているところへ速攻の反響一件。昨日付徳島新聞のコピーがファクスで届きました。「こちらデスク」なるコラムなのですが、徳島新聞の関係各位には見て見ぬふりをしていただくことにして、そのコピーを確信犯的にそのままごらんにいれましょう。クリックすると大きな画像が現れ出でます。 ごらんいただけましたか。南陀楼綾繁さんの新刊『路上派遊書日記』で「日本三大公務員」のひとりとして徳島県の「北島町創世ホールのK館長」があげられているのは頼もしいことである、みたいな記事なのですが、三大公務員の残るふたりは「小樽文学館のTさんと名張図書館のNさん」とのことで、いやー、おれもとうとう徳島県まで盛名を馳せてしまったか。日本三景になったみたいで面映ゆいぜ。 ちなみに『路上派遊書日記』は別冊栞つきで本体二千二百円。名張市内の本屋さんには並ばないかもしれませんが、名張市民のみなさんにもお薦め申しあげる次第です。帯から引いておきましょう。 ──ある時は大量の古本を買い込み、ある時は安居酒屋にしけこみ、常連客の話に聞き入る、またある時は本のイベントで大いに盛り上がる……仕事と私事の間をあっちへふらふら、こっちへふらふらのナンダロウ的生活。
|
名張市立図書館の江戸川乱歩リファレンスブック1『乱歩文献データブック』を上梓したとき、手にとってくださった方からいろいろと誤脱のご叱正を頂戴しました。あれが抜けてますねこれが洩れとるぞといったあんばいで私はそのたびに膏汗のにじむ様な、恐怖に近い驚きに撃たれたということはとくになかったのですが、いずれ増補改訂版を出さねばならぬであろうなとは考えました。その後インターネットというやつが急速に普及しましたので、とりあえず『乱歩文献データブック』の増補改訂はこの名張人外境で進めている次第なのですが。 『乱歩文献データブック』をつくることになったとき、私はみずからを省みて暗澹たる気分に陥りました。自分に足りないところがたくさんあるなと、あらためて気がついたからでした。なにしろ私はアカデミズムにはまるで縁がなく、書誌にかんしてもまったくの素人、あろうことか探偵小説にもたいして興味がないうえ古書にはとんと無関心。こんなことでいいのか、いいわけねーだろ、などといった煩悶に身もだえしながらつくった『乱歩文献データブック』でありましたから、刊行後にさまざまな方から自分に足りないところを補っていただけたのはありがたいことであったと思い返されます。なんと殊勝な。 で、あれが抜けたこれが洩れたという指摘をもっとも多く集めたベストワン作品は(こういう場合にベストワンという呼称がふさわしいのかどうか判断に苦しみますが)、むろんいちいちカウントしたわけではありませんから正確なところはわかりませんけれど、たぶん中谷克己さんの「『押絵と旅する男』論 江戸川乱歩の深層構造」ではなかったでしょうか。1993年6月、帝塚山短期大学日本文学会の「青須我波良」四十五号に掲載された一篇です。遺漏の指摘を受けて幾星霜、ミラボーの下をセーヌが流れ、新町橋の下を名張川が流れ、『乱歩文献データブック』の刊行から十年近い日月を閲したいまになってようやく増補を果たすというのはいかにもお恥ずかしく、怠慢のそしりは免れまいて。すまんなみんな。 この論文はのちに『母胎幻想論 日本近代小説の深層』という中谷さんの著書に収録されましたので、怠慢をお詫びする意味もこめてその内容というか目次をご紹介しておきたいと思います。版元は和泉書院、発行は1996年10月25日、本体二千五百円。いまも入手が可能なはずです。
それでこのどこにあるんだかわからなくなっていた『母胎幻想論』をようやく見いだすことができましたので、以下はこちらで──
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて「押絵と旅する男」の日付問題。乱歩の視線が青年期に、老醜への怯えを秘めながらもかつて若さと美をふたつながら手にしていた青年期の絶巓に向けられていたものか、はたまた幼年期に、不在の母への希求を秘めながらもかつて祖母と密着するようにして過ごしていた幼年期の始原に向けられていたものか、それとももっと別のものに投げかけられていたものか、それを断ずることはもちろんできません。しかしこの明治28年4月27日という日付はなにやらとても謎めいていて、私には蝉のおしっこのように気にかかる(どうよこの時代がかったおふざけ)。この日付を『江戸川乱歩年譜集成』に書き入れたいという誘惑は断ちがたい気がする。 手がないことはないでしょう。伝記的事実として年譜にそのまま記すのではなくて、明治28年4月のページに「明治二十八年四月二十七日」という項目を立て(項目といったって本文と同じ級数のゴシック体でいいのですが)、それにつづけてこれは「押絵と旅する男」で怪異が起きた日なのであるが、この日付にかんして平井隆太郎先生はこんなぐあいに、そして中谷克己さんはこんなぐあいに考察している、みたいなことを書き記しておけばそれでいいのではないか。 それでいいのではあるけれど、それやっちゃうと書誌としてのバランスが崩れてしまうやもしれぬ。なんかもう収拾がつかなくなってしまうのではないかという危惧をおぼえる。いったいどうしたものじゃやら。とはいえ明治28年4月27日という日付をどうするか、なんていうのはまだまだ先の先に思案すればいいことなのであって、とりあえず目先の作業を地味にこなさないことには話が進みません。 目先の年譜原稿で明治28年のパートを見てみますと──
まだこれだけである。この程度である。『探偵小説四十年』を虱潰しにしてから『貼雑年譜』にとりかかるつもりでおりますので、乱歩自身のことはまだ出てきてはおりません。『貼雑年譜』を開くのはいつのことになるのかな。 にしてもこうして眺めてみると、阿部豊にかんする記述はやはりいかにも多すぎましょう。私という人間は若き日に漫才作家をめざしていただけのことはあり、映画監督も含めた芸能人というか舞台人というか喜劇人、そういう人種に肩入れしてしまう傾向があるようで、ボードビリアン榎本健一のことなんかずいぶん長々しく書いてしまったものでした。いくらなんでもこれではな、とあとから原稿を削りはしましたが。やれやれ。 さて、ぶつぶついってないできょうも寸暇を惜しんで目先の作業を進めるか。どうせすぐ横道にそれてしまうのであろうけれど。
|
いやまいった。コンピュータメーカーからOSのアップデートにかんする連絡がありましたので、きのうさっそく最新版をダウンロードいたしました。電源をオフにしてけさを迎え、ふたたびオンにしてOSを立ちあげてみましたところ、どうもおかしい。不具合が出ている。マッキントッシュをおつかいでない方にはご理解いただけぬことでしょうが、いつまで待ってもクラシック環境というOSが立ちあがってこないの。立ちあがってくれないの。これではお仕事の一部に支障が出てしまうの。いやまいったなと思ってさっきからちょこっと焦っておりますので、本日はわりと簡単に。
さあOSが立ちあがってくれるようにあれこれやってみなければ。 |
ご心配をおかけいたしました。OSのアップデートにともなう不具合はどうやらアップデート後最初の起動時のみの現象であったようで、あれこれやってるうちになんとなく解決し、いわゆるクラシック環境も支障なく起動できるようになりました。パソコン画面にもおかしな点が見られたのですが、デスクトップなんとかをどうとかするという処理によってすんなりおさまりました。何をどうやったのか自分でもよくわからないのですが、まずはめでたしめでたし。 ではここで、カステラ好きの方に耳寄りなお知らせをひとつ。東京は自由が丘に8日の日曜、黒船というカステラ屋さんがオープンするそうです。こんなふうなダイレクトメールが届きました。 これまでの経験からいいますと、この手のダイレクトメールはたいていがちょっとおしゃれなお水関係のものです。ですから私はてっきり黒船という名前の飲み屋が開店するのだろうと早合点してしまい、いったいどこのお姉さんが店を開くのかとオフィシャルサイトにアクセスしてみたのですが、なんだ大阪は心斎橋にあるカステラ屋さんが東京都目黒区自由が丘1-24-11にお店を出しますという挨拶であったか。妙にがっかりしてしまったのですが、東京あるいはその周辺にお住まいのカステラ好きのみなさんにはこたえられない話だと思います。上の画像をクリックすると別ウインドウに黒船のサイトが現れ出でます。カステラマニアはぜひどうぞ。 乱歩もカステラが好きだったみたいで、昭和35年の「カステーラ・ノスタルジア」という随筆にこんなことを書いています。
こういう文章を眼にしただけで、ああ、『江戸川乱歩年譜集成』の幼年期のページには乱歩カステラ初賞味のことも書いておかねばならんな、と思ってしまう業の深さを何としょう。 業も深ければじつは欲だって深いみたいで、『江戸川乱歩年譜集成』のことをあれこれ構想していると妄想が水死人のようにふくれあがってきて始末に負えなくなってしまいます。あれもやりたいこれもやりたいそれはどうよといったあんばいなわけで、どうにもこうにも手に余る。私だって指折り数えればもう十年以上も乱歩という作家に関係するお仕事をつづけてきたわけなんですから、自分でも気づかないうちに乱歩の偉大さにあてられて自我肥大に陥っているということがあるのやもしれず(つまり乱歩の偉大さを自分のものだと勘違いして思いあがっているばか、それがおれなのさ、みたいな話なのですが)、こうなると乱歩を狂信し自分を過信してこれから何をやらかすか知れたものではないぞ実際、という危惧がないわけではありません。 ここはひとつ、最近読み返して眼についた漱石の文章を引いてみずからの戒めとしておきたいと思います。
明治45年1月に発表された「彼岸過迄に就て」から引用しました。「彼岸過迄」を朝日新聞に連載したときの「緒言」だそうで、底本は新潮文庫『彼岸過迄』。私には自分を漱石にたぐえる気などもとよりなく、それ以前にそもそも『江戸川乱歩年譜集成』は小説ではないのですけれど(ただし「作物」ではあるでしょう)、読み返していてこのくだりが不意に身にしみてきたことはたしかです。手腕を磨き衒気は棄て、天国の乱歩と地上の乱歩ファンに済まない結果だけはもたらさないように気をつけたいなと思います。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
漱石つながりでまいります。秋山豊さんの『漱石という生き方』が出たのはことしの春のことでした。奥付を確認すると2006年5月5日の発行で、版元はトランスビュー、本体二千八百円。版元オフィシャルサイトの紹介ページはこちらです。 私はこの本を眼にして、なんか垢抜けないなと思った。タイトルの話です。漱石という生き方。愚直であって洒脱でない。生硬であって柔軟でない。つまりは垢抜けてないなと感じたのですが、奥付の略歴で著者が岩波書店の編集部に勤務し、「1993年に刊行が開始された新しい『漱石全集』の編集に携わる。2004年、同社を停年退職した」人であることを知って読んでみる気になりました。 私はどうやら全集の編纂に従事する人間に格別な興味を抱いているようで、今年1月に出版された西村賢太さんの『どうで死ぬ身の一踊り』も著者が藤澤清造全集の刊行を企図しているらしいことから手に取った次第だったのですが、全集編纂者にとっては作家とその作品に対して愚直であったり生硬であったりすることがおそらく不可欠の条件でしょうから、それならそれで『漱石という生き方』というタイトルはすとんと腑に落ち、冒頭を立ち読みしてみたところこんな文章が眼を射ました。 ──私の希望は、漱石に寄り添って、よく彼の言葉を聞き取りたいということに尽きる。 低声ながらも毅然たるマニフェストだというべきでしょう。よほどの覚悟がないかぎり(それはむろん自負に裏打ちされた覚悟なのですが)、こんなせりふは決められません。そうかなるほど漱石に寄り添うのか、と私は納得し、これは漱石という生き方と漱石に寄り添うという生き方をポジとネガのごとく静かに併置した本ででもあろうかと想像しながら購入いたしました。 つづくくだりを引いておきましょう。
全集編纂者というのはこんなことまでやってしまうのか、と感心したり驚いたりしたその内容についてはここではふれませんが(全集の編纂を志す諸兄姉はぜひご一読ください、とは申しあげておきます)、この引用に記された著者の言葉をそのままパクって私の自戒としておきたいと思います。すなわち私は、それが乱歩であれあるいは乱歩の記述に登場してくる有名無名の数えきれぬほどの関係者であれ、対象に寄り添う姿勢で『江戸川乱歩年譜集成』を編纂してゆきたいということを、ここに表明しておきたい。
|
インターネットでお寺の名前を検索したら自分の名前が出てきたのでびっくりした、というおはなしからはじめます。 まず Yahoo! ニュースがこんなぐあい。 livedoor ニュースはこんなあんばい。 べつに驚かねばならぬことではありません。10月5日付毎日新聞伊賀版に掲載された「歴史講座シリーズ:15日から“寺子屋教室”で「大超寺に眠る先人達」 /三重」という記事が転載されただけの話です。むろん私もこの記事は眼にしていたのですが、なんだかこっ恥ずかしい気がいたしますから誰にも内緒にしておいたというのに、こんなローカルな話題まで Yahoo! ニュースだの livedoor ニュースだのにとりあげられてしまうというのはいかがなものであろうか。地域ニュースならばほかにもいろいろあるであろうに。ことの軽重などというものを一気に無効にしてしまうのがインターネット社会というやつなのであろうけれども。 それでこの記事にもありますとおり、10月15日に伊賀市上野寺町の大超寺というお寺で「同市出身の実業家、田中善助(1858〜1946)について名張市立図書館嘱託職員の中相作さんが講演する」というわけです。この田中善助という実業家を語るに際してはマックス・ウェーバーの「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」あたりを援用して伊賀地域における「資本主義の精神」の体現者と位置づけるのが都合がよろしいのですが、しかしお寺でありがたいおはなしをするのですから仏教にちなんだ話題のほうがいいのかな、そういえば長部日出雄さんは新潮新書『仏教と資本主義』において奈良時代のお坊さん行基に「資本主義の精神」の体現を見ていらっしゃったし、やっぱ仏教にからめるのがいいのかなと、これはもう招かれたお座敷にあわせてネタを演じなければならぬわれわれ芸人の宿命なのであって、ですから大超寺というのはそもそもどんなお寺なのかときのう「伊賀 大超寺」で Google 検索を試みたところ自分の名前が出てきたのでびっくりした、というおはなしでした。 名前が出てきたところで漱石からマックス・ウェーバーに流れてみましょう。もとより自戒の問題です。『江戸川乱歩年譜集成』編纂者としてのわれとわが身を亀甲縛りにしてしまう自戒の縄、本日はウェーバーの「職業としての学問」ということにいたします。底本は尾高邦雄訳の岩波文庫。
漱石からマックス・ウェーバーへというのはかなり強引な流れではあるのですが、私の眼にはふたりのいってることがとても似ているように見える次第です。これはつまり私がふたりの文章に自分にとってのいましめを見ている、見ようとしているということに過ぎません。ってことはつまり、いくら対象に寄り添おうとしても人間には結局こういうことしかできないのであろうか。
|
おっせーんだよばーか、とお叱りを頂戴するのは百も承知でお知らせ一件目。読売新聞東京本社主催の「読売江戸川乱歩フォーラム2006」が10月14日、立教大学池袋キャンパスで催されます。立教大学オフィシャルサイトの案内をどうぞ。 「ミステリー小説講座」と銘打って午後2時にスタートし、大沢在昌さんの基調講演ならびに大沢さんと福井晴敏さんによるトークショーがくりひろげられます。入場無料ながら申し込みが必要で、読売新聞オフィシャルサイトの「本よみうり堂」内ブログ「書店員のオススメ読書日記」9月28日付「「ミステリー小説講座」参加者募集」によれば申し込みの締切は10月5日でした。おっせーんだよばーか。知らんがな。 読売の乱歩フォーラムといえば私は昨年10月1日に開催されたフォーラムには足を運び(「乱歩地獄」という映画が上映されておりました)、忘れもしません新宿ゴールデン街の幻影城というお店で夜明かしをしたあげく山手線の始発で置き引きに遭うというおまけまでつけてもらって魔都東京をあとにしたものでありましたが、今年のフォーラムが開かれるという10月14日にはじつは京都へ行こうかなと私は考えておりました。江戸川乱歩リファレンスブックの装幀をお願いしている戸田勝久さんの個展「旅の手紙」が開幕する日だからです。会場は京都市東山区古門前通大和大路東入元町のぎゃらりぃ思文閣、会期は22日までとのことで、これが本日のお知らせ二件目となります。 よーし。とりあえず読売の乱歩フォーラムはスルーと決めるか。だいたいどこが乱歩フォーラムか。乱歩にはさして関係のない内容ではないか。2004年にはじまったと記憶するこの乱歩フォーラム、すでにして消化試合と化してしまった観が否めないように私は思う。しっかりしろ読売。 お知らせ三件目。メールで教えていただいたのですが、「黒蜥蜴」と「陰獣」を合わせ技一本にした英訳本『Black Lizard and The Beast in the Shadows』が黒田藩プレスから刊行されました。オフィシャルサイトの紹介ページをどうぞ。 さっそく Buy at Amazon いたしました。この本のことはイギリスのミステリ同人誌で紹介されていたそうなのですが、黒田藩プレスから「黒蜥蜴」の英訳が出ることはいつであったか掲示板「人外境だより」で大熊宏俊さんから教えていただいておりました。教えていただいてはおったのですがその後ぼんやりしておりまして、この『Black Lizard and The Beast in the Shadows』は今年1月に刊行されていたみたい。おっせーんだよばーか。知らんがな。
|
きょうもまた、おっせーんだよばーか、とお叱りを頂戴するかもしれません。立教大学で開催されつつある乱歩イベントのお知らせです。立教大学と豊島区の主催による公開講座「〈乱歩〉大衆文化成立の観点から」が9月から12月まで月一度ずつ催されております。私はぼんやりしていてまったく知らなんだのですけれど、ご親切にメールでお知らせくださった方がありました。 まずは豊島区オフィシャルサイトの紹介ページをどうぞ。 第一回講座はすでに終了しており、この酔っぱらいW先生(ここでW先生の名誉のためにひとこと説明を加えておきますと、W先生イコール酔っぱらいであるというわけでは全然ありません。私が以前、ただ一度のことではあるのですが、W先生から「この酔っぱらい」ときついお叱りを頂戴してしまったというだけの話です)が「江戸のサブカルチャーから見る乱歩」というなんとも面白そうなタイトルで講師を担当していらっしゃいます。立教のサイトにレポートが掲載されるのを待ちたいと思います。 この公開講座は立教大学文学部の創立百周年と江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの開設を記念するもので、2007年の百周年へ向けて今年はこんな行事がくりひろげられております、という立教大学オフィシャルサイトの紹介ページをどうぞ。 当サイトでも遅ればせながら「番犬情報」にPRを掲載いたしました。
|