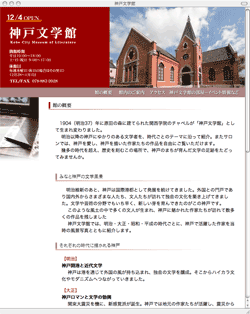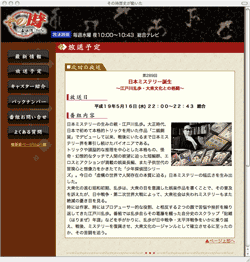|
2007年5月上旬
|
|
|
1日 ▼フラグメント忍法帖 誤認でニンニン
2日 ▼フラグメント忍法帖 東上と下阪の謎 3日 ▼フラグメント忍法帖 寡黙それとも饒舌 4日 ▼神戸文学館で『真珠郎』をどうぞ 5日 ▼タルホとフラグメント 7日 ▼タルホフラグメントから Rampo Fragment へ ▼江戸川乱歩年譜集成 「鏡」 探偵趣味の会 8日 ▼名張市からプレゼントのお知らせです ▼RAMPO Up-To-Date 漱石、龍之介、賢治、乱歩、そして謎解き 四季が岳太郎 9日 ▼ある山中における重大で特異な数日間の記憶 ▼RAMPO Up-To-Date 日本ミステリー生誕の地 陳舜臣 10日 ▼ある山中における「屋根裏の散歩者」擱筆の日 ▼江戸川乱歩著書目録 タルホ事典 |
|
月が替わりましたところで「江戸川乱歩年譜集成」におけるフラグメントその他の説明をば。
これが記載の基本スタイルとなります。日付と事項というのは、要するに何月の何日にこれこれこういうことがありましたという説明です。いわば年譜の本文。 そのあとに引用すべき文献があれば引用する。『探偵小説四十年』からの引用は「引用文のタイトル」とあるところに「探偵小説四十年」というタイトルと引用したパートの章題とを記し、「引用文の執筆者」のエリアにはそれが『探偵小説四十年』の何年度に記されているのかを明記する。例をあげればこんな感じ。
初出や底本といった典拠の記載はいささか煩瑣ではありますが、なにしろリファレンスブックなんですからリファレンスのためのデータとして煩をいとわず明示しておく。 それからもうひとつ、年譜本文の記載がこんなふうになってるものもあります。
私の使用しているブラウザで行頭二字下げくらいに見える見当にページを設定してあるのですが、これは『探偵小説四十年』以外の文献にもとづいた事項であることを示しています。手っ取り早く例を引くならば──
これは『探偵小説四十年』ではなくて『子不語の夢 江戸川乱歩小酒井不木往復書簡集』に依拠した記載事項ですから、年譜本文の段落が二字下げとなっている。 それでこの例でいえば「近くに東上のよし是非御立寄り下さい(。)御待ちして居ます」というのがフラグメント。こんなのいちいち引用しなくてもとお思いの方もいらっしゃいましょうが、そもそも私は引用という行為が大好きで、それにたとえば不木なら不木という執筆者ないしは不木が執筆した文章に対してできるだけ誠実でありたいと考えておりますので、ならば不木が記したそのままを引用するのが望ましい。 逆にいいますと、この場合の「小酒井不木、乱歩に葉書を出し、年頭に書簡で伝えられた来意に応諾する」という年譜本文、これは私の書いた文章なのですが、これがなんかやだ、という気がする。理想をいえば『江戸川乱歩年譜集成』にはただフラグメントのみが隙間なく整然と美しく並んでいて編纂者たる私の文章など一行も見あたらず、しかし年譜を通読するとその背後に編纂者の意志や企図や批評や見識といったものが、いや自分で見識といってしまってはまずいですけど、そうしたものが確乎として存在していることがうかがえる。そういうのがなんかかっけー、とか私は思いますので、自分の文章が出てくるのはなんかやだ、という気がしてくるわけなのですけれど、さすがに編纂者が年譜本文を書かないわけにはまいりますまい。 それにしても私はどうしてこんなことを考えてしまうのか。つらつら案じますに伊賀の忍びの伝統ででもあるのでしょうか。忍びも達人の域に達すると自身の気配を完全に消し去り、ひとつの虚無と化して任務を遂行すると伝えられるわけなのですが、そういうのがほんとかっけーなと私は思う。しかし伊賀の忍びも最近はずいぶんと相場を下げているようで、あれは上忍とか中忍とか下忍とかいうのではなくてたぶん愚忍とか痴忍とかいうのでしょうけど、やれ忍者議会じゃほれ手裏剣対決じゃと何かにつけてメディアに露出したがるのが伝統に生きる忍びの眼には見苦しい。しかし伊賀上野観光の PR なんだそうですから、まあどうぞお好きにというしかありません。おーい、愚忍だか痴忍だか知らんけど今度ゴルフやるときは地震の起きない日を選ぶんだぞー。 それでフラグメントを寄せ集めてみますといろいろなことがわかってきて面白い。面白いというよりは、乱歩先生だいじょうぶっすかー、みたいな心配さえおぼえないではありません。つまり乱歩の事実誤認がやたら判明してくるわけです。 『探偵小説四十年』の大正14年度における事実誤認といいますと、いまやよく知られたところでは名古屋駅置き引き事件があります。乱歩は小酒井不木をはじめて訪ねたおり名古屋駅で置き引きに遭ったと記しているのですけれど、それはじつは一年後の大正15年1月に起きた事件なのであった。置き引きに遭ったというだけでもまぬけなのに事件発生の年までまちがえて、いやいや、私だっておととしの秋に JR 山手線の始発列車内で置き引きに遭ったまぬけですから偉そうなことをいうのはやめておきましょう。 ほかにはたとえば西田政治と横溝正史にはじめて会った日の日付に事実誤認があります。これを最初に指摘したのはおそらく脚註王村上裕徳さんによる『子不語の夢』の脚註で、乱歩が正史からもらった葉書に「昨日は失礼致しました」とある「昨日」を初対面の日だと誤解したことが躓きの石となったわけなのですが、正史のいう「昨日」は探偵趣味の会の最初の会合が開かれた日のことであり、三人の初対面はそれ以前のことでなければおかしいというのが真相なわけです。 ところでこの初対面の日のことは西田政治と横溝正史の両人もそれぞれに書き記していて(ふたりとも日付に関しては乱歩の事実誤認を踏襲しているのですが)、フラグメントばかの私はそれらをしっかり記載しました。そのひとつ、西田政治の「乱歩さんと私」には当然『探偵小説四十年』からは知りえない事実がつづられています。たとえば乱歩が手紙でまず政治に声をかけ、政治が援軍として正史を呼びつけたらしいことがわかりますし、三人とも和服であったとか話し合ったあと三人で元町通りを歩いたとかいったディテールが鮮明になってきて、編纂者たる私には乱歩の年譜がいきいきとした精彩を帯びてくるように感じられる。しかし政治は「何分にも三十年前のことで記憶が薄れている」とも書いていて、編纂者たる私はがっくり肩を落としたりもする。 ほかにもいろいろあります。これは今回はじめて気がついたことで、乱歩先生だいじょうぶっすかーと思うと同時におれの頭もあんまり大丈夫じゃねーなーと実感させられた誤認がひとつ。それを明らかにしたフラグメントは「新青年」大正14年3月号の森下雨村による編集後記「編輯局より」でした。 大正14年1月中旬、乱歩は名古屋の不木を訪ねたあと東上し、森下雨村ら「新青年」関係者と対面します。『探偵小説四十年』には日付はいっさい記されていないのですが、この「編輯局より」には乱歩の歓迎会が1月16日に開かれたと記されていて、これは得がたい記録である。みたいなことは「編輯局より」を引用してこの伝言板の「本日のアップデート」に記しもいたしましたが、この「編輯局より」にはもうひとつ大切な事実が記録されていました。
あッ、と年譜編纂者たる私は叫んだ。『探偵小説四十年』にはどう書いてあるか。牧逸馬が英訳していたのは「心理試験」ではなくて「D坂の殺人事件」であったと書いてある。また事実誤認なのである。乱歩は逸馬からの手紙を引いて──
ありえない。こんなことはありえない。「D坂の殺人事件」は「新青年」の大正14年新春増刊号に掲載された作品で、実際の発売日は前年12月初旬ですから脱稿は秋ごろのことと考えられます。だったら「あの短篇を書いた直後、私が上京したのを機会に、探偵作家の会合があって」なんてことはありえません。上の引用箇所は光文社文庫版全集『探偵小説四十年(上)』の103ページにあるのですが、95ページに乱歩はその歓迎会のことをこんなふうに書いてるわけ。
大正14年1月にはじめて会った牧逸馬に大正13年の秋に会ってるわけがありません。 こうなると私には、乱歩がいったいまたどうして「心理試験」ではなく「D坂の殺人事件」が翻訳されたと(結局は翻訳されずじまいだったわけですが)思い込んでいたのか、それが気になってくる。どのような無意識の動きが乱歩をそんな誤謬に導いたのか。うーん。ようわからん。 しかし乱歩先生だいじょうぶっすかー、という以上に『探偵小説四十年』におけるこんな明らかな矛盾にさえ気がつかなかった私はめいっぱい大丈夫ではないであろう。だいたいちょっと考えてみれば、「D坂の殺人事件」が翻訳にふさわしい作品でないことくらいすぐに察しがつきそうなものではないか。タイトルにアルファベットが入っているからなんとなくモダンな印象があるけれど、障子の格子の隙間から太い棒縞の浴衣がちーらちらなんて、そんな話が欧米向きか? それでもってまだある。まだあるのじゃ。乱歩の事実誤認らしきものはまだあるのじゃよ皆の衆。私はなんだか泣きたいような気分なのですが、情け容赦なく『探偵小説四十年』から引きましょう。探偵趣味の会について述べられたパートです。
ここでフラグメント忍法、春日野緑の「乱歩君の印象」の術。昭和2年に発表された文章です。
話がぜんっぜんちがうじゃん。乱歩は春日野緑から誘いがあって大阪毎日新聞社を訪ねたと記し、春日野のほうは乱歩から手紙が来て自宅で会ったとしている。春日野は二年前のこと、それにひきかえ乱歩は二十五年前のことを回想しているのですから、たぶん春日野のいってることが事実なのかなという気はするけれど、しかしそんな曖昧な根拠で乱歩が誤認していたと断ずるのはなんだかしのびない。 そこでまたフラグメント忍法、今度は乱歩自身のフラグメント「探偵趣味の会を始める言葉」の術。「『探偵趣味の会』」というタイトルで「新青年」大正14年6月号に発表された文章です。
乱歩先生はこのように「星野龍猪君に相談して見た」とお書きじゃ。乱歩先生のほうから話をもちかけたのじゃな。ただしこの点は、春日野緑から誘われて会ったその席で、乱歩先生のほうから『探偵小説四十年』にあるごとく「一つ探偵趣味の会を作ろうじゃないか」と切り出したということであったのかもしれぬ。じゃがそれにしても、最初に会いたいという手紙を出したのがどちらであったのか、会った場所が大阪毎日新聞社だったのか春日野緑宅だったのか、そしてその時期は大正14年の4月だったのか春日野のいう「冬頃」であったのか。わからんことはたくさんあるのじゃ。 ここでふと気になって、私は中島河太郎先生の『日本推理小説史』をひもといてみました。第二巻の第七章「探偵趣味の会」には、ああ、やっぱりこんなふうに記されているではありませんか。
中島先生は『探偵小説四十年』に全面的に依拠して筆を進めていらっしゃったようです。それはまあ当然といえば当然のことなのですが、なんだかほんとにどうよまったく。 ほかに傍証はないものか。私はほとんど涙目になって川口松太郎の「乱歩讃」を読んでみました。「新青年」の昭和10年1月号に掲載された随筆です。『探偵小説四十年』にも引用されておりますので、光文社文庫版上巻の146、147ページをお読みください。 それでもってこれがまた傍証というかなんというか、事実関係をいっそう複雑にこんがらがらせてくれるフラグメントなのであった。「江戸川乱歩年譜集成」の大正14年のページでこの随筆をどう扱うべきか、私はいまだ思案に暮れておるわけなのですが、とりあえず記された事実を追ってみると── (a)「苦楽」の編集者だった松太郎、守口に住んでいた乱歩をいきなり訪問した。探偵小説を流行させたいという乱歩の熱意に感じ入り、乱歩を中心に探偵作家を糾合する計画をたてた。 (b)その第一回会合を六甲の苦楽園で催した。ひどい雨で参会者は少なく、松太郎と乱歩のほかには三人くらい。なかに横溝正史がいて、初対面だというのに「苦楽」の編集方針に辛辣な批評を加えた。 (c)当時、大阪毎日の星野龍猪と和気律次郎も探偵小説を隆盛に導きたいとの野心に燃えていた。これが乱歩と結んで探偵趣味の会を結成した。 (d)その第一回の催しを大毎のホールで開いた。来会者から会費五十銭を徴収し、余興にルパンの映画を観た。 最後の(d)は『探偵小説四十年』の引用では省略されているのですが、まず(a)から見てみます。松太郎から乱歩へのファーストコンタクトは一通の書状で、『貼雑年譜』にスクラップされた封筒には乱歩による「大正十四年四月九日」という書き込みがあります。用件は「苦楽」への執筆依頼、「成る丈け早くお願ひいたしたいのですけれど、御諾否を伺はせて下さいまし」とありますから、松太郎が乱歩を訪ねたのは4月9日からまもなくのことであったと考えられます。 (b)の日付も不明ですが、雨だったというのですから梅雨のことか。 (c)にある探偵趣味の会が発足したのは4月11日。 (d)に第一回の催しとあるのはどの催しのことか。探偵趣味の会の第一回の会合は(c)の4月11日なのですが、この日のことを指しているのではないでしょう。松太郎が乱歩に手紙を出したのは4月9日のことですから、その翌々日の11日にはまだ対面も果たせていなかったにちがいない。大毎のホールで開いたというのですから、松太郎が10月25日に苦楽園で催された探偵ページェントと勘違いしていたということもありえないでしょう。 いやしかし、しかしどうも、どうもこれは、いやしかしどうもこれでは、ふと気がつくと私はいまやそこに確実に勘違いや事実誤認が存在しているということを前提として人の文章を読んでいるではありませんか。なーんかやな性格。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なーんかやな性格、ていうかこれが伊賀の忍びの本性なわけです。たとえ親子兄弟のあいだがらであっても相手を絶対に信用しない猜疑心のかたまりのような人間でなければ優秀な忍びにはなれません。ですから私も『江戸川乱歩年譜集成』の編纂にあたっては乱歩の述べているところをそのまま鵜呑みにすることなどけっしてなく、債鬼のように仮借ない資料批判を血も涙もなく展開したいと念じている次第なのですが、性格がいよいよ悪くなってしまいそうではある。 それでなくても私は「『新青年』趣味」第十二号の「脚註王の執筆日記【完全版】」において、かの脚註王村上裕徳さんから、 ──ボクは、中さんは、そうとうにイケズや、思います。 とのご託宣をたまわった人間なのであるが(「いけず」の語義は Yahoo! 辞書のこのページでどうぞ)、『江戸川乱歩年譜集成』編纂者として余儀なくいけずの王道を究めることになるのであろうかしら。 とはいえ、たとえばきのうの伝言をお読みいただいた乱歩ファンのみなさんには、『探偵小説四十年』の徹底した資料批判が必要であるという事実はご理解いただけたのではないかと拝察いたします。徹底した資料批判、なんてことになるともとより私の手には余る作業だといわざるを得ず、それにだいたいが天国の乱歩からも、 ──いけず……。 とかいわれたりしそうな気がしてなんかやだ。 いや。 いやいや。 天国の乱歩が私にむかって、 ──いけず……。 などというわけがありません。ある意味聖典視されてまったく無批判な引用や孫引きがあっちこっちで行われている『探偵小説四十年』ではあるけれど、たとえば大正14年度の記述内容ってのは結局どんなものなのかというと、五十五歳の人間が二十五年前、自分が三十歳だった当時を回想した文章であるに過ぎません。手許に『貼雑年譜』をはじめとした参照資料があったとしても、勘違いや事実誤認、記憶の錯誤や修正はいくらでも生じてくるのが当然でしょう。だから私は天国の乱歩から、おかげで昔のことがよくわかったと感謝されこそすれ、 ──いけず……。 などといわれねばならぬ道理はないのである。そのはずである。そのはずではあるのであるが、まあいいか。 それでは伊賀の忍びにしてフラグメントばかでもある『江戸川乱歩年譜集成』編纂者がきのうにつづいてお届けするフラグメント忍法帖第二弾。本日は東上と下阪の謎に迫ります。いや迫ったりはできません。謎を提示してみるだけです。 大正14年1月、乱歩は大阪から上京しました。『探偵小説四十年』にはただ「一月中旬」とあるだけで、日付は明らかではありません。しかし「新青年」大正14年3月号に掲載された森下雨村の編集後記「編輯局より」によりますと、「新青年」関係者が乱歩を歓迎する小宴を催したのは1月16日のことであった。これはきのうも記しました。 乱歩はその小宴が東京に着いた日の「翌晩か翌々晩」のことであったとしています。ここでは翌々晩であったと仮定しましょう。関係者に連絡する時間も必要なら関係者にだって都合というものがあったでしょうから、一日あけて翌々晩のことであったと見ておく。すると乱歩の動きはこうなります。
なんとも空白の多いスケジュールです。ちなみに1月24日という日付がどこから出てきたのかというと、『子不語の夢 江戸川乱歩小酒井不木往復書簡集』収録の「〇一〇 乱歩書簡 一月二十四日 封筒便箋4枚」にこうあるからです。
1月24日付の書簡に「本日帰阪致しました」と書かれているのですから、これは真に受けるしかないでしょう。ほんとはもっと早く帰ってたんだけど不木に礼状を出すのを忘れていて、あわてて書こうとしたのだけれど帰阪から何日もたってからの手紙では人としていかにも実がない、誠が感じられぬ、だから嘘ついて24日に帰ったことにしとこっと、みたいなことであった可能性もないではないけれど、しかしそんなことまで疑いはじめたら際限というものがなくなってしまいます。それに乱歩はたいへん律儀な人でしたから、帰阪したその日に関係者への礼状をしたためたはずである。ここはいくら伊賀の忍びとて乱歩の言を信じることにして、だからこの空白の多いスケジュールはどうよということになる。 不木宛書簡に名の見える馬場孤蝶、星野龍緒と東京で対面したことは『探偵小説四十年』には記されていないのですが、このふたりと宇野浩二でわずか三人。不木宛書簡にはほかに誰を訪ねたとも書かれていませんから、東京で会った探偵小説ないしは文壇の関係者はこれだけであったとして、たとえば14日に森下雨村、15日に馬場孤蝶、16日に星野龍緒、その夜には「新青年」の寄稿家、17日に宇野浩二といった日程で面会してゆけば四日間でこなせるスケジュールなのである。 と書いて気がついたのですが、「新青年」大正14年3月号の「編輯局より」にはこうありました。
欠席だった「星野」というのは星野龍緒のことでしょうから、乱歩は16日には星野に会っておらず、17日以降に対面を果たしたということになるでしょう。しかしそんなのは些細な問題であって、早ければ17日には用事が済んでいたはずなのに、乱歩の帰阪が24日になったのはいったいなぜなのか。 宇野浩二の証言を見てみましょう。乱歩が菊富士ホテルへ訪ねてきたときのことが、宇野の「日本のポオ──江戸川乱歩君万歳」にはこんなふうに描かれています。
これは大正15年の1月、つまり乱歩の訪問から一年後に書かれた随筆なのですが、ここにある「一両日前に東京へ来たのであるが今夜にも帰るつもりである」という乱歩の言にもとづいてスケジュールを組み直してみると、雨村と会った日の翌々晩ではなくて翌晩に歓迎会が開かれたことにして──
これならば乱歩の言のとおりということになるだろう。しかし乱歩の帰阪は18日ではなく24日なのである。『子不語の夢』にそう書いてあるのである。 あ。 もしかしたらあれか。 『子不語の夢』に誤植があるのか。 それとも乱歩書簡をちゃんと判読できてないのか。 そんなことも私は考えた。『子不語の夢』でお骨折りいただいたみなさんにはほんとに申しわけない話であるけれど、伊賀の忍びは猜疑心のかたまり、どうぞ許してくださいな、と心で詫びながら『子不語の夢』附属 CD-ROM に収められた乱歩書簡の写真を見てみると、そこにはちゃんと、 ──廿四日 とあるではないか。『子不語の夢』スタッフのみなさん、疑ったりして本当にすみませんでした。 もうひとつの手がかりとして宇野浩二の手紙があります。これは『探偵小説四十年』にも引用されていて、光文社文庫版全集上巻の113、114ページをお読みいただきたいのですが、そこにこうあります。
これは1月26日付の書簡で、『貼雑年譜』にもスクラップされており、日付はたしかに「二十六日」です。事実関係を推測してみますに、乱歩は東京で菊富士ホテルに宇野浩二を訪ね、「心理試験」が掲載された「新青年」を手渡した。そして大阪に帰ってから、今度は「D坂の殺人事件」が掲載された「新青年」を添えて礼状を送った。帰阪は1月24日。その日のうちに礼状を書いたとして、24日に大阪で投函された郵便物が26日に東京に到着するのかどうか。当時の郵便事情がよくわかりませんからなんともいえませんが、不可能なことではないのではないか。もしも不可能なのであれば、乱歩の帰阪は24日よりも前であったということになります。 いや、いやいや、乱歩が「D坂の殺人事件」の載った「新青年」を東京滞在中に送っていたという可能性もあるのですから(げんに小酒井不木には東京からも手紙を出していたことが『子不語の夢』で確認されます)、1月26日付の宇野浩二の手紙もたいした手がかりにはならないか。うーん。まいった。 ですから結論といたしましては、不木への手紙にあるとおり帰阪はやはり1月24日のことで、となると乱歩は東京に十日間も滞在していたということになります。何をやっていたのか。博文館に足を運んで森下雨村と探偵小説談義に花を咲かせるとか、そんなことをしていれば時間はすぐに過ぎてしまうでしょうけれど、乱歩はむしろ早く大阪に帰りたかったのではあるまいか。「新青年」の寄稿家に知己ができ、探偵小説の隆盛を実感し、自分が探偵作家として大きな期待を寄せられているという事実も肌身に感じたことでしょうし、敬愛する宇野浩二に会うこともできたわけですから、かくなるうえは早くうちに帰って「赤い部屋」を書こうっと、今度はプロバビリティの犯罪だもんねー、とか思って大阪まで矢のように帰ってゆくのがふつうではないのかしら。だというのに東京で何をぐずぐずしていたのか。 あるいはまあ、宇野浩二に別れを告げて菊富士ホテルを出たあと、東京駅にむかう途中である不思議な事件に遭遇し、それを解決するために東京にとどまりつづけたなんてことがあったりしたら面白いとは思うのですが、実際にはそんな小説みたいなことあるはずもないしなあ。やっぱもちまえの放浪癖で、都会の雑沓をあてもなくふらふらしたりなんかしてたのかしら。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まいった。むろん「江戸川乱歩年譜集成」のことでまいってるわけですが、フラグメントをたったかたったか掲載してゆくとだんだんえらいことになってくる。 けさなど大正14年の5月14日にいきなり、 ── ヘンリー・ライダー・ハガード、六十八歳で死去。 なんてのが出てまいりまして、こういう歴史事象が前後の脈絡とは関係なしに不意に顔を出してくるのが年譜というものの面白いところなのですが、違和感を感じる方もいらっしゃるかもしれません。 しかしそんなのはフラグメントの問題ではありませんからこの際どうだってよろしい。問題なのはフラグメントが増えてくるとトリビアルなところばかりが眼につくようになってしまい、年譜としてのおおまかな流れが見えにくくなってくるようだという一事です。これはいささかまずいか。 問題を回避する方法はあります。フラグメントの本文を隠してしまうことです。すなわち大正14年のページには年譜本文とフラグメントのタイトルならびに執筆者名だけを記すことにして、そのタイトルをクリックするとブラウザの別ウインドウが開き、その時点ではじめてフラグメントの本文が読めるようになる。そうしておけば問題はクリアされることでしょう。フラグメント忍法のうち火遁の術でも水遁の術でもなく、ウインドウ遁とか窓遁の術といったことになるのでしょうか。その場合、フラグメントなんてたいていは短い文章なのですから、別ウインドウは小さなサイズで開くようにするのがおしゃれである。これは可能です。そのように設定すればいいだけの話です。 しかし私にはその方法がわからない。新たに開かれるウインドウのサイズは縦が何ピクセルで横が何ピクセルと設定するのはごく簡単なことであるはずなのに、その方法がわからない。サイト構築ソフトのヘルプを開いてあっちこっち眺めてみても、いったいどういった項目を参照すれば自分が知りたい操作方法にたどりつけるのか、それさえわからなくて朝から途方に暮れてしまう。するうち私は、いや待てよ、と思い返す気になりました。年譜本文とフラグメントとは、あくまでも同一のページの上で緊密に照応し合っていなければまずいのではないか。 フラグメントってのはいったい何か。『探偵小説四十年』の記述を、ということは年譜本文の記述を相対化するための素材である。読みたいときだけ読めるというのではまずいのではないか。意地の悪い奥方のようにいつも年譜本文にぴったり寄り添っていないことには、年譜本文だけが事実としてひとり歩きし誰かと浮気してしまうことになるのではないか。 例として大正14年4月の年譜本文を引いてみましょう。 (a)乱歩、春日野緑(星野龍猪)から手紙で誘われ、大阪毎日新聞社を訪ねて面会する。その初対面の場で、探偵趣味の会を結成する相談がまとまる。 (b)乱歩、森下雨村に手紙で探偵趣味の会のことを伝える。京阪神に住む探偵小説同好者の名前と住所を問い合わせ、京都の山下利三郎、神戸の西田政治と横溝正史を教えられる。 (c)乱歩、神戸で西田政治と横溝正史に会い、探偵趣味の会に入会することの承諾を得る。 以上三件、いずれも日付は不明、じつは4月のできごとであったかどうかも怪しいのですけれど、乱歩は、 ──大正十四年四月ごろだったと思う。 としてこれら一連の歴史事象が4月ごろに生起したと記しています。 さらに年譜本文をたどってゆくと、4月11日に大阪毎日新聞社で探偵趣味の会が発足したという記述にぶつかります。この日付はたしかな日付です。『探偵小説四十年』にも引かれているとおり小酒井不木の書簡でそれが証明できますし、例の横溝正史の葉書も傍証になります。 ここで人は何を思うか。上に引いた(a)から(c)までのできごとはほんとに大正14年4月のことなのか。どうもそうとは思えない。ていうか絶対にちがうと思う。あれだけのできごとが4月の上旬だけに収まってしまうはずがない。ならばいつなのか。それを考える手がかりこそがフラグメントなのであって、たとえば4月9日付の不木宛乱歩書簡にはこうあります。
「二三の人々」というのは春日野緑、西田政治、横溝正史のことでしょう。ならば「逢つて話して居た」「大分以前」というのはいつのことか。春日野緑のフラグメント「乱歩君の印象」を見てみる。
「一昨年」というのは大正14年のこと、その「冬頃」というのですから1月か2月か、そういった見当になるでしょう。そのころに何があったか。今度は乱歩自身のフラグメント、1月24日付不木宛書簡を見てみます。東京から帰阪した日の手紙です。
つまり乱歩は1月に上京したおり、森下雨村から京阪神の探偵小説同好者の名前やたぶん住所も教えられていたわけです。ところが『探偵小説四十年』にはこんなぐあいに書かれている。 ──そのとき、私は「新青年」編集長の森下さんに手紙を出して「探偵趣味の会」のことを報じ、京阪神の同好者の氏名住所をたずねたが、それに対して、森下さんから、たしか京都の山下利三郎、神戸の西田政治、横溝正史の三君の住所を知らせて下さったのだと思う。 これは春日野緑と初対面を果たしたあとの、つまり大正14年4月ごろのアクションとして回想されていることなのですが、事実とは相当に異なっているのではあるまいか。ならば事実はどうであったか。推測してみますに、乱歩は1月24日に東京から帰ってきた。「赤い部屋」の執筆という当面の課題をこなしながら、いっぽうで「好きの道を語り合」うべくまず春日野緑にコンタクトを取り、つづいて雨村から知らされたアドレスを頼りに西田政治に手紙を出した。そういったところなのではなかったかしら。 ですから上に掲げた年譜本文のうち、4月ごろのことだったという(a)はそもそもそんな事実があったかどうかさえ疑わしく、実際は春日野緑の「乱歩君の印象」にあるごとく、乱歩が春日野に連絡してまだ寒い時期に春日野宅で初対面を果たしたものとおぼしい。つづく(b)だって、何もその時点で雨村に手紙を出して京阪神地方に住む探偵小説同好者の住所氏名を問い合わせる必要はなかったであろうと思われますし、それが4月のことであったはずもない。そして(c)、政治正史との初対面ももとより4月11日のことではなく、たぶん2月か3月のことであったはずである。どっちかっていったら2月かな。 みたいなことを人は想像するわけである。「江戸川乱歩年譜集成」の大正14年のページの閲覧者は必ずそのような思いを馳せるはずなのである。ただしそれは年譜本文とフラグメントとが同一ページ上で緊密に照応し合っている場合の話であって、大正14年のページに年譜本文とフラグメントのタイトルおよび執筆者名のみが記載され、フラグメントの本文がウインドウ遁とか窓遁の術で隠されてしまっているのであれば、人はそこまで緻密な想像力を働かせて年譜を読み込んでくれないのではあるまいか。 したがいまして当面の結論としては、大正14年のページに年譜本文とフラグメントを同時に存在させたままで作業を進めることとしたい。とりあえず1月から12月まで一貫したページをつくってしまってから、そのあとでいろいろあれこれ細かい点について考えることといたします。 それともうひとつ、私にはフラグメントが年譜のおおまかな流れを見えにくくしてしまうという問題以外にもうひとつ気になることがあって、それは年譜編纂者がここまで寡黙であっていいのかどうかということである。必要最小限の言葉で年譜本文を記述し、あとはフラグメントを配置してさあどうよと、年譜本文とフラグメントの照応からいろいろなことを読み取ってくださいなと、それは読者の作業ですと、そういって収まり返っているだけでいいのかどうか。年譜本文とフラグメントの照応性に読者の注意を喚起する、みたいなことをもっと心がけたほうがいいようにも思われる。 たとえば西田政治、横溝正史の両人とはじめて会ったのは大正14年4月11日であったとするのは明白に乱歩の事実誤認なんですから、年譜本文でもそれは指摘してある。しかし確たる根拠はないけれどこれはこう考えたほうが自然なんじゃないのとかおそらく乱歩の勘違いなんじゃないのとか、そういったことは読者の判断に委ねることにしてあって年譜本文ではいっさい言及していない。それでいいのか。あるいはもうちょっと注意喚起が必要なのか。この伝言板に記したごとく小酒井不木と乱歩の初対面はいつであり乱歩の東京滞在は何日間であり、あるいは乱歩は宇野浩二に「新青年」のこの号を手渡しこの号を郵送していたのである、みたいなことをたったかたったかと書き連ねてゆくと驚くべし、年譜本文が『子不語の夢』の脚註のようなものに化してしまう虞が多分にある。それではまずかろう。あの脚註は脚註だからあれでいいのであるけれど、『江戸川乱歩年譜集成』の本文があんなになってはよろしくない。 私は伊賀の忍びとして峻険な崖の上でひとり風雪に耐えている松の木のように寡黙でありたいと念じているのですが、里の木に羽を休める小雀みたいにもう少し饒舌になったほうがいいのかな。 なーんか悩ましい話ですけどここでお知らせ。ミステリー文学資料館のオフィシャルサイトがリニューアルされましたのでぜひアクセスを。光文社のサイトから独立し、権田萬治さんの「館長ブログ」も掲載。 6月には資料館の新しい企画として土曜講座「ミステリーの書き方」全五回がスタートするそうで、講師は新保博久さん。詳細はサイトで直接どうぞ。 |
けさは「江戸川乱歩年譜集成」にまったく手をつけておらんのですが、むろんこんな日があってもよろしい。 きょうのところは神戸文学館で昨日開幕した企画展「探偵小説発祥の地 神戸」のお知らせを「番犬情報」でごらんいただければそれでよろしい。 神戸文学館のオフィシャルサイトはこちら。 私はまだ足を運んでおりませんので展示内容をつまびらかには承知していないのですが、正史の著書では昭和12年に六人社から出版された『真珠郎』が、なんてったって乱歩への献呈署名入りとあってひときわ異彩を放っているものと思われます。この『真珠郎』、自慢じゃないけど名張市立図書館の蔵書なり。 名張市立図書館もたまには世間のお役に立っておるというわけなのですが、いくらなんでももうそろそろ乱歩と無縁な図書館にならなければならんわけで、関係者全員がそれを願っているものと推測される次第なのですが、あ、そういえば、 ──いいかこら教育次長だかなんだか知らんがろくに経緯や事情もわきまえぬ人間が横からしゃしゃり出てきて人に偉そうな説教かましてんじゃねーぞたこ。 の件、名張市教育委員会の教育次長とやらもまったく困ったものであって、そろそろ名張市役所に凸して凹ってやろうかなと思っても連休であったか。へっ。へへっ。へへへっ。 |
いつか宝塚版黒蜥蜴に関連して記したことですが、私は稲垣足穂の「美しき穉き婦人に始まる」を読むまで「穉」という漢字があることを知りませんでした。同様に『タルホフラグメント』という本を読むまでは、断片や断章を意味する「フラグメント」という言葉を知らなかったのであろうなと振り返られます。 『タルホフラグメント』は大和書房から出ていた「夢の王国」というシリーズの一冊で、いまは手許にありません。このシリーズのなかで私が現在も所蔵しているのは、どうやら中井英夫の『黒鳥の囁き』だけみたい。1974年5月30日発行のそれを引っ張り出してきて巻末のシリーズ一覧を見てみると、『タルホフラグメント』はこんなぐあいに紹介されていました。
ああそうか、やっぱりな、と納得されるところがありました。何が納得されたのか。自分がこんなフラグメントばかになってしまったのは、やっぱ足穂の影響なのかな、といったようなことでした。 いや、ここで訂正を入れておきましょう。私は先日来自分のことを「フラグメントばか」と称してまいりましたが、僭越ながら「フラグメントきちがひ」とあらためることにいたします。ばかというのは単なるばかなのですが、きちがひとなるとなにしろ気がふれているのですからたいしたものです。常人にできないことはばかにもできませんが、きちがひというのは常人にできないことでもへたすりゃ平気でやってしまう。そういったいわゆるものぐるいへのあこがれをこめて、私はきょうから「フラグメントきちがひ」を僭称することにしたい。どうして「きちがい」ではなく「きちがひ」なのかというと、歴史的かなづかいで表記したほうが気のふれ方に品が感じられるという理由によります。向後万端よろしくお願いいたします。 おととい、大阪にある旭屋書店のあれは本店か、曾根崎の店に立ち寄ってみたところ、雑誌「ユリイカ」のバックナンバーを平積みにしたコーナーがありました。「ユリイカ」という雑誌が名張市内の本屋さんに置かれてあるのかどうか、あらためて考えてみるとよくわからないのですが、とにかくそんなのが出ていたことなどまるで知らなかった去年の9月臨時増刊号《総特集 稲垣足穂》、眼についたので手に取ってみました。 目次をながめてちょっとだけ愕然としました。名も知らぬ書き手がたくさん並んでいるからです。むろん松岡正剛さんを筆頭に見なれた名前もあるものの、どちらさまで? と尋ねたくなるような名前がそこここにある。ですから最初は購入する気もありませんでした。しかしそのうち食指が動いて、巻末に年譜と書誌が掲載されているから資料として手許に置いておくかとか、江戸川乱歩リファレンスブックの装幀をお願いしている戸田勝久さんの絵も収録されていることだしとか、あがた森魚さんが荒俣宏さんと対談しているのがなんか楽しみなような気もするしとか、そんなことをみずからにいいきかせながら購入した次第でした。気になるお値段はなんと二千二百円。 巻末の書誌はとりあえず、キネマクラブの編による「稲垣足穂著書目録」が有用。おととし出版されたちくま文庫の稲垣足穂コレクションの内容を確認することができました。というのもこのコレクション、当地の本屋さんではまったく見かけなかったような気がするからで、乱歩に関連のある作品も収録されているのだろうなと気にかかりながら、むろん大阪の本屋さんに立ち寄ったとき手に取ってみればいいのですが、そのときにはそんな文庫本のことなどきれいに忘れ果てているから始末が悪く、ときどき思い出しては、あ、いつか内容を確認しなくちゃなと思いつつおとといまでむなしく日々を過ごした私であった。 稲垣足穂コレクションから著書目録をさかのぼってゆくと、あ、これはいかん、みたいな本にもぶつかります。1975年に潮出版社から出た多留保集別巻『タルホ事典』に乱歩の「萩原朔太郎と稲垣足穂」が収録されておるではないか。まいったな。この本のことは「江戸川乱歩著書目録」に記載してない。不備である遺漏である欠陥である。書棚をぐるーっと見てみたら多留保集はただ『びっくりしたお父さん』があるだけというていたらく。そこで私はついさっき、この本は手許に置いておきたいからとみずからにいいきかせつつ、「日本の古本屋」を検索してもっとも安価な『タルホ事典』を発注したのであるけれど、気になるお値段は三千六百七十五円もするのであった。 おなじくキネマクラブの編による「彼自身による稲垣足穂」は面白い試みで、足穂自身によってくり返し語られた生涯のあれこれの日々を、「全集から部品を拾い集め組み立てられたセイントタルホの縮尺模型〔スケールモデル〕」としてまとめた年譜です。まさしくフラグメントの集成であって、フラグメントきちがひたる私にはとても興味深く、またおおいに参考にもなりましたが、ちょっとした事実誤認がありましたので意地が悪いようなれど指摘しておくことにいたしましょう。 「大正十五年・昭和元年(一九二六年) 二十六歳」の項に、 ──江戸川乱歩と知り合う。 とあるのは誤りで、足穂と乱歩の初対面はおそらく昭和6年の秋であろうと推測されます。 事実関係の流れをごくあっさりと見ておきますと、昭和6年10月15日、萩原朔太郎と乱歩がはじめて会う。朔太郎、乱歩の人柄を好ましく思い、足穂に乱歩を紹介する。ですから足穂が乱歩と知り合ったのは昭和6年10月15日よりもあと、ただし足穂はこの「彼自身による稲垣足穂」によれば昭和7年の1月か2月に明石に帰省、「美しき穉き婦人に始まる」の日々がはじまるといったゆくたてとなります。 それからまた、『探偵小説四十年』には、 ──私の家内が早稲田大学の裏で下宿屋をやっているころで、稲垣君がその下宿屋へ遊びに来たのが最初であった。 とあり、足穂の「旅順海戦館と江戸川乱歩」には、 ──朔太郎は、なんでも現存の秘密なマッサージ倶楽部についてたずねるために、戸塚緑町に下宿屋をひらいていた乱歩を訪れ、先方の人柄が気に入ったと云って、自発的に私に紹介状を書いてくれたのだった。 とあります。この下宿屋の廃業は昭和6年11月のことで、東京日日新聞の11月24日付夕刊に「探偵作家の名物下宿もこれでなくなつた」と報じられていますから、足穂と乱歩の初対面は昭和6年の10月下旬か11月上旬または中旬といったところになるでしょうか。 それがどうして「彼自身による稲垣足穂」において大正15年のことと誤認されたのかというと、おそらくは『探偵小説四十年』の大正15年度に「萩原朔太郎と稲垣足穂」の章が置かれているからでしょう。こういう誤認を防ぐ意味でも一日も早く「江戸川乱歩年譜集成」を完成させねばならんわけですが、大正14年のページにはけさも手をつけなんだ私である。いかんいかん。こんなことではいかんのであるが、世間が大型連休だと思うとどうも気がゆるんできて、きのうも真っ昼間から知人とビールを飲んだりしてどうもいけません。 ともあれ、『江戸川乱歩年譜集成』をフラグメントの集成として構成するという発想は、その淵源をたずねれば足穂の「一千一秒物語」なのではないかしらと、この「ユリイカ」の臨時増刊号をながめていた私はなんとなくそんな気がしてきました。だからどうだということもないのですが、フラグメントきちがひの自己分析はまあそういったことなのである。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||