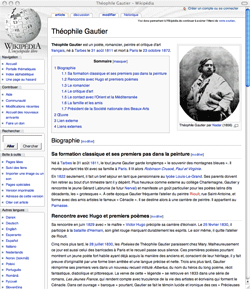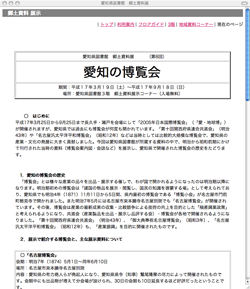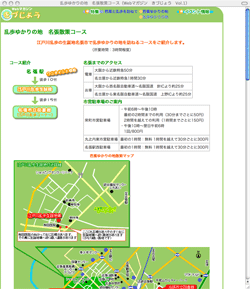|
2006年9月下旬
|
|
そんなこんなでほんとにね、ほんとにはかどらないの『江戸川乱歩年譜集成』の編纂が。泣きたくなるくらい進まないの。泣いてばかりもいられませんけど、時間を見つけて作業にかかってもすぐに寄り道してしまうこの惰弱さはなんとかならぬかと自分でも思う。 ご紹介しておりますとおり現在ただいまは、『探偵小説四十年』に記されている事実を年表化する作業と、登場した人物の生歿を年表に落としてゆく作業、このふたつをメインに編纂を進めているわけなのですが、後者の作業にはもう少し重要な意味があるのではないかという気がしてきたところです。たとえば出羽ヶ嶽文治郎という人物が出てきたら、彼が生まれた年のページに何月何日、出羽ヶ嶽が生まれたと記し、乱歩とのかかわりを記し、何年何月に彼が死去したと記してゆく。それが後者の作業なわけなのですが、これはいわば目次づくりのようなものなのではないか。 出羽ヶ嶽の場合はただ一度だけの遭遇であったけれど、これがたとえば横溝正史になると話は複雑です。青年期から乱歩が死去するまで(乱歩が書いた本陣評の裏話なんてのは乱歩の歿後に明かされてるわけですけど)濃厚な関係性で乱歩と結ばれており、『江戸川乱歩年譜集成』の随所にその名が登場してくるはずなのですが、それは時間の流れに沿った断片的な記述にならざるを得ないでしょう。ならば横溝の出生時、アウトライン程度のものにしても生涯にわたる乱歩とのかかわりをまず示しておくのがいいのではないか、と年譜編纂者は考えたわけです。 横溝出生の時点で何年何月には乱歩とのあいだでこんなことがありましたと書いておけば、読者にはその何年何月のページを開いてよりくわしい記述に接することが可能である。だから目次なわけ。これは『江戸川乱歩年譜集成』のどこに横溝正史が出てくるのかを大雑把に知ることができる目次といっていいのではないか、と年譜編纂者は考えてるわけ。なかなか面白いもくろみじゃないの、とも考えてるわけ。で、面白いけどそれはまたずいぶんと面倒な、と頭を抱えてるわけ。 頭を抱えて寄り道に走り、『江戸川乱歩年譜集成』にかろうじて関係がなくもないといった程度の本(たとえば現代日本文学大系第三十八巻『斎藤茂吉集』がそれですけど)をむさぼり読むことの快感といったらあなた、ほかにたとえるものなんかありゃしませんぜ。
|
読者諸兄姉にもそんなおぼえがおありでしょうけど、当面こなさなければならない作業から逃れるようにして本を読むことには得もいえぬ快感があり、なんかもうやみつきになってしまいます。むろん私の場合には『江戸川乱歩年譜集成』に関係がある、ないしはかろうじて関係がなくもない、といった限定を設けてはいるわけですけれど、それにしたって読むべき本はたくさんあります。 たとえば『探偵小説四十年』の最初のほうに倒叙ミステリの例としてあげられている「クロイドン発12時30分」。読んだことがありませんのでこれは眼を通しておかなければと思っておりましたところ、少し前に悪の結社畸人郷の先達からもうじき新訳が出るとお知らせいただき、なら好都合だと心待ちにしていたのが加賀山卓朗さんの訳によるハヤカワ・ミステリ文庫『クロイドン発12時30分』。先日地元の本屋さんにならんでおりましたのを購入いたしました。 これは『江戸川乱歩年譜集成』の編纂に必要な作業なのであるとみずからにいいきかせ、一気読みはせず時間があいたとき基本的に一章ずつ、ぽつりぽつりと読みはじめてみたのですが、まず驚いたのはてっきり鉄道の話だろうと思っていたら飛行機かよ。アリバイ崩しじゃねえのかよ。しかしなんだかかったるいな。まあ倒叙ミステリなんだから出だしはこんなものか。ところが主人公が殺人を決意してその準備を進めるあたりから俄然面白くなってきて、きのうなんかとうとうフレンチ警部が主人公を訪ねてきましてさあ大変。このあと一気読みに走ってしまいそうな予感がして私は怖い。 そうかと思うとカラマーゾフ。これもいい機会だから再読してみたいなと念じてはいたのですが、あの新潮文庫の細かい活字がなんだかな、と鬱々としておりましたところ渡りに船、光文社から古典新訳文庫なるものが創刊され、新聞広告によれば第一回配本にカラマーゾフの名があるではありませんか。そこで地元の本屋さんで探してみましたところ、光文社文庫がならんでいるところにはまるで見あたりません。田舎の本屋には置いてないのか、とか思いながらお店のお姉さんに尋ねてみましたところ、光文社古典新訳文庫は講談社文芸文庫や岩波文庫なんかがならんだあたりに平積みされておりました。普通の光文社文庫よりちょっと格上、みたいな扱いでしょうか。そこで亀山郁夫さんの訳による『カラマーゾフの兄弟1』、嬉々としてあがなってまいった次第ではあるのですが、訳文も活字のぐあいもかなりよさげなこの文庫本、実際にひもとくのはいつのことになるのでしょうか。 いかんいかん。私は本ばかり読んではいられないのだ。『江戸川乱歩年譜集成』の話題に戻りますと、『探偵小説四十年』に登場した人物の生歿をすべて年譜に落としてゆくという構想は、やはりなかなか見るべきところのあるものだと思えてきました。生歿の生のほうについてはきのう記したようなことなのですが、歿のほうだって結構面白い。歿ったって要するに何年何月何日に誰が何歳で死んだのか、その事実だけを点鬼簿のごとく無感情に録してゆくだけのことなのですが、それが意想外な興趣をおぼえさせるものだということを私は小谷野敦さんの『谷崎潤一郎伝 堂々たる人生』に確認いたしました。 『谷崎潤一郎伝』には谷崎歿後の動向も記されており、最後のほうは谷崎と関係のあった人物の死去の記録が主体となります。たとえばこんなあんばい。
死去の事実が列記されただけであるにもかかわらず、人間の生というもののなまなましい重みがひしひしと伝わってくるように感じてしまうのは私だけ? とにかく私は自分が『江戸川乱歩年譜集成』で試みようと考えていたことの先行事例をここに発見し、わが意を得たといいますか意を強くしたといいますか、そんなような気がしたことを打ち明けておきたく思います。 ちなみに『江戸川乱歩年譜集成』の1966年と1967年は、現段階ではこんな感じになっております。 まず1966年。
よく見てみたら現時点では1967年の物故者はゼロですので、1968年をごらんいただきましょう。
相当よさげじゃ、と私は思う。浅岡信夫って誰だっけ、とも思うけど。
|
きのうのつづきをもう少しつづけますと、小谷野敦さんの『谷崎潤一郎伝 堂々たる人生』の結びはじつに見事なものでした。天が味方したとしか思えぬほどの見事さです。単に関係者の死去の記録が連ねられているだけなのですが、1997年には嶋中鵬二と嶋川信子、1999年には雨宮庸蔵、2004年には水上勉と白川静、といったぐあいに死者の名前が列記され、最後はこんな一行。
見事というしかないではないか、と私は思います。満百歳というのが見事である。谷崎の生涯を追い関係者の死去を録して最後が「満百歳」。長く介護を受ける身となりながらもよくぞ生きておったな丹羽文雄、でかした。なんてこといってるとずいぶん不謹慎な感じがいたしますけれど、谷崎のものであれその関係者のものであれ、あるいは読者それぞれのものであっても、これは愚かしさにあふれ場合によっては介護を受けて長らえるなどという不本意を余儀なくされることも少なくない人間の生というものを、しかしそれでもなお副題にある「堂々たる人生」としておおらかに肯定し、人生なるものの本来的な豊かさに思いいたらせる見事な幕切れであろうと私には思われます。 見事という言葉をもう五回もつかってしまいましたけど、それほど私は感心しました。そして『江戸川乱歩年譜集成』の結びはいったいどのようなものになるのであろうかと、まだまだずーっとずーっとずーっと先のことにぼんやりと遠い思いを馳せ、しかしあの主人公のやつは執事まで殺しちまったのかよ、といよいよ佳境を迎えたハヤカワ・ミステリ文庫『クロイドン発12時30分』の展開もしきりと気にかかる。いろんなことを気にかけながらきょうも一日、愚かしさに充ち満ちた人生をなんとかふらふら生きてゆきたいなと念じている次第なのですが、本日は朝から亡父の墓参をはじめとした雑務がたてこんでおりますのでこのへんで。
|
『探偵小説四十年』を読んで出羽ヶ嶽という力士のファンになった、すっかりとりこになっちゃった、とおっしゃる方に耳寄りなお知らせです。きのうすべての雑務を終えて本屋さんにふらふら立ち寄りましたところ、平凡社新書の新刊で『昭和大相撲騒動記』というのが出ておりました。著者は大山眞人さん、発行は9月11日、本体七百四十円。版元オフィシャルサイトの紹介ページはこちらです。 副題は「天龍・出羽ヶ嶽・双葉山の昭和7年」。われらが出羽ヶ嶽もちゃんと名前を連ねております。昭和7年に相撲界で何があったのかといいますと、角界の改革を求めて天龍を中心とした幕内力士が大日本相撲協会を脱退、新興団体を旗揚げするという大事件でした。協会が存続の危機に直面した大騒ぎだったらしいのですが、『昭和大相撲騒動記』にはその顛末がくわしく記されているようです(買ってきたばかりでまだひもといておりません)。 『探偵小説四十年』には天龍の名前も出てきて、それゆえ昭和7年の春秋園事件(私が調べたかぎりでは天龍事件と称されておりましたが)について私にはわずかながらも知識があったのですが、こちらが必要としている資料はかくのごとくときに向こうから飛びこんできてくれるものなのであって、近い例ではやはり新書であれは新潮新書であったか、永嶺重敏さんの『怪盗ジゴマと活動写真の時代』というのがありましたけれど、新書の新刊もやはりこまめにチェックしておいたほうがいいだろうなと認識された次第です。 しかしよく考えてみますと、乱歩は天龍にばったり顔を合わせてすらおりません。昭和6年5月、読売新聞の附録にサイン浴衣なるものの漫画が掲載されました。お姉さんふたりが各界ナンバーワンのサインで埋めつくされた浴衣を着ている図、みたいなやつです。そこに列挙されたナンバーワンが乱歩であり天龍であり、角界ではもうひとりやはり春秋園事件で天龍と行動をともにした武蔵山でありといったわけで、天龍にしろ武蔵山にしろ乱歩との関係はきわめて稀薄、ていうかほとんど無関係としかいいようがありません。 そんなものまでいちいち調べにゃならんのかと思わないでもないのですが、『探偵小説四十年』に出てきた人名はひととおり調べつくすことにしておりますので、えー願いましては天龍は明治36年11月1日生まれで静岡県出身の本名和久田三郎なり、といったあたりのデータは是が非でも必要なのですが、しかし『昭和大相撲騒動記』に記されているであろう情報までは『江戸川乱歩年譜集成』には必要ないのである。ないのであるが面白そうだから読んでみるのである。これもまた寄り道なり。寄り道ばかりなり。寄り道が面白くって困るなり。 だがしかし、とじつは私は考えておりました。出羽ヶ嶽の調べを済ませてそれ以降に登場する人名のチェックを進めていたときのことです。あんまり愛想がないのもいかがなものであろうか、と。で、方針に変更を加えてみました。いったいどういうことなのか、実例をごらんいただきましょう。 まず、先日も引いた出羽ヶ嶽。明治35年12月の年譜です。
つづきまして天龍。明治36年11月です。
要するに色をつけたわけです。単に生歿となりわいおよび乱歩とのかかわりを示すだけでなく、それはもう出羽ヶ嶽にだって天龍にだってそれぞれの人生というやつがあったわけですから、あまりあだやおろそかな真似もできんのではないか。こういうことを考えてしまうところに私の人間性というやつがにじみ出ているのでしょうけれど、とにかくそのように考えて、私は方針に変更を加えてみたのであった。 ですからサイン浴衣の登場人物でいいますと、たとえば「早大小川投手」はもちろん小川正太郎というフルネームを示し、昭和二年春の選抜で和歌山中学を優勝に導いた速球派サウスポー、みたいな乱歩とはまったく関係のないエピソードもとりあえず書きつけておいた次第なのですが、この調子では大山眞人さんの『昭和大相撲騒動記』に眼を通したあと上掲の天龍にかんする記述がさらに長くなってしまうのではないかとひそかに懸念されてなりません。 『江戸川乱歩年譜集成』の編纂作業がますます泥沼化しているな、ということがひしひしと実感される昨今なわけなのですが、いったいどうなってしまうのでしょうか。
|
乱歩とはほとんど接点がなかった人物の記述にもそれなりの色をつけるとなると、結局とめどというものがなくなってしまいます。例をあげるとゴーチエあたりか。テオフィル・ゴーチエの名は『探偵小説四十年』では昭和5年にただ一度出てくるだけで、平凡社から世界猟奇全集の第三巻として乱歩訳の『女怪』が出たけれど、あれは代訳で誰が訳したのかもわしゃ知らん、といったことが「代作二冊」の章に記されております。 このゴーチエ作品は「モーパン嬢」、原題は「Mademoiselle de Maupin」、いかにも猟奇っぽく「女怪」とアレンジした題をつけられたわけですけれど、手許の文学辞典のたぐいをひもとけば「モーパン嬢」にかんして七月革命がどうのブルジョア批判がこうのとややこしい説明を見ることができます。しかし乱歩はそんなことにはまったく頓着いたしません。 ──誰が訳したのかも全く知らず、訳文さえも読んでいないという、まことに申訳ない仕儀であったが、「モウパン嬢」そのものは英訳で読んでいた。 と正直に打ち明けて、 ──日本の古い物語には、女と思って恋していたのが実は女装の男であったとか、男と思っていたのが男装の女であったとかいう「とりかえばや物語」風の着想がたくさんあり、下っては元禄歌舞伎などにもこの趣向が夥しく入っているが、「モウパン嬢」がやはりそれで、私はこういう話にひどく興味を持つ性格なので、その点だけからでも、この小説は面白かった。 と述べています。 余談ながら、私には乱歩のこうした率直さがじつに好ましい。乱歩がいつまでも新しいのはこうした姿勢にも理由があるのではないかとさえ思います。革命がどうのブルジョアがこうのなんてことにはまったく頓着せず(フランスの話ですから頓着するだけの知識がなかったということもあるのかもしれませんが)、作品にじかに向き合ってその勘どころを的確につかみとり、自分はこういう面白がり方をする人間であると表明して「モーパン嬢」をマイフェイバリットの系譜に位置づけている。こういった作品との接し方というのは当節ではむしろあたりまえのことなのかもしれず、だからこそ乱歩はわれらが先達なのだということになりもするのでしょうけれど、とにかく私には乱歩の揺るぎなさを支えているのはこうした少年のようなまっすぐさであると思われてなりません。 さてゴーチエの話題ですが、手許の文学辞典のたぐいだけでなくインターネットを利用すれば、ゴーチエにかんしてかなりの情報が得られるはずです。はずです、というのはほかでもない、掲示板「人外境だより」でこのところとくに力説しているとおり私は欧文にてんで弱くて話になりません。ゴーチエのことを記したフランス語のサイトなんてまったく意味が不明である。 たとえばネット版百科事典 Wikipedia のフランス語版に見えるゴーチエは次のとおり。 自慢ではないが何もわからぬ。それでもまあ、あれこれ参照し色をつけてゴーチエのことをどう書いてみたのかといいますと、文化8年、西暦でいえば1811年の8月にこんな感じで。
生年月日は Wikipedia フランス語版には1811年8月31日とありますものの30日としている海外サイトもあり(いくら欧文に弱い私だとて生年月日のあたりくらいはつけられます)、とりあえず田辺貞之助の説くところに依拠して30日といたしました。これはむろんただの下書きで、結構遊んでるところやたぶん不正確なところもあるわけなのですが、それにしても長すぎます。『探偵小説四十年』にただ一度登場するだけの海外作家にこれだけの筆を費やしていてはいかんだろう。しかし、しかしなあ、せっかくこうやって書いたのだし、ゴーチエにはなんとか色をつけてやりたい気もするしなあ。
|
とめどがなくなるということでいいますと、社会背景というか時代相というか、そういった情報も『江戸川乱歩年譜集成』に盛りこみはじめると際限がなくなってくる感じです。乱歩自身は時事的な問題はほとんど書きとめておらず、たとえば二・二六事件のことも『貼雑年譜』から、 ──この年二月、二・二六事件起り、自由主義、個人主義没落の前兆既に歴然たり。唯美主義の如きは消えてなくなるべき時代がはじまった。 といったあたりを引用しているばかりで、自伝執筆に際して事件のことをあらためて筆にすることはしておりません。 とはいうもののたとえば大正15年には、 ──【十二月】(二十五日、大正天皇崩御、「昭和」と改元) 昭和6年には、 ──【九月】(満洲事変勃発) といった程度のことは記録されておりますから、『江戸川乱歩年譜集成』においても改元や満州事変にふれないわけにはまいりません。ならばどこまで? と私は悩むわけです。たとえば満州事変。単に満州事変勃発としておくだけでいいのであろうか。むろん『江戸川乱歩年譜集成』は、 ──満州事変って何? 東京事変みたいなもん? とおっしゃるようなみなさんを読者として想定しておるわけではないのであるが、それにしたってもう少し丁寧な説明が望ましいのではないか。かといって昭和6年9月18日に柳条湖事件、7年3月に満州国建国、8年5月に塘沽停戦協定、なれど12年7月に蘆溝橋事件、みたいな歴史的事実をそのまま年譜に落としてみたところでただ煩雑になるばかり、だいいちそんなことでは満州事変の概要を説いたことにはならぬであろう。事変にいたる背景への目配りも要請されることであろうし。となると、昭和6年9月のあたりに満州事変のことをある程度まとめて記しておくのがいいのかな。いやもうやっぱり、 ──満州事変勃発。 としておくだけでいいのか。かなり悩ましい問題である。ああ悩ましい。
|
満州事変のあとは日露戦争の話題です。日露戦争といえば司令長官東郷平八郎ひきいる連合艦隊の旅順港夜襲、そして第二回旅順港閉塞作戦において沈みゆく閉塞船福井丸で行方不明の部下を探しつづけた軍神広瀬武夫中佐を懐かしく思い出す、とおっしゃる方もおいででしょうが(私はコカコーラのテレビコマーシャルで「杉野はいずこ」と絶叫していた加山雄三さんを思い出すのですが)、乱歩ファンなら旅順と聞いて連想するのはいうまでもなく旅順海戦館。 旅順海戦館は『探偵小説四十年』に稲垣足穂がらみで「明治の末期、名古屋市に開かれた博覧会の余興の一つ」と出てきて、大正15年の随筆「旅順海戦館」には「明治四十何年だったか、名古屋に博覧会が開かれた時、その余興の一つとして興行された」とも記されているのですが、ごらんのとおりずいぶんと曖昧。『江戸川乱歩年譜集成』編纂のためにはいずれこの博覧会の会期も特定しなければな、と思っておりましたところ早くも特定できてしまいました。すごい楽でした。 なぜ楽であったのかというと調査作業を人に丸投げしてしまったからで、愛知県在住の方にメールをお送りするついでがありましたので、あの博覧会のことは簡単に調べがつきそうか否か、みたいなことをお訊きしてみたところ、旬日を経ずして返信があり、そこには微細にわたる調査結果の報告が記されておりました。だからすんごい楽でした。なんか面倒だから『江戸川乱歩年譜集成』の編纂をすべて丸投げしてしまってもいいのだが、とつくづく納得されもした次第ですので、丸投げを受けてやろうとおっしゃる方はお気軽にお申し出ください。 では、頂戴したメールにもとづいて丸写し孫引きによる旅順海戦館あれこれ。 最初に愛知県図書館オフィシャルサイトのこのページをどうぞ。 愛知県で開催された博物館の歴史をたどるページなのですが、この「愛知の博覧会」によれば明治40年代に催された博覧会はただひとつ。引いておきましょう。
会場の鶴舞公園というのは乱歩ファンにとって印象深い名前で、名古屋駅前でタクシーを拾って「鶴舞公園の慰問橋を渡って二つ目の角を左へ」と命じると小酒井不木の家に到着した、と乱歩が回想しているあの公園なのですが、名古屋市オフィシャルサイトにある「歩いてみませんか昭和区」の「vol.4 鶴舞公園」にはこんなふうに記されています。
このページには「第10回関西府県連合共進会」について「九州・北海道・東北を除く3府28県が参加し、各種パビリオンが立ち並んでいました。当時の名古屋の人口が約41万人に対して、観客数は約260万人だったことからも、その規模の大きさがうかがえます」とも記されているのですが、成功裡に終わったらしいこのイベントにほんとに旅順海戦館なるパビリオンがあったのかどうか。 調査の手は国立国会図書館に伸びました(むろん私の手ではなかったのですが)。 近代デジタルライブラリーで公開されている資料を検索してみると、明治43年10月10日に大阪市役所が発行した『第拾回関西府県聯合共進会調査報告』なんていうのがひっかかってきます。「第一、第十回関西府県聯合共進会」の「(一)規則」に定められた「第一章 総則」から「第一条」を引いてみましょう(デジタルデータはこちらです)。
ほかにもいろいろと知ることができるのですが、とりあえず旅順海戦館はどうよ? と見てみると、まず「(三)敷地及建坪数」にデータがあって「其他重大ナル建物」の「十四、旅順海戦館」は建坪数が五百五十坪であったといいます(デジタルデータはこちらです)。さらに「(十)余興場ノ種類及観覧者数」によれば旅順海戦館は不思議館、観戦鉄道、曲馬、天女館などのパビリオンを大きく引き離して三十六万千四百九十人という最多の入場者を集めているのですが(デジタルデータはこちらです)、「殊ニ余興場中旅順海戦館ノ如キハ建築費設備費等ニ多額ノ資金ヲ要シタルカ為メニ前項ニ示スカ如ク入場者数モ余興場中第一位ヲ占ムルニモ拘ラズ損失ヲ招キシ結果ニ帰セリト」とも報告されています。 つづきまして明治44年3月15日に第十回関西府県聯合共進会事務所が発行した『第十回関西府県聯合共進会事務報告書』。第十一章「構内ノ設備」に第十一節「興行物」があり、そこには旅順海戦館のことがこんなぐあいに記されております(デジタルデータはこちらです)。
乱歩は『探偵小説四十年』に「ジオラマといったか、キネオラマといったか、謂わばパノラマの親類筋のような仕掛け」とじつに適当なことを書いているのですが(それにしても「親類筋」ってのはどうよ)、旅順海戦館は「米国式化学応用電気作用」による「活動的パノラマ」と見るべきもののようです。 あすにつづきます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅順海戦館にかんしてはまだまだほかにも、たとえば入場料はいったいいくらであったのかみたいなデータも克明に知ることができますので、興味を惹かれた方は国立国会図書館の近代デジタルライブラリーをご利用ください。 本日はやはり近代デジタルライブラリーから、第十回関西府県聯合共進会愛知県協賛会が明治43年12月28日に発行した『第十回関西府県聯合共進会記念写真帖』を見てみます。なにしろ写真帖なんですから、音に聞く旅順海戦館のファサードもこれこのとおり眼にすることが可能です。 この画像をクリックすると新規ウインドウが開かれ、『第十回関西府県聯合共進会記念写真帖』の当該ページが現れ出でますので、表示の拡大率と画面の大小を調節して「館戦海順旅」ならびに「景夜館戦海順旅」の画像をご堪能ください。 以上、愛知県にお住まいの方からメールでお寄せいただいた調査報告にもとづいて、丸写し孫引きによる旅順海戦館あれこれをお届けいたしました。お手数をおかけしたほりごたつさんにあらためてお礼を申しあげます。 つづいてひとつだけ関連情報。『子不語の夢 江戸川乱歩小酒井不木往復書簡集』の脚註に「名古屋博覧会」なるものが登場いたします。大正14年の書簡では、34ページの脚註(三五)に、 ──この鶴舞公園は、翌十五年九月十五日から十一月三十日まで、名古屋博覧会が開催され、モダン都市名古屋を全国的にアピールする拠点となる。 109ページの脚註(一六三)に、 ──翌十五年に名古屋博覧会が開かれ、近代的になっていくという意気込みが感じられる。 昭和3年には264ページの脚註(四八八)に、 ──鶴舞公園で開催された名古屋博覧会は二年前の大正十五年であり、全国に向かって、モダンな都市・名古屋をアピールする気運があったのだと考えられる。 といったぐあいなのですが、昨日お知らせしました愛知県図書館のこのページ── この「愛知の博覧会」には大正15年に名古屋で博覧会が開催されたという記録は見えず、その前後となると昭和3年に鶴舞公園で名古屋勧業協会の御大典奉祝名古屋博覧会が、脚註に見える名古屋博覧会とおなじく9月15日から11月30日という会期で開かれています。もしかしたら脚註には、昭和3年の博覧会を大正15年に催されたものだとする誤認があるのかもしれません。むろん「愛知の博覧会」から大正15年の博覧会が洩れているという可能性も、ぶっちゃけかなり低いけれども否定はできませんので、とりあえず脚註がどんな資料に依拠していたのか、脚註王村上裕徳さんに機会を見つけてお訊きしてみたいとは思うのですが、しかしさすらいの脚註王に連絡するなどということが可能なのかな。ともあれ、結論は保留したまま上記の事実をお知らせしておく次第です。 さてこれで、私は『江戸川乱歩年譜集成』の明治43年のページに第十回関西府県聯合共進会と旅順海戦館のデータを盛ることを得ました。この年、乱歩は満十六歳。旅順海戦館を見たころはまだ十五歳だったのですが、これがどんな年であったのかを年譜から拾ってみましょう。 この年、のちに読売新聞のサイン浴衣の漫画で乱歩とともに名をあげられることになる早稲田のエース、小川正太郎が生まれました。海彼に眼を転ずるならばアメリカではマーク・トウェインが死去し、イギリスではアドリアン・コナン・ドイルが誕生し、フランスではルブランが『813』を刊行。本邦に戻れば森鴎外が「文芸倶楽部」に「うずしお」というタイトルでポーのメエルシュトレエムを独語訳から重訳し、谷崎潤一郎は「新思潮」に「刺青」と「麒麟」を発表して文壇に華々しく躍り出ました。 そしてその年、乱歩は関西府県聯合共進会に足を運んで旅順海戦館にいたく感動し、その翌日には友人とふたりで自分の家の四畳半の離れ座敷にそのミニチュアをつくったわけです。できあがったらその旅順海戦館を近所の子供に見物させてもやりました。子供たちからはやんやの喝采がまきおこったそうですが、栴檀は双葉よりかんばし、これはまことに乱歩らしいエピソードであると私は思います。 乱歩は旅順海戦館を面白いと思った。自分の手でそれをつくってみたくなった。大海原や水平線や東郷平八郎がひきいた艦隊、ひるがえる旗、たちのぼる黒煙、とどろく砲声、火に包まれて沈んでゆく敵艦、夜の月、光る灯台、その光をきらきらと反射する波。そんなものをつくりたくなって、たとえば船火事にはアルコールをしみこませた綿を利用すればいいだろう、などといった仕掛けを、からくりを、アイディアを、いやもういっそトリックといったっていいだろう、夢中になってあれこれ思案して自分なりの旅順海戦館をつくりあげ、できればできたで子供を集めて見せてやった。つまりは観客、小説でいえば読者というものの存在をあらかじめ想定していた。これで子供から見物料をまきあげていたらたいしたものであったのだが、さすがにそこまではしていなかったことでしょう。 結局のところ、旅順海戦館がのちに探偵小説に代わったというだけで、乱歩は生涯にわたってこういうことをつづけた人であったのだろうと私には思われます。探偵小説の面白さに感嘆し、自分でも面白い探偵小説を書こうとし、探偵小説から逸脱しても読者の喝采は浴びつづけ、少年読者をもまた熱狂させつづけた。十五の春に旅順海戦館の面白さを近所の子供たちに教えたのとおなじく、乱歩というのは探偵小説の醍醐味を日本人に伝えつづけた人であったのだ、と。やはり栴檀は双葉よりかんばしく、乱歩は子供のころから乱歩なり。
|
なんだかんだいってるあいだに9月もあしたでおしまいです。読者諸兄姉お住まいの地域におかれましては季節の変わり目に妙なのが湧いて出たりはしておりませんでしょうか。当地は結構大丈夫みたいです。 といったところで本日は地域限定のお知らせ。名張市立図書館の窓口業務が10月1日から民間委託されます、というニュースを中日新聞オフィシャルサイトから。伊東浩一記者の記事です。
これにより、これまでは午前10時から午後6時までだった開館時間は午前9時30分から午後7時までに拡大され、従来は休館だった祝日にも開館されることになりました。図書館運営費は年間約九百万円削減できるとのことです。 名張市外にお住まいなれどいい機会だから(何がいいんだかよくわかりませんが)名張市立図書館に行ってみようか、とおっしゃるみなさんにはついでに名張のまちの散策もお楽しみいただきたく、国土交通省木津川上流河川事務所(というのが名張市木屋町にあるのですが)のウェブマガジン「きづじょう」第一号(2004年5月に掲載されたもののようです)の「乱歩ゆかりの地 名張散策コース」をご紹介申しあげておきましょう。乱歩生誕地や名張市立図書館などをめぐる三時間ほどのコースです。 つづきまして乱歩がらみの地域限定情報を──
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日もまずお知らせ一件。東京の弥生美術館できょう30日、「竹中英太郎と妖しの挿し絵展」が開幕いたします。英太郎の生誕百年を記念した企画展で、おそらく相当な充実ぶりではないかと想像されます。ぜひ足を運びたいなと私は思う。くわしくは「番犬情報」をごらんくだされ。 さて『江戸川乱歩年譜集成』の話題ですが、そんなこんなでまあ進まないの。ひいひいいってるの。ふうふういってるの。目先の作業をひいひいふうふう地味にたらたら進めてはいるのですが、全体の構成となるといまだ五里霧中、レイアウトのプランなどは白紙の状態で、それゆえときにとんでもないアイディアが湧いてくることがあります。アイディアというよりは妄想なのですが。 たとえば、現実と虚構をごっちゃにしたらどうなるか。つまり乱歩の小説に明記された日付を年譜に落としていったらどうなるのか。むろんどうにもこうにも意味のないことではあるのでしょうが、やってみたい誘惑にかられないでもありません。乱歩の小説で日付がちゃんと示されている例は珍しいのですが(ほかの作家の場合も同様でしょうが)、それでも「孤島の鬼」には、 ──その翌日、忘れもせぬ大正十四年七月二十九日、私達は旅支度も軽やかに、南海の一孤島を目ざして、いとも不思議な鹿島立ちをやったのである。 とあります。ちなみに上に引いたのは光文社文庫版のテキストで、桃源社版全集にもとづいた講談社文庫版はこのとおり。 ──その翌日、忘れもせぬ大正十四年八月十九日、私たちは南海の孤島を目ざして、いとも不思議な旅立ちをしたのである。 ふたつのテキストに見られる日付のくいちがいについてはここではふれませんが、とにかく大正14年の7月29日または8月19日という日付が出てきます。ここで手許の年譜原稿を見てみますと、大正14年7月には18日に春陽堂から『心理試験』が刊行され(もちろん奥付上の話です)、牧逸馬から29日付書簡が届き、8月に入れば乱歩は川口松太郎と名古屋を訪れて小酒井不木や本田緒生、国枝史郎と夕食をともにしている。そんなところにいきなり諸戸と蓑浦はいよいよ岩屋島に出立したのであった、みたいな記述が出てきても読者には、はぁ? としか思われないことでしょうし、年譜編纂者自身そんな試みには意味が見いだせない次第ではあるのですけれど、しかしそれでもただひとつ、私が捨てがたく思うのは明治28年4月27日という日付です。 ──それはもう、一生涯の大事件ですから、よく記憶して居りますが、明治二十八年の四月の、兄があんなに(と云って彼は押絵の老人を指さした)なりましたのが、二十七日の夕方のことでござりました。 私にはこの日付が捨てがたい。ていうか、この日付はちょっとした謎である。
|