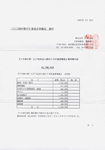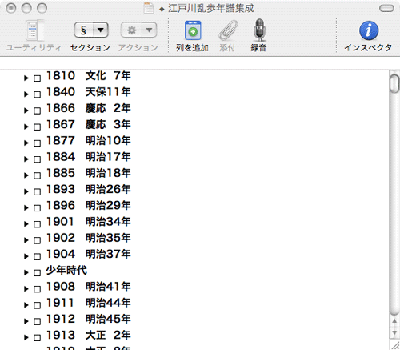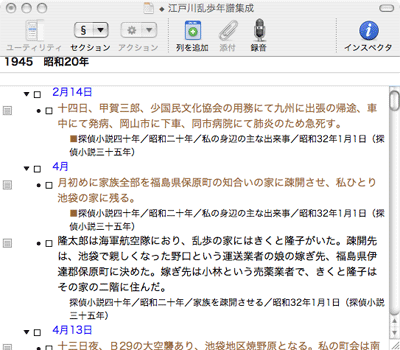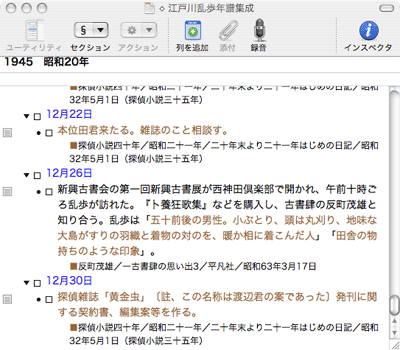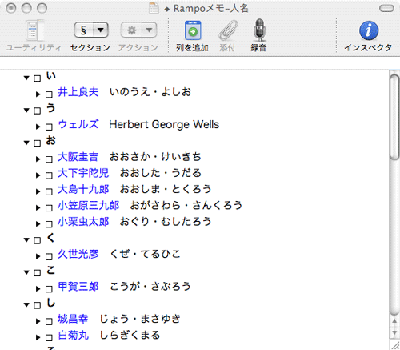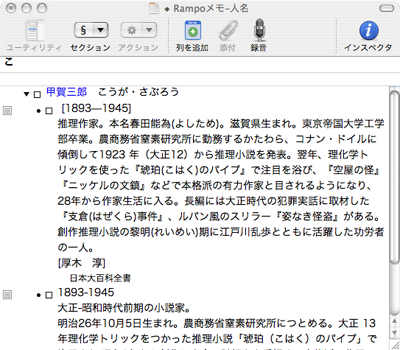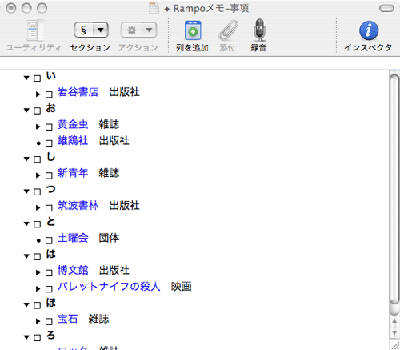|
2006年3月上旬
|
|
弥生3月を迎えまして、まず映画祭のお知らせをおひとつ。 名張市にお住まいの映画監督、田中徳三さんの大規模な回顧上映会「RESPECT 田中徳三」が3月25日に開幕します。会場は大阪市西区九条のシネ・ヌーヴォ。4月14日まで三週間のロングランで、田中監督が大映時代にメガホンをとった四十九作品中三十二本を一挙上映。日程はこのページで、作品解説はこのページでご覧ください。 パンフレットから田中さんのコメントを引いておきます。いやこれはもう引用などではなくてコメント全文をまるっと無断転載してしまうわけなのですが、満腔の祝意を表する確信犯の犯行なのであるとご理解ください。
私はこのシネ・ヌーヴォという映画館のことも、その映画館でこんな企画が練られていたことも、どちらもまったく知りませんでしたが、よくぞ実現してくれたものだとうれしく思います。 3月25日と4月1日には対談、3月26日と4月2日にはトークと、田中さんをフィーチャーした催しもあるみたいですから、大阪圏にお住まいの方は(といった限定を加える必要もないのですが)ぜひお運びください。田中徳三監督といえばなんといっても「悪名」と「続・悪名」の監督として名高く、とくに続篇終幕におけるある雨の日のモートルの貞殺害シーンは日本映画史上に残る名場面のひとつであると愚考する次第なのですが、4月1日夜の特別オールナイト「田中徳三“勝新”ナイト」では上記二本と「新・座頭市物語」「続・兵隊やくざ」がまとめて楽しめます。
|
しかし実際には、村上裕徳さんの「脚註王の執筆日記【完全版】」に記されているとおり、脚註王による尋常ならざる分量の脚註は、 ──それがホトンド全部、ボツにもならんと印刷されてしもたんです。 脚註王も驚かれたことでしょうけれど、私もまたひっくり返りました。編集部なき出版社ゆえの悲喜劇ということなのでしょうが、脚註担当者と編集者との丁々発止というプロセスがすっ飛ばされ、出版社は限られた紙幅に脚註をぎゅうぎゅう押し込むことに汲々として、それでもあがってきた第一校を見てみると、本文は終わっているのに脚註ばかりがえんえん延びつづけ、仕方ありませんから脚註だけを二段に組んでレイアウトしてみました、みたいなページまで出現しているありさまでした。 さすがにこれではまずかろう、ということになったのかどうか、僻遠の地にいた私にはつぶさにはわからねど(というよりも記憶が怪しくなっているのですが)、この時点でようやくスタッフおよび出版社と脚註王との話し合いが行われ、なんとか最終的な形態に落着したのであった、と思います。 脚註王による『子不語の夢』の脚註は、原稿量をべつにして考えてもおよそ破天荒な逸品でした。はじめて眼にしたときにはずいぶん驚かされたものでしたが、読んでみると基本的にはすこぶる面白く(基本的には、などと書くとまたイケズのそしりを頂戴するのでしょうけれど)、そうした面白い脚註を目指してくれた村上裕徳さんの心意気と気合がたいへん嬉しいものに思われましたし、それにまた先日も記しましたとおり、『子不語の夢』の刊行は私にとって三重県民の血税三億円をどぶに捨て去るお祭り騒ぎに身を投じることにほかなりませんでしたから、脚註王における常識的世界からの逸脱ぶりはそれにうってつけのものであるとも判断されました。 『子不語の夢』が刊行されたあとこの脚註のことでごちゃごちゃいってくるやつが出てきたら、おそれおおくも三重県知事になりかわってまずおれが一発かましてやらねばならんな。私はそのように決意していたのでしたが、それはまったくの杞憂に終わり、脚註王の脚註は江湖の読書子に圧倒的な好評をもって迎えられました。第五十八回日本推理作家協会賞評論その他の部門の選考でも、たとえば藤田宜永さんの選評を「オール讀物」2005年7月号から引用いたしますと、 ──『子不語の夢』は注釈が非常に面白かった。注釈でこんなに愉しんだのは生まれて初めてである。この部分だけで一冊の本になっていたら受賞したと思う。 とまで絶讃していただきました次第。ただしこの選評、このあと、 ──他の選考委員から、誰に賞を渡すのか分からない作品という意見が出て、受賞は見送られた。 とつづくのですが、あーこれこれそこの日本推理作家協会、おまえらどうして絶望的なまでに判断力を欠如させたうえにみずからそれを暴露して恬として恥じるところのない手ひどいばかったれ連中を選考委員にするのじゃ、ふざけてんじゃないわよ、ええかげんにしなはれ、ばーか、みたいな啖呵を一度でいいから切ってみたいと思うのですが、いやじつにどうもまあなかなか。日本推理作家協会のますますの発展を祈念いたします。
|
|||||||||||||||||
脚註王村上裕徳さんも第五十八回日本推理作家協会賞評論その他の部門の選考には不審不満がおありのようで、「脚註王の執筆日記【完全版】」のイントロダクションにはこんなことが記されています。
前後の脈絡がようわからんゆう人は「『新青年』趣味」第十二号を購入して全文読んでくれたらええんです。 さるにても、古来あてとふんどしは向こうからはずれると相場が決まっているわけですが、本格ミステリ大賞と日本推理作家協会賞のダブル落選は想定の範囲外。脚註王もお書きのとおり、天城一さんの本格ミステリ大賞受賞は『子不語の夢』スタッフからも余裕でかつまた心から祝福された慶事であったのですが、あてにしていた日本推理作家協会賞の選考結果はにわかには信じがたいものでした。あきれかえって口もきけないものでした。しかし致し方ありますまい。選考委員がきわめてナイーブであったのだと諦めて(ここはもう完全に、選考委員がとんでもないばかばかりであったのだと諦めて、という意味だとご理解ください)、先に進みましょう。 しかし先に進むといっても、「脚註王の執筆日記【完全版】」に関する補足説明、いうならば脚註に脚註を重ねる作業はおおむね終わってしまいました。その先が何になるのかというと、じつはこれからが本題というべきかもしれないのですが、あすにつづきます。
|
『子不語の夢』は三重県が2004年度に実施した官民合同事業「生誕三六〇年芭蕉さんがゆく秘蔵のくに伊賀の蔵びらき」の一環として刊行されました。刊行のためにぶんどった予算は総額三億円のうち五百五十万円でした。 この長ったらしい名前の事業が完全なる失敗に終わったというのはいまや衆目の一致するところであって、伊賀地域住民のなかにはいまでも私の顔を見かけるとこの事業の批判を厳しく展開してくださる方があります。今年に入ってからでもつい先日、といっても先月のことですが、おまえが「伊賀百筆」に発表した事業批判は面白かった、じつは自分もあの事業にちょっとだけかかわったのであるが、それはもうひどいものであった、と打ち明け話を聞かせてくださる方があり、といっても酔っぱらって聞いていたものですから仔細には思い出せぬのですが、事業の一環としてビデオ作品を公募する企画があった、しかしふたを開けてみると悲しいことに作品がほとんど集まらず、したがってそこらの中学生か高校生が撮影した屁でもないようなビデオが堂々の入賞、むろん入賞作品の発表と表彰も行われたのであるが、審査員を務めた旧上野市出身のNHKプロデューサーだかディレクターだかは気に入らないことがあったらしく途中でぷいと帰ってしまって、しかもそのときの入場者数ときたらあなた、 「あの蕉門ホール借り切ってたったの十六人ですよ。たった十六人」 その十六人もすべて入賞者の関係者なのであったそうな。 まったく何をやっておったのか。とにかくひどい事業でしたが、官民双方のばかが寄ってたかってどぶに捨ててしまった三億円のうち、じつに微々たる額ではありましたが五百五十万円の血税を有効に活用できたのは喜ばしい。伊賀地域や三重県にとっても喜ぶべきことであったと思います。 この五百五十万円は全額、一円も残さず出版社に支払いました。内訳は1月2日に「江戸川乱歩小酒井不木往復書簡集刊行事業(続)」でお知らせしましたが、下の画像のとおりです。 おもだったところをあげておきましょう。
ほかは書簡の撮影費、乱歩が製本してあった不木書簡の解体修復費など。五百五十万円で千部を発行し、うち六百六十部は全国の図書館や研究者などに献本しました。書店でも販売しましたが、それによって発生する利益は『子不語の夢』の発行者だった乱歩蔵びらき委員会には無関係、つまり本がいくら売れても委員会には一円も入ってこないということにしました。その主たる理由は、委員会は事業が終われば消滅してしまいますからお金の受け皿がなくなってしまう、二〇〇四伊賀びと委員会の内部にはこの事業で利益を発生させることを疑問視する声もあった(むろん疑問視しない声もあったのですが)、といったところです。 さてそれで、脚註王の話題にこと寄せてお知らせ申しあげてきましたとおり、この出版社には編集部がありませんでしたから編集作業がなかなか進行しませんでした。私は編集業務を出版社に丸投げして高みの見物を決め込んでいたのですが、そんなこともしていられなくなって、たとえば脚註チェック用の非公開ページを開設してスタッフに提供したこともまたお知らせしたとおりです。 結局、いかんいかん、こんなことではいかんではないか、ということになりました。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いかんいかん、こんなことではいかんではないか、ということになりました。 ならばいかにすべきか。要するに編集部が機能しないのですからその点をなんとかせにゃなりません。 善後策を思案した結果、監修をお願いしていた浜田雄介さんに編者にまわっていただくことで衆議が一決しました。それはいいのですがその余波として、スタッフに名を連ねていなかった私が監修者としてしゃしゃり出ることになってしまいました。こいつぁ痛かった。 むろん私とて自己顕示欲や功名心や名誉欲は人並みにもちあわせているつもりなのですが、それが素直には発動しない傾きがあるようです。自分自身を強引に前へ押し出すことに抵抗を感じる。いわゆる上昇志向であるとか、もっと大きくいえば野心であるとか、そういったものが私にはやや稀薄なのではないかしらん。出世栄達はわがことにあらずという感じがどこかにあって、漱石風な〓徊趣味に親近感をおぼえる。そこらのお姉さんと愉しくお酒を飲むことができればそれで機嫌がいい。紅旗征戎わがことにあらず。時節柄の定番曲でいえば「仰げば尊し」の「身を立て名をあげ」という歌詞に対してはいたって冷笑的である。身なんか立てなくていいんだし、名なんかあげなくたって全然OKなんだぜと、お若い衆にどうしていってやれんものかと思う。だいたいが名前なんてのはたぶん何かをなした結果としてあがったり残ったりするものであって、名をあげたり残したりすること自体のために血道をあげるのはずいぶん暑苦しいことではないか。とにかく私はそんなことのために一生懸命にはなれぬのである、というのはいわゆる負け犬の遠吠えにすぎないのかもしれませんが、とにかく私はそんなふうに考える。 (上の段落にある「〓」は「低」のにんべんがぎょうにんべんになっている文字です) しかし、そういったいってみればアジア的な謙譲の精神はべつにしても、私には『子不語の夢』という本に自分の名前を出したくない理由がありました。当初は自分が編集するつもりでいましたから、その場合にはどうしたって名前を出さなければならなかったのですが、編集作業を出版社に丸投げすることができたのですから、しめしめ、こいつぁ好都合だぜ、てなもんでした。脚註王村上裕徳さんの脚註に自分の名前が二箇所出てくるのを発見し、先日も記したとおりちょっとまずいなと思ったのも同様の理由によっているのですが、村上さんがわざわざこうやって名前を出してくれたのだから、陽の当たる表舞台にはけっして姿を現さぬ伊賀の忍びがかすかに足跡を残しておくのもおつりきではないかと考え直した次第でした。 三重県が税金三億円をどぶに捨てた官民合同事業「生誕三六〇年芭蕉さんがゆく秘蔵のくに伊賀の蔵びらき」においては、ぶっちゃけていえば協働だの全国発信だのの旗のもとに浅ましく卑しく胡乱で得もいえず愚かな(あいうえおで頭韻を踏んでみました)乞食根性がうずまいていました。官民双方の乞食のみなさんは一円でも多く自分の懐にかき集めるために眼の色を変え、そのくせ懐にいくら入ったのかをいっさい明らかにしようとせず、しかもそのことに何の疑問もおぼえないってんですから公金を費消する立場の人間に当然要求される倫理や道徳なんてどこ捜してもありゃしません、とにかく三億円をきれいにどぶに捨ててくれたわけですね。乞食のみなさんが。 で私は、そうした乞食のみなさんとは一線を画したかった。それはたしかに三億円に群がってそのうちの五百五十万円で『子不語の夢』を刊行するのではあるけれど、五百五十万円のうちの一円だって自分のものにはしたくない。ぶんどってきた予算のいくばくかを環流だかキックバックだか名目はどうあれ自分の懐に入れてしまうような、そんな浅ましく卑しく胡乱で得もいえず愚かな(もう一度踏んでみました)真似はしたくなかった。 しかし『子不語の夢』という本に私の名前が出てくるとなると、当然のことながら労務に対する報酬が発生することになります。たとえ一円も受け取らなかったにしても、人は私がこの事業によっていくらかの金銭を手にしたと認識してしまうかもしれません。 それじゃなんだか垢抜けねーな、と私は思い、だからこそ『子不語の夢』に自分の名前が出てこないのはじつに望ましいことであったわけです。おれは乞食じゃねーんだッ、と叫ぶかわりに、伊賀の忍びの秘術を尽くして完全に姿をくらましてしまうことが私の念願でした。
|
こと志と異なり、私は『子不語の夢』という本に監修者として名前を連ねることになってしまいました。忍びの術がまだまだ未熟であったということか、とにかくそうせざるを得ない状況になってしまいました。ですから結局、じつに不本意なことながら、監修者としての報酬を手にすることにもなってしまったわけです。 北川正恭さんとおっしゃる前知事が決定し、野呂昭彦さんとおっしゃる現知事がそれを継承した、三重県民の血税三億円(厳密にいえば、三億円のうちの二億円は三重県が、残り一億円は伊賀地域旧七市町村がもちだした税金です)をばらまく愚策のその結果、私の懐にもわずかながらお金が転がりこんできたわけです。 しゃれにならんな、と私は思いました。私はあくまでも清廉潔白、みそぎを終えた巫女のごとくに汚れを知らぬ身で「生誕三六〇年芭蕉さんがゆく秘蔵のくに伊賀の蔵びらき」を批判しているつもりであったのに、巫女さんはいつのまにか春をひさいでおった。いやいや、私は春をひさぐ女性のことを大事にしたいと思っている人間であるのだし、そもそも巫女と売春には古来密接な関連があるのだからそれはいい。それはいいのであるけれど、しかし難儀じゃ、こんなことではおれはもうそこらの乞食と選ぶところがないではないか。くっそー。 こら北川。 こら野呂。 これもみんなおまえらのせいだ。名張市立図書館にその人ありと謳われたカリスマがおまえらのせいでいまや乞食だ。人生裏街道の枯落葉だ。やってらんねーなーまったく。おまえらが無節操に金をばらまいて県民に媚びを売ろうとするからこんなことになるのだ。いくらばらまいたって伊賀地域住民なんてみんなばかなんだから税金をどぶに捨てることにしかならんということすらわからんばかであったかおまえら。 こら北川。 こら野呂。 もっとまじめにやれ。 とここまで書いてみて、これがはたして合理的な説明になっているのかどうか、若干の疑念を抱かないでもないのですが、話の流れとしてはまさにこのとおりなのですから仕方ありません。編集部の不在をフォローするため、監修者だった浜田雄介さんが編者になり、何者でもなかった私は監修者になった。そして私は監修者としての報酬を手にした。そういうことです。 そしてその報酬は、私をおおきに困らせました。自己破産のペナルティとして郵便物がすべて管財人経由となっていた時期のことで、報酬が入った現金書留もまた管財人の弁護士事務所を経て届けられてきたのですが、私は封を切りもせずそこらにほっぽり出しておきました。封を切ったらふらふらつかってしまうことでしょうし、ただの私利私欲で消費してしまったらおれはほんとに乞食ではないか、しかしあまり偽善的な使途ってのもまた気色が悪いものだし。 ちょうどそのころ、『子不語の夢』を刊行した乱歩蔵びらき委員会の後継組織として乱歩蔵びらきの会というのが発足することになり、いっそそこに全額寄付してしまうかとも考えてみたのですが、結成総会に顔を出してみたところ、うーん、なんかちがう、という感じがしたので思いつきは却下、現金書留は未開封のまま私の手許にとどまりつづけ、そんなものがあったということも忘れがちになっていたころ、『子不語の夢』増刷分の報酬というのが届きました。 いやまいったな、と私は思い、困惑はその極に達したのですが、そうした状態を見澄ましでもしたかのように、低い声で悪魔が囁きかけてきました。悪魔の誘惑に負けた私は、二通の現金封筒を勢いよく開封し、中身を取り出し、紙幣もコインもすべて財布にぶちこんでしまいました。まだつい最近のことです。こーりゃいまのうちにパソコン買い換えとかなきゃならんぞと意を決したときのことです。報酬はもとよりパソコンを購入できるほど多くはなく、せいぜいが常用しているアプリケーションソフトの最新版を買い揃えているうちいつのまにかなくなってしまう程度、しかも私は、いやいいんだいいんだ、新しいパソコンとソフトはいずれも『江戸川乱歩年譜集成』をつくるための不可欠のツールなんだからこれでいいんだ、これこそが生きたつかいみちというものではないか、はっはっは、おれは何もやましいことはしておらんぞ、おどおどする必要なんかどこにもないじゃないか、まったくおわらいぐさだぜ、はっはっは、とみずからにいいきかせもしたのですけれど、それでも私が悪魔の囁きに耳を傾けてしまい、そのせいで清廉潔白たらんとしていた心がぽっきり折れる結果になってしまったのはまぎれもない事実です。うーん、まいった。 まいったけれど仕方がない。ここで「生誕三六〇年芭蕉さんがゆく秘蔵のくに伊賀の蔵びらき」に携わった乞食のみなさんにご挨拶を申しあげておきましょう。 ──やあみんな。きょうから僕も君たちの仲間だ。よろしく引き回してくれたまえ。 あずかり知らぬところで三億円をどぶに捨てられてしまった三重県民ならびに伊賀地域旧七市町村住民のみなさんには心からなる謝辞を。 ──右や左の旦那様、毎度おありがとーごぜーやす。
|
ともあれそういった次第で、私はなんとか『子不語の夢 江戸川乱歩小酒井不木往復書簡集』に関する報告を終えることができました。終えることができたように思います。えらく強引なようなれど、そういうことにしてしまいます。 先日も記しましたとおりこの本のことを記すのはなんとも気が重い作業で、それでも村上裕徳さんの「脚註王の執筆日記【完全版】」が発表されたのを得がたい奇貨として、脚註王の話題に無理やりこじつけたどさくさまぎれ、血税三億円のうちの五百五十万円のうちのごくごくわずかな金額がゆくりなくも自分の懐に入ってしまった事実を告白することができた次第なのですが、考えてみれば私は『子不語の夢』のために結構身銭も切ってきたのであって、それは手にした報酬のどう少なめに見積もっても数倍には相当するのではあるまいか、だからべつに卑屈になることもないんだとみずからにいいきかせ、心根のまっすぐな乞食としてこれからも生きてゆきたいと思います。 思い起こせば私には反省すべき点が多々あり、とくにスタッフ各位にはお願いした仕事以外のすったもんだによる精神的負担や心労、ありていにいえばはらわたの煮えくりかえるような思いを押しつける結果になってしまったであろうことは私の不明と不徳のいたすところであったとしかいいようがないのですが、とにかく『子不語の夢』をなんとか上梓できたというその一事に免じて、スタッフ一同のご諒恕を乞いたいと思う次第です。 さらに思い起こせば2002年の春、なんとも懐かしい気分で胸がいっぱいになりますが、成田山書道美術館に足を運んで不木宛乱歩書簡をまのあたりにし、これはなんとか本にしなければならんだろう、しかし商業出版社には無理だろうからやはり官の出番か、採算や効率が足かせになって民には不可能だというのなら官の出番ではないか、よーし、すまんな名張市民諸君、市民生活には何のかかわりもない乱歩と不木の書簡集に君たちの税金をつかわせてもらうぞ、と考えていた矢先に名張市が財政非常事態宣言を発してしまいましたので私は途方に暮れたものでしたが、それだけに三重県がうまいぐあいにばらまきの愚策を展開してくれたのはまことに好都合なことでした。残りの二億九千万円あまりがきれいにどぶに流れたのだとしても、『子不語の夢』を刊行できただけでも「生誕三六〇年芭蕉さんがゆく秘蔵のくに伊賀の蔵びらき」を実施した意義はあったのだと、そのように書いておいてやるから泣くな乞食ども。 ともあれ、スタッフ各位はもとより無理難題を聞き届けていただいた出版社も含めて、関係各位にあらためてお礼を申しあげておきたいと思います。 そして、脚註王。 「『新青年』趣味」第十二号に掲載された「脚註王の執筆日記【完全版】」によれば、われらが脚註王は現在ただいま富士山の見える辺土で悠々自適の明け暮れとの由。インターネットにノータッチどころかいまやパソコンにもノータッチ、原稿はすべて手書きという生活でいらっしゃるとも聞き及びます。 私は村上裕徳さんに脚註王日記のブログを開設してもらいたいものだと考えていたのですが、そしてそうなれば必ずや、悪の結社畸人郷の両巨頭を筆頭に熱心なファンが続々と生まれるであろうにと推測されもする次第なのですが、そうは問屋が卸さぬようです。惜しむべし惜しむべし。惜しみてもなおあまりある富士の星影。 脚註王の隠遁生活が夕映えのような穏やかな感情に包まれたものであることを、そして脚註王がいつの日かふたたびわれわれの前にその勇姿を現してくれることを切に願いながら、乞食天国伊賀の国からお別れを申しあげます。
|
|||||||||||||
脚註王のあとは年譜王の登場となります。しかし脚註王という言葉の響きに比較すると、年譜王の場合は pu という破裂音がなんだか間抜けで困ったものです。 そんなことはともかく、いまや全国の乱歩ファンのあいだには、 ──あのカリスマがついに立ちあがった。 と期待を寄せてくださっている方が五人や六人はいらっしゃるのではないかと贔屓目で考えられぬでもない『江戸川乱歩年譜集成』ですが、当のカリスマは立ちあがってすぐにしゃがみこみ、暗澹たる気分で蟹とたわむれているとでもお思いください。鬼神も落涙するであろう艱難辛苦の大海原を前にして、東海の小島の磯の白砂にひとりだけほっぽりだされたみたいな心境です。 とりあえず着手はしてみました。どぶに捨てられた血税三億円のうちの五百五十万円のまたそのうちの、いやそんなお金の出どころの話はどうでもいいのですけれど、『江戸川乱歩年譜集成』編纂のための不可欠のツールとしてオムニアウトライナーというアウトラインプロセッサを堂々導入し、年譜づくりをスタートさせたとお思いください。 「江戸川乱歩年譜集成」と名づけたファイルをご覧いただきましょう。まずは目次をどうぞ。
これは余談なのですが、専門家のご指導よろしきを得て私はいまやこれこのとおり、画面キャプチャー画像とかスクリーンショットとか呼ばれるやつも意のままにあやつれるようになっております。すごいすごい。 最初に作成したのが文化7年、乱歩の祖父にあたる平井杢右衛門陳就の生年のページです。ついで天保11年は祖母和佐が生まれた年。双方の没年も、さらには乱歩の父母の生没年も押さえました(じつはお母さんの生年が曖昧、没年が不明。いずれご遺族にお訊きしなければなりますまい)。このあたり、年譜編纂にあたってまずは乱歩のご先祖様に花の一輪も手向けようかという殊勝な心がけです。 つづいて、試みに昭和20年のページをつくってみました。なぜ昭和20年か。深い理由はないのですが、先日「本日のアップデート」に記しましたとおり反町茂雄の『一古書肆の思い出』が昭和20年12月26日の乱歩の姿を描きとめておりましたので、とりあえずそのデータをほうりこんでみたいなと考えた、みたいなことであろうと思われます。 ラミネートで表紙を補強した光文社文庫版全集『探偵小説四十年(下)』を机に開き、ぐいぐい押しひろげ、それでも手を離すとぱたんと閉じていますから本を開いたうえに透明なものさしを横に渡し、さらにそのうえにガラス製の文鎮で重しをして、これでよしとばかりにめぼしい事項をアウトラインプロセッサに書き写してゆきました。こんな感じです。
読者諸兄姉ご賢察のとおり、私がまずもくろんでいるのは『探偵小説四十年』という一冊の本を徹底的に解体し、年表の形式に再構成することです。乱歩が記した文章をそのまま引用し(上掲の画像でいうと茶色い文字が乱歩の文章です)、必要とあらば補足を加え、たったかたったか年表をつくってゆく。いつ終わるとも知れぬ作業ではあるのですが、これをやらないと話が前に進みません。 乱歩の記したところのみをとりあえず引き写した昭和20年のおしまいにいたって、ようやく反町茂雄の記録が登場します。
これだけの作業でも結構ふうふういってしまうのですが、なんのなんの、艱難辛苦の種は尽きまじ。
|
鬼神も落涙する艱難辛苦のおはなし。 『探偵小説四十年』の昭和20年の項に配された「私の身辺の主な出来事」は、この年2月14日の甲賀三郎の死去の話題ではじまります。となると、死去だけでなく出生も押さえておく必要があるでしょう。調べます。明治26年生まれと知れます。「江戸川乱歩年譜集成」のファイルに明治26年のページを新設して、甲賀三郎が10月5日に滋賀県で生まれた旨を記します。 甲賀三郎以外にも、昭和20年には次から次へと人名が登場してきます。井上良夫、田中早苗、大下宇陀児、水谷準、大阪圭吉……。すべて生没年をチェックし、それぞれの年のページを新たに設けてゆきます。 そのうち私は、人名を控えておいたほうがいいだろうということに気がつきました。最終的には人名索引をつくらなければなりませんから、そのときにも大助かりすることでしょう。さらに私は、人名だけでなくその人物の事績などのデータもまとめておいたほうがいいかなとも気がつきました。まとめるといっても、ネット上にあるデータをコピー&ペーストする程度のことでいいんだから。 そこで、人名と事績を控えておくためのファイルをつくりました。項目だけを表示するとこんな感じです。
久世光彦さんの名前があるのはたまたま訃報に接したからですが、そのほかはすべて『探偵小説四十年』の昭和20年から21年にかけて出てくる名前です。 甲賀三郎のことを記した「こ」のページを開いてみましょう。
コピー&ペーストしてある文章は「JapanKnowledge」というサイトに掲載されているもので、「日本大百科全書」と「日本人名大辞典」にある「甲賀三郎」の項目解説です。こういった辞典系サイトを利用するのは、いちいち辞書を手にとる必要がありませんからとても楽な感じです。ただし、大阪圭吉あたりになるとどちらの辞書にも項目が立てられていませんから、その場合には手許にある『日本ミステリー事典』の出番となります。 この「JapanKnowledge」は有料会員制サイトで、小学館の『精選版日本国語大辞典』を購入した特典として三か月だけ無料で利用しているところなのですが、その期限が3月いっぱいで切れてしまいます。一度おぼえた利便はなかなか手放すことができませんゆえ、私は4月1日からお金を支払ってこのサイトを利用することになるのだと思います。あー頭が痛い。 しかし、艱難辛苦の頭の痛さはこんな程度ではおさまりません。人名索引のほかに事項索引もつくらなければならないのだからと、私はこんなファイルも設けました。
実際ほんとにたまりません。思いついたことをちょっと試みただけだというのに、作業はどんどん横にばかりひろがってゆきます。肝腎の年表づくりは昭和20年と21年にとどまったままで、これはもうなんだか戦後の混乱期にタイムスリップして帰れなくなったみたいなあんばい、いま東京に行けば五十歳の乱歩に会えるのではないかという気さえ私にはしてくる始末です。
|
|||||||||||||||||