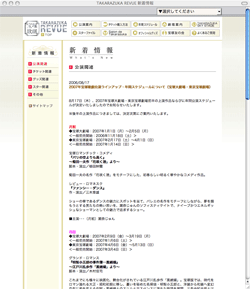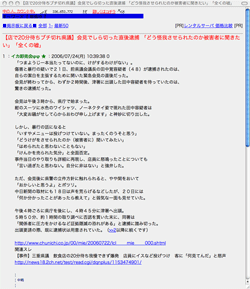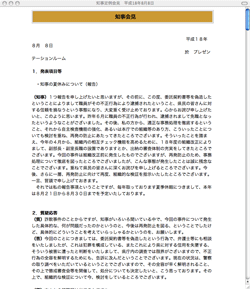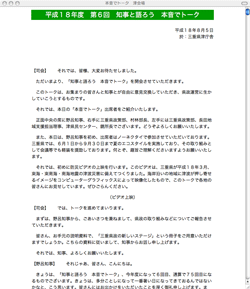|
2006年8月中旬
|
|
まずお知らせ。昨日付「本日のアップデート」に補足を追記しました。こちらをごらんください。 つづきまして、昨日付朝日新聞に掲載された鳥羽みなとまち文学館の幻影城の話題。
それでは日延べがつづいておりました小谷野敦さんの新刊『谷崎潤一郎伝 堂々たる人生』(中央公論新社)の話題に入ります。「まえがき──大谷崎と私」によれば、 ──作品のことはひとまず措いて、ひたすらその人生を再現すべく、谷崎の書簡、来簡を読み、随筆類から実人生を再現していくと、谷崎が私の中で次第に形をなし、息づいていった。 という「谷崎の詳細な年表」づくりから作業がはじまり、 ──かねてから感じていた谷崎の魅力の中心を僅かながら捉ええたと感じ、作品論でも作家論でもない、谷崎潤一郎という一個の人間像を描いてみたいと思い立つに至ったのである。 と執筆されたのがこの大部の評伝。「跋文」にはこうあります。
何をおおげさな、とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし私にはなんとなくわかるような気がします。これと似ていなくもないことを、私は名張市立図書館の『乱歩文献データブック』を編纂する過程で経験しました。私の場合はゲラに眼を通しているときのことでしたが、大正12年から時代を追って乱歩が身に受けた毀誉褒貶、身辺を通り過ぎた喜びと煩い、人生の軌跡を交差させた誰彼、そんなものを関連文献のタイトルを確認することで追体験した私は、昭和40年の死去が近づいてくるとほんとにつらくせつない気持ちになってしまいました。死に際しては文字どおり「感情を揺り動かされ」、不覚にも涙ぐみそうにさえなりました。ですから昭和44年、講談社版全集の配本がはじまって乱歩再評価の気運が高まってきたときには嬉しくてうれしくて。 そんなことはまあどうだってよろしく、のびのびになっていた8月8日付伝言のつづきにまいりますが、『谷崎潤一郎伝』に記されていた、 ──おそらく当時谷崎は、恐怖を覚えつつ乱歩の作品に接したに違いない。 というあたりを読んで、私はまず驚き、うれしく思い、しかしながらやはり、 ──うーむ。 と唸らざるをえませんでした。天国の乱歩が読んだら躍りあがって大喜びするところであろうが、これははたしてありであろうか。少なくとも私の認識としては、谷崎は通俗作家乱歩のことなど頭からばかにしていた、問題にしていなかった、歯牙にもかけなかった、そういったところなのであって、死から四十年以上が経過した現在の眼から見れば谷崎と乱歩を並び称するこうした推断も成立するかもしれないが、しかしなあ、うーむ。 谷崎が乱歩をどう見ていたかはひとまずおいて、大正時代に谷崎と乱歩を関連づけて論じた例があったのかどうか。そのあたりを手近なところで探してみますと──
あすにつづきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
きのうの朝日新聞にこんな記事が載っておりました。
「合併しない」と宣言した福島県矢祭町が「本を買わず、建物も建てないで新しい図書館をつくる」準備を進めているという記事です。市町村合併を拒否した自治体はとりあえず知恵をしぼらなければしかたがない、という見本のような話でしょう。朝日新聞のオフィシャルサイトでは地方版の記事は「マイタウン」というカテゴリでの扱いになるのですが、この記事は「マイタウン」ではなく「暮らし」に仕分けされていますから、ニュースとしての価値が全国規模であると判断されたものと見られます。 こうなりますと惜しまれるのはわが名張市の市立図書館ミステリ分室構想でしょう。合併しないと宣言した三重県名張市が本を買わず、建物も建てないで江戸川乱歩の生誕地にふさわしいミステリ専門の図書館を全国のミステリファンの協力を仰ぎながらつくろうというのですから、ニュースバリューは矢祭町の試みの比ではありません。私はそんなことどうだってかまわないのですが、名張市が小さいながらも知恵のある自治体であることがメディアを通じて全国にPRされるいい機会であったと思われます。しかし実際のところは知恵がないものですから名張市立図書館ミステリ分室構想はあっさり消え去ってしまいました。残念な気がしないでもありません。 いやいや、いつまでも死児のよわいを数えて何とする。谷崎潤一郎の話題にまいりましょう。とはいえ本日は都合によりましてあっさりと。
| ||||||||||||||||||||||||||||
しつこいかもしれん。しつこいかもしれんが先生関連の続報です。 まず昨日付朝日新聞。
先生の暴力沙汰に端を発して8月11日に開かれた臨時県議会の話題です。なんですか「謝罪合戦」とやらが展開されたそうで、まず議長が、 「現職県議の逮捕は誠に遺憾。議会を代表し心からおわびする」 ぺこり、と頭をおさげになりました。できの悪い部下が公金を懐に入れていたことが発覚した知事のほうも負けてはいません。 「誠に遺憾なことであり、県民の皆様に心から深くおわびする」 と頭をおさげになりました。なんと謙虚な話でしょう。この暑いさなか、開会する必要なんかまったくなかった臨時議会をわざわざ開いての謝罪合戦。県民としては高原の涼風に吹かれるようなすがすがしさをおぼえずにいられません。 伊勢新聞は二本立てです。
先生も頭をさげておられます。記事から引用いたしますと、 「ご迷惑をお掛けしました」 「足元を見つめ直したい」 「議会に迷惑を掛けた」 「ご迷惑をお掛けし、おわびを」 「大変申し訳ありませんでした」 「当面、自分の足元、景色を見つめ直したいと思います」 「十六年間走り続けてきて、自分を見失った点もある。将来のことは自分の足元、景色を見つめ直した上で」 ぺこりぺこりの連続です。なんと謙虚なことでしょう。これに対し、自民党県連幹事長は先生の手を両手でしっかと握りながら、 「人生にはいろんなことがあるで。頑張って」 なんとおやさしいことでしょう。 お次は毎日新聞。
そもそもこの日の臨時議会がなぜ開かれたのかといいますと、『江戸川乱歩年譜集成』編纂者の腕を発揮してネット上の新聞記事を年表ふうに再構成した7月30日付伝言を見てみれば一目瞭然。必要箇所を抜粋しますと──
つまり先生に対する辞職勧告決議案を議論する、政治倫理確立特別委員会を設置する、このふたつを目的に開かれたのがこの日の臨時会だったわけですが、先生は8月7日に辞職してしまいましたから辞職勧告決議案なんてどうだってよくなってしまいましたし、政治倫理確立特別委員会を設置する必要などは最初からこれっぽっちもありません。 これは以前にも指摘したことですけれど、ここにひとりの政治家がいて、その政治家が飲食店で待たされたことに腹を立てて店の人間に暴行を加えるようなことがあったとしても、そんなのは政治倫理には何の関係もない話です。単にその政治家が人として決定的なあほであったというだけの話です。そんなことでいちいち政治倫理がどうのこうのとやかましくさえずっているようでは、普通なら人からばかと呼ばれてしまいます。 にもかかわらず、知事は県議会の請求を受けて臨時会を開会してくださいました。そして県議会はまず県民に謝罪し、それから政治倫理確立特別委員会を設置してくださいました。ですから近い将来に制定されるはずの政治倫理条例には、 「いくら腹が立ったときでも人に椅子をぶつけないようにしましょー」 ですとか、 「トイレに行ったあとは手を洗いましょー」 ですとか、幼稚園児レベルのおやくそくが条項としてずらずら書きならべられているにちがいありません。なッ、なんと謙虚な。三重県議会の先生たちはなんと謙虚な人たちなのでしょう。一般的に考えれば、政治倫理条例にはたとえば、 「そこらの業者と癒着して甘い汁を吸ってることは絶対ばれないようにしましょー」 みたいなことが書かれてなければおかしいのですけれど、いやいやこれは、 「そこらの業者とは癒着しないようにしましょー」 とあるべきなのか。まあいずれにせよ百八十万県民から負託を受けた三重県議会のやってくれることです。まちがいはないでしょう。県民のなかには、あれ? あれれ? 7月25日には自民・無所属・公明議員団の団長が、 「県議会として早くこの問題を取り上げ、県民に説明責任を果たさないといけない」 といってくれたそうだけど、8月11日の臨時議会であの問題にかんする説明責任が果たされたのかな、何も説明されてなんかいないように思えるけど、三重県議会は自分たちの都合だけで動いてるようにしか見えないけど、とお思いの方がいらっしゃるかもしれませんが、えーい、黙らっしゃい。県民風情が何を申すか。この臨時議会にかんして私は7月27日付伝言に、 ──だからわざわざ臨時議会を開いて説明しなければならぬことなど何もないのである。「政治倫理確立特別委員会の設置を目的に」などというのはその場のがれのおためごかしにしか聞こえぬ。手前どもは無関係ですと訴えたいのが三重県議会の本音であろう。しかしここまで本音を明らかにしてしまったら、三重県議会における「説明責任」なるものは保身のためのとりつくろいでしかないこともまた明らかになってしまう。だから寝言は寝てからいえというのだ。 と記しているのである。あんな寝言にまともにつきあってどうする。三重県議会がばかばっかだからといっていちいち驚いていられるか。そんなことで三重県民がつとまるか。みんなもっとばかに慣れよーぜ。おれなんてもう免疫ついてっから。 さ、どうしようもないぼんくら議会の話題はここまでとして、谷崎潤一郎の話題にまいりましょう。本日も時間の都合であっさりしており、きのうきょうとただ素材をならべただけみたいであることを遺憾といたします。
あすにつづきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日は四海波静か。お盆というものはこうでなければならぬでしょう。さっそく谷崎の話題に入りますが、これまでのところを整理しておきますと、小谷野敦さんの新刊『谷崎潤一郎伝 堂々たる人生』(中央公論新社)に、 ──谷崎は、乱歩に対して不安を覚えていたと思う。 という指摘がありました。「つまり乱歩は、谷崎が提示したモティーフを、より完成された形にしたのである」、ゆえに「おそらく当時谷崎は、恐怖を覚えつつ乱歩の作品に接したに違いない」といったことなのですが、引用全文は8月8日付伝言でどうぞ。 ところが私は以前からずっと、 ──谷崎は通俗作家乱歩のことなど頭からばかにしていた、問題にしていなかった、歯牙にもかけなかった、 と認識しておりましたので、小谷野さんのこの推断には「うーむ」と唸らざるをえませんでした。いまでこそ谷崎と乱歩がならべて論じられるのも珍しいことではないようですが、こんなのはごく近年の傾向ではないのか。乱歩がデビューしてまもないころには乱歩作品に谷崎のそれと共通する味わいを感じた読者も存在していたことでしょうが(8月11日付伝言の村松梢風の文章がその一例)、いわゆる通俗長篇に転じて以降、谷崎と乱歩を同日に談ずる同時代評はほとんど例がなかったのではないか。 同時代の読者はともかくとして、当事者である作家本人はどうであったのか。昭和5年4月に発表された「春寒」において、谷崎は乱歩のことをずいぶんと見くだしています。自分と同じ土俵で相撲をとっている力士ではないと断じている気配があります。だいたいが谷崎は嫌いな人間にはひどく冷酷で、そうした感情をはばかることなくあからさまにしてしまう人間でもあったようで、たとえば谷崎松子の「倚松庵の夢」には、 ──自分の好きでない人に会った時の素振りは実に全く取りつく島もないと云う言葉が如実に生き生きする位立派なもので、相手の人に外方を向いて煙管で思いきり吸い込んだ煙草を天井に向けてやけにふきつけ、煙草盆をポンポンと気せわしく叩く仕種は如何なる名優も及ばないであろうと、ひそかに仰天し、時に恐くもあった。 といった谷崎の日常が記録されていますが、「春寒」などはまさしく煙草の煙を天井にやけに吹きつけ、煙草盆をぽんぽん気ぜわしく叩きながら書いたような文章であると私には見えます。8月12日付伝言に引いたところを再掲いたしますと──
谷崎は乱歩の「途上」評を批判しています。「途上」は大正9年1月の「改造」に発表された作品ですが、乱歩は大正14年8月の「新青年」増刊に「日本の誇り得る探偵小説」を発表し、 ──僕は「途上」こそ、これが日本の探偵小説だといって、外国人に誇り得るものではないかと思う。 と「途上」を絶讃しました。探偵小説ファンが「専門の探偵作家の書いたものでなければ、例えば文壇の人の作物などは、純文芸であって、探偵小説ではないとして、顧みない」風潮に異を唱え、「潤一郎や春夫の作品を探偵小説といってはいけないものだろうか」として、「途上」こそは「芸術品であって、同時に純探偵小説ではないか」と結論づけているのですが、この相聞に対する谷崎の返歌が「春寒」だったわけです。 いわく、「途上」には探偵小説のようなところもあり論理的遊戯もあるけれど、それは「仮面」にすぎない。そんなところをうんぬんするのは「狙ひ所」をはずした批評である。自分が書きたかったのは「一人の女の哀れさ」なのである。 これを読んだ乱歩はどう思ったか。むかっ腹を立ててキレてしまったようです。「春寒」から二年後の昭和7年5月に発表された「探偵小説十年」からそれがうかがえます。「日本の誇り得る探偵小説」にかんして記されたところを読んでみましょう。「この一文は今から考えると少し見当はずれな箇所がある様に思うが」としながらも──
乱歩は二年たってもむかっとしていて、「逢い度いとは思わぬ」と宣言しています。谷崎の書を床の間にうんぬんといったあたりにも、素直な敬愛よりはからかいの気分を読みとるべきかもしれません。あるいは「子供みたいかしらん」といった結びにも。 まあそういったようなことなので、「春寒」という随筆から判断するかぎり、谷崎は乱歩に不安や恐怖をおぼえてなどいなかったのではないかと思われます。しかし『谷崎潤一郎伝』にはこんな指摘も見られます。
この指摘には虚をつかれました。とても合理的な解釈だと思えます。だがしかし、やはり私はうーむと思う。
|
もうないだろうと思っていたらまだありました。先生関連の続報です。本日付中日新聞をどうぞ。
8月12日夜に民主党三重県連の緊急幹事会が開かれ、先生から提出された離党届を受理すべきか、それとも受理せずに除籍処分としてきっちり落とし前をつけてしまうか、侃々諤々の議論が戦わされたその結果、離党届を受理することで話がまるく収められました。なんともゆるゆるのお裁きです。 私は岡田克也さんのおっしゃるとおり除籍処分が妥当だと思います。学歴を詐称したことを理由に除籍された衆議院議員がいたというのに、非力な女性に暴力をふるい、傷害罪で罰金五十万円の略式命令を受けた県議会議員が除籍されない。これは明らかにおかしい。かりに先生が衆議院議員であったとしたら、事件のことはテレビのワイドショーあたりでも大々的に報じられてぼこぼこにされ、除籍処分に追いこまれるのは必定であろうと判断されるところなのですが、ローカルな話題であるのをいいことに民主党はなあなあ体質をまるだしにして喜んでいる。まるで自民党である。 先生の地元である旧上野市選挙区のみなさん。これがいったいどういうことなのかというと、民主党県連がみなさんをばかにしているということです。こけにしているということです。有権者の存在をないがしろにしているということです。これで先生が適当な時期を見はからって民主党に復党し、みそぎは終わったとかなんとかいっちゃって来春の県議選に立候補する可能性が残されてしまったわけなのですが、もしもそうなったら旧上野市選挙区のみなさん、そのときこそみなさんの良識を示す好機でしょう。これはむろんみなさんに良識などというものがあればの話ですけど、そのへんはじつに微妙だ。なにしろ旧上野市というところはいまだ近世まっただなかの土地柄なんですから、うーん、困った。 私が困ったってどうにもなりませんけど、いやいやそんなことではなくて、よく考えてみたらば私はこの秋10月、旧上野市内のお寺で旧上野市民のみなさんにありがたいおはなしをすることになっているではありませんか。こんなことばっかいってるとそのお寺の境内に筵旗が林立するかもしれん。しかもそのうえ議員辞職して暇になったからと先生が私のおはなしを聴きにきてくださるかもしれん。もしもそんなことになったらどうしよう。そうだ。いい機会だから事件の真相をお聞かせいただくことにしようっと。ねーねーせんせー、ほんとにはめられちゃったんですかあー、とかなんとかいってたら先生はたしか柔道五段でいらっしゃるそうですから…… ばかなこといってないで谷崎潤一郎の話題です。「金色の死」までたどりつきました。谷崎潤一郎が生前の全集に収録することを認めず、歿後ようやく読めるようになったといういわくつきの一篇。小谷野敦さんの『谷崎潤一郎伝』によれば、乱歩の「パノラマ島奇談」が「金色の死」のモチーフをより巧みにかつ面白く発展させた作品であったため、昭和五年から六年にかけて改造社から刊行された谷崎全集には収められなかったということなのですが、このあたりはどうなのか。 要するに「金色の死」は意に満たない作品だから全集に入れませんでした、というただそれだけのことではないのかと私は考えておりました。谷崎というのはじつに中絶作の多い作家で、つまりは自作に対する評価が厳しく、他人に対してのみならず自作にも冷酷な作家であったわけですから、気に入らない作品を全集に収録しないのはあったりまえの話なのではないか。そんな例はたぶんごろごろしているのではないか。 たぶんごろごろしているのではないか、などと推測しただけで終わっていたのでは実証主義の看板が泣きましょう。私は一応は実証主義の立場に立ちたいと念じている人間ですから、やはり実証してみなければなりません。手許には一冊の谷崎全集もなけれども、ありがたいことにきょうびのことですからインターネットが利用できます。国立国会図書館その他の図書館の蔵書を検索し、改造社版全集と1981年から83年にかけて刊行された中央公論社全集とを比較検討してみることにいたしました。 以下、中央公論社版全集(全三十巻)のうち改造社版全集(全十二巻)の収録作品を収録した巻を列挙してみます(ややこしい話で恐縮です)。ただし改造社版全集第十二巻に収められた随筆は対象外といたしました(いよいよややこしくて恐縮です)。この色で示したのが改造社版全集に収められた作品です。中央公論社版全集第十二巻の「乱菊物語」は執筆時期が改造社版全集のカバーエリア外です(何のこといってんだかよくわからないくらいにややこしくて恐縮です)。
ごらんのとおりこの色以外の作品、つまり黒い色で示された作品も少なからずありますから、作者の意に染まなかったせいで改造社版全集に収録されなかった作品は「金色の死」のみにとどまらず結構ごろごろしていたようである、ということが裏づけられたように思います。しかしそれはそれとして、問題はむろん「金色の死」のどこが谷崎の気に入らなかったのかという点です。 それにしても実証主義はもうたいへん。えらく手間ひまがかかってしまいました。手間ひまをかければかならず何かが解明できるというものでもなく、しかし実証できることはすべて実証しつくしたそのうえで実証できないことに想像力をフル回転させるのが実証主義の精髄というものなのであって、いやもうほんとにたいへんです。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ついでですから行っときましょう。きのうの毎日新聞の記事です。
ついでですからもうちょいおちょくっときましょうか。7月29日付伝言から引きます。
7月22日の段階で、民主党三重県連は先生を幹事職から解任し、来春の県議会議員選挙では先生を公認いたしませんと表明したわけです。なおかつ先生が「党の名誉を傷つけた」ため、倫理委員会を設置して先生の処分を決定することにしました。この時点では、先生はいまだ容疑を全面否認しておりました。県連は何を焦っておったやら。 お次は7月30日付伝言から。
7月23日、倫理委員会は「除籍処分が適当」との判断を示しました。が、それを受けた幹事会は結論を先送りしました。理由は「本人が容疑を全面否認していることなど」とされていたのですが、本人が罪を認め、傷害罪で罰金五十万円の略式命令を受けたのですから、先送りの理由はとっくになくなっております。 ひきつづく倫理委員会は8月9日に開かれたようなのですが、いつのまにか見解がころっと変わってしまったみたいです。昨日付中日新聞の「激論の末、離党届受理 田中氏問題で民主県連」には、 ──倫理委員長の森本哲生衆院議員が9日の同委の協議結果について「除籍処分を求める声もあったが、全般的には『除籍は厳しい』との声が多かった。私に一任されたが、受理の方向でいかがでしょうか」と答申した。 とあるのですから、民主党って、あほ? と思わずにはいられません。よくもここまでころころと意見を変えられるものです。7月23日に「除籍処分が適当」との判断を示しておきながら、いまになって何が「除籍処分を求める声もあったが、全般的には『除籍は厳しい』との声が多かった」でしょうか。じつにいい加減です。しかしこの場合、民主党県連のみなさんが全員あほであるという可能性と同時に、県民には見えない藪の中、つまり三重県政の闇の中で何かしら大きな力が働いたという可能性も捨てることはできないでしょう。いずれにせよ民主党三重県連なんてとても信用できるものではない、というのはたしかなことのようです。 そして8月12日、除籍処分は見送られて先生の離党届が受理されました。ということはきのうの中日新聞にもありましたように「田中氏の復党の可能性が残った」、つまり先生が民主党に復党したうえで来春の県議選に出馬する可能性が残されたわけなんですから、そんなおかしな話はありますまい。ほんとに選挙民を愚弄した話ではあり、旧上野市選挙区の有権者のみなさんは、いやみなさんもみなさんなんですからもういいか…… 「金色の死」の話題に戻ります。三島由紀夫は1970年4月に刊行された新潮日本文学『谷崎潤一郎集』の解説で、谷崎から「特に嫌はれ」ていた「金色の死」をとりあげ、ていうか解説のほとんどすべてを費やしてこの作品を論じ、「金色の死」に秘められていた「或る重要な契機」を検証しました。 作者に嫌われた作品にこそ作者の重大な秘密が隠されているというのは、乱歩作品でいえばいわゆる通俗長篇、わけても「盲獣」あたりを想起すればわかりやすいおはなしでしょう。 というところで申しわけありませんが時間切れです。あすにつづきます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「金色の死」の話題です。8月15日付伝言で引いた「解説」で三島由紀夫は、「金色の死」は「明らかな失敗作」であり、「しかし天才の奇蹟は、失敗作にもまぎれもない天才の刻印が押され、むしろそのほうに作家の諸特質や、その後発展させられずに終つた重要な主題が発見されることが多いのである」と述べています。そしてこの作品は「一種の思想小説・哲学小説」であり、「谷崎氏の生涯の美の理想が語り尽されて」いるのだが、それは「これより後谷崎氏によつて故意にか偶然にか完全に放棄された思想」にほかならず、谷崎はここに示された「命題を綜合的に追究することなく、失敗作『金色の死』から身を背けてしまつたのである」と指摘しています。
要するに谷崎は、「金色の死」に理想の美の体現者として描いた「岡村君」になることを断念した。岡村君のように美を追求し実践してゆくならば死を選ぶしかなくなってしまうことを直感し、身を翻して「金色の死」の主題を永遠に放棄してしまった。そのことで谷崎は「自殺を否定し」、認識者として生きることを選択した。「生きるといふことは、自己が美しいものになることを断念することであり、『金色の死』の芸術論の大切な前提を断念することである」。そのような生を選んだ谷崎自身によって、「金色の死」は葬り去られてしまった。 これはもう批評家三島の面目が躍如とした分析であるというしかないでしょう。谷崎作品全体を視野に入れ、作者自身の手で葬られていた「金色の死」を全作品のなかに据え直して、そこに隠された何かしら重要な秘密を探りあてる。批評家の仕事のひとつは作者自身にさえ自覚されていない無意識的企図を探りだすことにあるのでしょうから、三島由紀夫の慧眼はまさに批評家として十全に機能していたというべきでしょう。 ただしこの「解説」、われわれはある先入観にもとづいてしか読むことができないように思われます。われわれの前には「解説」が発表されたのは1970年4月のことであり、おなじ年の11月25日には三島自身が「金色の死」を迎えたという事実が横たわっている。「解説」執筆の時点で自死は明確な目標として存在していたことでしょうから、われわれはこの調子の高い「解説」から遺書に似た印象を感じとらずにはいられないのではないか。三島は「解説」のなかで、 ──話者の「私」は岡村君を際立たせるために故意に凡庸な性格を与へられてをり、「私」と谷崎氏は境遇こそ似てをれ、全くの別人である。むしろ「私」といふアリバイを設定することによつて、作者は自由に岡村君に感情移入をなしえたやうに思はれる。 と記しているのですが、作中の「私」も「岡村君」同様に谷崎の分身であったと見るべきでしょう。「全くの別人」としたのは三島が自身と谷崎との決定的な差異を強調するためのそれこそ「アリバイ」工作であり、そのアリバイがあったればこそ三島自身がこの文章において思う存分「感情移入をなしえたやうに」私には思われます。それはむろん、谷崎が若き日に断念してしまった「金色の死」の延長上に訪れたはずのものに対する感情移入なわけですが。 しかしまあそれはそれとして、三島由紀夫による精緻な検証分析はげんにあるにせよ、しかし谷崎自身にとって「金色の死」は単に意に満たない作品ということでしかなかったのだろうと私は考えておりました。「金色の死」は生硬で稚拙な若書き、幼稚浅薄な美意識や芸術論をそのまま作品化した失敗作でしかなく、全集を編むにあたっては躊躇なく捨て去られるべき一篇、ちょっとこんなのも書いてみたんだけどやっぱ失敗しちゃったな、みたいな程度のものでしかなかったのではないかと、私は長くそう思っていたわけです。 そこへ出てきたのが小谷野敦さんの『谷崎潤一郎伝』でした。そこには何と書かれてあったか。8月14日付伝言に引用したところから引きますと、 ──生前の全集というのは、昭和五─六年の改造社版以降のことだろうが、大正十一年には春陽堂ベストポケット傑作叢書として『金色の死──他三篇』が出ていて、そう始めから嫌っていたわけではないことが分かる。 なーるほど、と私は思いました。こら理屈やな、と感じ入りました。たしかに谷崎は改造社版全集刊行に際して少なからぬ自作を埋葬してしまいましたが、単行本の表題作にしたほどの作品をあっさり捨て去るというのはいささか不可解ではないか。しかも調べてみると、「金色の死」は二度も表題作になっています。最初は大正5年6月刊の日東堂名家近作叢書『金色の死』(収録は「金色の死」「創造」「独探」)、次が大正11年5月刊の春陽堂ヴェストポケット傑作叢書『金色の死 他三篇』(収録は「金色の死」「人魚の嘆き」「刺青」「The affair of two watches」)。てことは結構なお気に入りだったんじゃないの、と私は思うた。 ここで実証主義の立場から附言しておきますと、単行本の表題作になりながら改造社版全集に収録されなかった作品には「金色の死」のほかにもう一篇、大正12年の1月から4月にかけて(つまり関東大震災の直前ということになりますが)「東京朝日新聞」に連載された「肉塊」というのがあるのですが、大正13年1月に春陽堂から出版されたという『肉塊』の収録作品などの詳細は不明です。ともあれ、単行本の表題作品が改造社版全集に収録されなかったのはレアケースであったとはいえ、ほかにも例のないことではなかったということになります。 で、小谷野さんは「金色の死」にかんして、 ──ではなぜ昭和五年の全集には入らなかったか、といえば、昭和二年に乱歩の「パノラマ島奇談」(連載時の表題は「パノラマ島奇譚」)が完結し、昭和四年までに三つの単行本に収められていたからだろう。 と推測していらっしゃいます。たしかに「パノラマ島奇談」は昭和2年から4年にかけて三回にわたって出版されており、「江戸川乱歩著書目録」から引くならば次のとおりです。
ここでひとつの問題が浮上してきます。谷崎潤一郎は「パノラマ島奇談」を読んでいたのかどうか。この一事です。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さてそれで問題の「パノラマ島奇談」。はたして谷崎がこの作品を読んでいたのかどうか、みたいなことは私はこれまでに考えたこともありませんでした。なにしろ私は以前から、 ──谷崎は通俗作家乱歩のことなど頭からばかにしていた、問題にしていなかった、歯牙にもかけなかった、 と思っておりましたので。 しかしよく考えてみると、この場合の谷崎というのは「細雪」を書き「鍵」を書き「瘋癲老人日記」を書き、いわゆる文豪として世俗的栄達の絶巓をきわめたあとの谷崎であったのだということに気がつきました。大正末年から昭和初年にかけて、つまり乱歩がデビューした大正12年から改造社版谷崎全集の配本がはじまった昭和5年まで、谷崎は同時代作家としての乱歩をどう見ていたのか。とくに講談社の雑誌にいわゆる通俗長篇を執筆するまでの乱歩は、谷崎の眼にどのように映っていたのであろうか。 そんなことはむろんわかりません。だから推測してみることにします。まずは「江戸川乱歩著書目録」にもとづいて、当時の乱歩の著作を列挙してみましょう。アンソロジーや全集、翻訳などは省きます。
べつにこんなことまでしなくてもいいのですが、ずらずらならべてみると結構きれいかなと思いまして。 まず『心理試験』。収録作品の大半は「新青年」に掲載されたもので、谷崎がそれを読んでいた可能性もあるわけですが、ここは単行本を問題にすることにして、谷崎は『心理試験』を読んでいたのであろうか。たぶん読んでいたのではないでしょうか。理由としては谷崎が探偵小説を好んだことがあげられます。小谷野敦さんの『谷崎潤一郎伝』には、東京創元社版世界推理小説全集の内容見本に寄せた、 「推理小説と云ふものは、近代小説のうちで最も面白いものであると云へよう」 という谷崎の文章が紹介されていますし、そういえば渡辺千萬子さんによるこんな証言も思い出されます。
日本ではじめて刊行された(といっていいように思うのですが)創作探偵小説集、作者は新進の探偵小説専門作家、筆名はポーのもじり、書名は心理試験。そんな本が出たと知って、谷崎の食指が動かなかったと考えるのは不自然でしょう。8月17日付伝言に引いた萩原朔太郎の「探偵小説に就いて」に記されていたところと同様に、谷崎もまた、 ──江戸川乱歩氏の「心理試験」を買ってよんだ。 といった感じでひもといたのではなかったか。しかしそのあと朔太郎のように、 ──もちろん相当に面白かった。 と感じたのかどうか。このあたりは微妙でしょう。朔太郎の「探偵小説に就いて」には「二銭銅貨」や「心理試験」への不満のあとに「赤い部屋」への讃辞が記され、 ──所謂探偵小説のマンネリズムがない。そしてポオや谷崎氏の塁を摩するものが現われている。それから私は江戸川乱歩が好きになった。 とあるのですが、乱歩が谷崎の塁を摩していたかどうかはともかく、そして朔太郎が『心理試験』をどう読んだのかもともかくとして、『心理試験』を読み終えた谷崎自身は自作と乱歩作品とのあいだに何かしら響きあうものがあると感じ、おそらくは不快な気分を味わったのではないかと想像されます。 想像されるだけですからいい加減な話ではあるのですが、さらに推測を重ねてゆくと、『心理試験』につづく『屋根裏の散歩者』『湖畔亭事件』『湖畔亭事件』、それから「パノラマ島奇談」が収められた『一寸法師』といったぐあいに、谷崎は乱歩作品を複雑な思いを噛みしめながら読み継いでいったのではないか。少なくとも『陰獣』や『悪人志願』あたりまでは読んでいたのではなかったか。私にはそのように想像されます。 『悪人志願』について記しますと、8月12日付伝言に引いた谷崎の「春寒」にこんな文章がありました。 ──僕の旧作「途上」と云ふ短篇が近頃江戸川乱歩君に依つて見出だされ、過分の推奨を忝うしてゐるのは、作者として有り難くもあるが、今更あんなものをと云ふ気もして、少々キマリ悪くもある。 作品名こそ明示されていませんが、乱歩が「途上」のことを書いたのは「日本の誇り得る探偵小説」というエッセイで、これは大正14年8月の「新青年」増刊に掲載されました。「春寒」は昭和5年4月の「新青年」に発表されましたから、そのなかに「近頃」うんぬんとあるのであればそれは「日本の誇り得る探偵小説」を収録して昭和4年6月に刊行された『悪人志願』にもとづく文言であろうと判断してまちがいないでしょう。 ならば、昭和3年11月に出た『陰獣』はどうか。たぶん読んでたんじゃねーの、と私は推測します。これといった根拠はないのですが、やはり谷崎の「春寒」、そのなかには探偵小説を論じたこんな箇所もあります。
私にはこれが、むろんそういった先入観をもって読むからこんなふうに見えてしまうということなのでしょうが、作品名こそ伏せてあるものの谷崎による「陰獣」評であると読めてしまう。読者諸兄姉はそのようにお思いにならぬかもしれぬが、私にはそのように読めてしかたがなく、乱歩もまたそのように読んでしまったのではないかという気さえする。 「陰獣」にかんしては、昭和3年の「新青年」11月号に平林初之輔が「『陰獣』その他」という評文を寄せています。平林は乱歩が「読者の想像力を屈服せしめて作者が凱歌をあげてはやまぬというしつこさ」を指摘し、そうした乱歩作品の傾向について、 ──絶対に読者の追随を許すまいとする作者の頑強な自負心のあらわれではないかと思う。だが、飽くまでもこういう意図をもって探偵小説が構成されるなら、探偵小説はついに成立しないかもしれぬ。 と述べています。底本は『平林初之輔探偵小説選2』(論創社)。そしてこの評言は「春寒」にあった、 ──若しも所謂探偵物の作家が最後までタネを明かさずに置いて読者を迷はせる事にのみ骨を折つたら、結局探偵小説と云ふものは行き詰まるより外はあるまい。 となんとよく似ていることか。むろんこれは探偵小説一般に敷衍できる指摘ではあるのですが、それでも私は「春寒」には「陰獣」批判がこめられていたのではないかと勘ぐってしまう。そして乱歩もそのことに思いあたり、それもまた8月14日付伝言に引いた「探偵小説十年」における「逢い度いとは思わぬ」という乱歩にしては結構激越な一文に結びついたのではないかとまで想像を、いやさ妄想をたくましくしてしまう。 しかし問題は「パノラマ島奇談」でした。谷崎はやっぱ「パノラマ島奇談」を読んでたんじゃねーの、というのが本日の結論です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まずお知らせです。宝塚歌劇団の2007年公演ラインアップが8月17日に発表されました。宝塚大劇場と東京宝塚劇場では花組による「黒蜥蜴」公演があります。オフィシャルサイトをごらんください。 引用しときます。
「三島由紀夫版とは違う宝塚歌劇ならではの結末」というのですから、 ──明智 ええ、本物の宝石は、(ト黒蜥蜴の屍を見下ろして)もう死んでしまつたからです。 なんて感じでは全然なく、明智小五郎となぜか死ななかった女賊黒蜥蜴とが仲よく肩を組んでなぜか三島由紀夫作詞の「用心棒の歌」を朗々と歌いあげる、そんなような幕切れにでもなるのでしょうか。楽しみにしておきましょう。しかし私は宝塚歌劇というものをいまだ一度も見たことがなく、見にゆくのがなんだかこっ恥ずかしいような気がしないでもない。誰かお連れを見つけねば。 さていっぽうの「パノラマ島奇談」ですが、ほんとかよ、とは私も思う。谷崎は『心理試験』にはじまる乱歩の初期の著作を追っかけるようにして読んでいた、いわんやパノラマ島をや、という結論にたどりついてしまった私ではあるのですが、しかしほんとかよ、とも思われてならぬ。半信半疑。阪神懐疑。優勝絶望。なんのことだかわかりませんが、かといって谷崎が乱歩作品をまったく読んでいなかったと証明することも不可能なわけですから、とりあえず昨日たどりついた結論からさらに先へと進みます。 かりに谷崎が「パノラマ島奇談」を読んでいたのだとすれば、単行本の表題作にするほどお気に入りだった「金色の死」を改造社版全集に収録しなかったのも首肯できることであるように私には思われます。 もっとも、春陽堂の『金色の死 他三篇』が出た大正11年5月から改造社版全集の配本がはじまった昭和5年4月までは、谷崎にとってまさしく大きな転機と呼ぶしかない時期だったと想像されます。関東大震災を機に関西に移住し、そこで「痴人の愛」を書き「卍」を書き「蓼喰う虫」を書き、私生活においては「蓼喰う虫」の同時進行的な素材にしていた千代子夫人と和田六郎、というか大坪砂男との不義密通をそれとなくそそのかし、大坪が夫人のもとからつれなく去ってしまったあと、とうとう佐藤春夫に夫人を譲渡すると表明したのが昭和5年8月のこと。それ以後は「吉野葛」を書き「盲目物語」を書き「蘆刈」を書き「春琴抄」を書き、お世辞にも深遠とはいえぬ西洋崇拝を露呈した「金色の死」とは正反対の方向に進んでいったわけなんですから、この転機における谷崎にどのような心変わりが訪れてもたいして不思議ではなく、ましてこの時期に全集を編み自作を取捨選択するということはそのまま作家としてそれ以降の方向性をさだめるということでもあったでしょうから、「金色の死」などはいの一番に抹殺されてしかるべき作品であった。 といったようなこともむろん考えられるのですけれど、「パノラマ島奇談」というファクターを介在させて想像してみるならば、昭和2年に刊行された『一寸法師』で「パノラマ島奇談」を読んだ谷崎は、そこにまぎれもない「金色の死」のカリカチュアを見たのかもしれません(乱歩の場合でいえば、竹中英太郎の「大江春泥画譜」を眼にしたときのような感じでしょうか)。血圧が一瞬にして上昇し、顔面は紅潮の極に達した。頭のなかでは「金色の死」の意に満たぬところが一気に増幅されて迫ってくる。耳鳴りさえおぼえる。あ、あれはだめだ。「金色の死」はだめだ。二度と見たくない。 そんな反応があったと考えられなくもないでしょう。私は小谷野敦さんが『谷崎潤一郎伝』に書いていらっしゃる推測、つまり谷崎は「パノラマ島奇談」が「金色の死」を「より巧みに、面白く発展させたもの」であるという理由で改造社版全集に収録しなかったとする考え方に全面的には賛同できず、「パノラマ島奇談」を読んだ谷崎の反応はもっと感情的なものだったのではないかという気がします。パノラマ島は谷崎が「金色の死」から反射的に顔を背け、身をひるがえして遠ざかったあといっさい近づかないようになった契機ではなかったか。なぜかというと、そこには思い出したくもない自分の過去が歪曲拡大されてべったりと描かれていたから。そんなようなことではなかったのかと推測される次第です。 ですから『谷崎潤一郎伝』第六章の結びにある、 ──谷崎が天才なら、乱歩もまた一方の天才である。大正期谷崎の、最も独自の部分は、乱歩に丸取りされてしまったと言ってもいいのだ。乱歩に会うのを嫌がったのも当然だろう。 という指摘にかんしても、これは批評家の言としてはどこにも差し支えのないものであるにせよ、谷崎自身が同時代作家としての乱歩を「一方の天才」であると認め、自身のある時期の「最も独自の部分」を丸取りした作家であると見なしていたかどうか、そのあたりには現時点ではやや首をかしげざるをえないと正直に打ち明けておきたいと思います。 乱歩に関連する箇所だけをとりあげましたが、小谷野敦さんの『谷崎潤一郎伝 堂々たる人生』(中央公論新社)は、素人の私がいうのもあれなんですが谷崎研究にまちがいなく新しいページを開いた一冊であるといえるでしょう。著者の主眼のひとつは松子夫人にまつわる神話を徹底的に相対化することにあるらしく、たつみ都志さんの主張に共鳴しつつ、 ──『盲目物語』『聞書抄』『春琴抄』『蘆刈』といった谷崎の名作群は、理想の女性たる松子との出会いによって導かれたものであるといった神話が、長く流布してきた。しかしそれは、谷崎死後、松子が自ら作ったと言っても過言ではない。 とするあたり、あるいは、 ──思えらく、谷崎はこの頃、女というのは妻になったらみな似たようなものだと思い知っていただろう。 といったあたりはいかにも痛快。「倚松庵の夢」の気取りがどうにも鼻についちゃって、とおっしゃる方にはとくにお薦めいたします。 むろんこの『谷崎潤一郎伝』、いつの日にか名張市民のみなさんの税金をちょこっと頂戴して乱歩を愛するすべての人のために刊行されるはずの『江戸川乱歩年譜集成』において引用紹介することになるのですが、しかし名張市立図書館の『江戸川乱歩年譜集成』はなんのなんの、それだけでは終わりません。谷崎と乱歩にかんしてはこんな随筆も引用紹介されることになっております。
|
8月も20日。ということは、例の先生の逮捕が先月21日のことでしたからもう一か月が経過したことになるのですが、この件にかんしましては7月25日付伝言に、 ──人の噂も七十五日なんてのはとっくに過去の話、この話題もじきに忘れられてしまうだろうとは思うのですけれど、 と記したとおりのことみたいです。ちょっと調べてみましたところ、2ちゃんねるでは先生の逮捕を受けて立てられたいくつかのスレッドがすでに全滅。最後まで残っていたのがこれなのですが── 8月17日付の投稿を最後に終了しております。 そういえば、知事の定例会見がそろそろ掲載されているころではないかと三重県のオフィシャルサイトを閲覧してみましたところ、8月8日の会見内容が掲載されていました。 8月21日から30日まで知事は夏休みです、みたいな報告のあと、記者団からはやはり先生にかんする質問が。
先生に関係のないところもつらつら読んでゆきましたところ、あっと驚くような質問が。
8月5日に津市内の会場で催された「知事と語ろう 本音でトーク」にパトカーが出動したというではありませんか。この「本音でトーク」は知事が県内を巡回して県民の声を直接聴くという当節ありがちな催しなのですが、「不規則発言者」がいたせいでパトカーが呼ばれたとはなにやら剣呑。いったいどんな発言者がいたのかな、と当該会場の全発言を掲載したページにアクセスしてみたのですが、どうもようわかりません。しかし強いて考えるとDさんでしょうか。
ここでひとこと苦言を呈しておきますと、テープ起こしにやや問題があります。五段落目の「ふだんのレストラン」は「くだんのレストラン」とあるべきでしょう。おなじく五段落目、「既に傷を持つ身」はどう考えたって「すねに傷を持つ身」でなければおかしい。その前段に「レストラン女性店長のすねにいすを投げて負傷させた」とあるのですから、これを受けるのはどうあっても「すねに傷」でなければならぬ。 ──女性店長のすねにいすを投げて負傷させた というところと、 ──田中覚がすねに傷を持つ身となった というところは緊密に照応していてしかるべきであろう。テープ起こし担当スタッフはDさんの練りに練ったくすぐりを十全に理解して作業を進めるべきであったと私は思います。 で、Dさんに対する知事の回答。
Dさんが受ける。
知事が切り返す。
あちゃー、と私は思いました。Dさんの、 ──食事後、田中覚が同伴の外国人女性とどのような行動をとったのかは報道されてはいませんが、県政レベルでの外交交渉であったとの釈明はありませんから、外国人の背後も、女性の背後の勢力からつけ入れられることは十分に考えられます。 という発言が人権侵害に相当するというのであれば、7月24日付伝言に記したこんな発言もやはり人権侵害になるのかな。
むろん私がこんなふうに考えたというわけではありません。これは新聞記事によって先生の一行が「友人の男性1人と外国人女性2人の計4人」であったと知らされた大衆的想像力がどのような方向に流れてゆくかをシミュレートしたものであって、意識の流れをビビッドに表現するため読点をいっさい使用しない手法を採用した実験精神はおおいに賞讃されてしかるべきだと私は思うのですが、しかしこんなふうに考えそれを公表することが人権侵害なのか三重県では。いくら三重県が言論封殺先進県だからといって、そんなことをいって人の想像力というものを抑圧してしまってはいかんではないか。一般庶民が想像力をもちあわせていては為政者として都合が悪いのだという事情はよくわかる気がするけれども。 みたいなことはともかくとして、Dさんと知事との応酬をしばらく眺めてみましょう。
事務局が介入する。
Dさんは負けない。しかしいよいよぐだぐだになってゆく。
いや面白い。じつに面白くてたまりませんけど、こんなあほなことはもうやめたらどうか。「知事と語ろう 本音でトーク」ならば私も一昨年に参加したことがあるが、あまり意味のあるものではないという感想を抱いた。こんな催しに参加しようという県民はかなりエキセントリックな人種であるということもわかった。知事と参加者が双方の自己顕示欲を満足させるためのものでしかないとも知れた。こんなことに税金つかうのはもうおしまいにしてはどうかと私は思う。 そんなことはさておき、いったいどの時点でパトカーが呼ばれたのか。私にはとうとうわかりませんでしたけれど、トークが終了を迎えるにあたってまたDさんの不規則発言が飛び出しておりますから、お暇な方は当該ページでご確認ください。 しかしほんとにこんなものには何の意味もないぞ。もしも意味があるというのであれば、それは三重県政に不備があるということにほかならない。いちいち知事が出張らなくても県民の声が反映されるような県政でなければ困るではないか。みたいなこといっとってもしかたないのだが。
そんなような次第で、三重県知事はあすから8月30日まで夏休みを過ごされるようですが、私もあしたから夏休みをいただき、今度お目にかかるのは8月28日月曜日のことになると思います。どうぞごきげんよう。 |