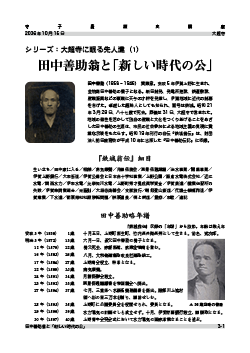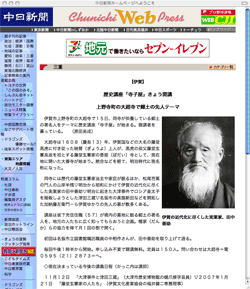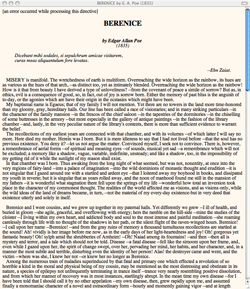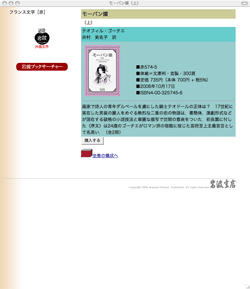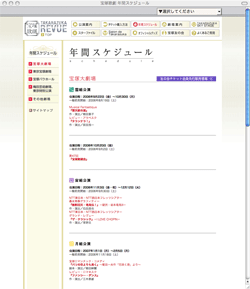|
2006年10月中旬
|
|
|
11日 ▼お知らせのない水曜日 ▼直木三十五伝
12日 ▼ぼーっとしている木曜日 ▼山田風太郎育児日記 13日 ▼まだ立ち直れない金曜日 ▼横溝正史:草稿5000枚見つかる 14日 ▼もうあとがないきょうは土曜日 ▼路上派遊書日記 15日 ▼妙に肌寒い日曜日 ▼私の一冊 『続・幻影城』江戸川乱歩 16日 ▼田中善助リターンズ ▼酒井七馬の謎 17日 ▼江戸川乱歩を遠く離れて ▼下中彌三郎と平凡社の歩み 18日 ▼突然ですが映画祭のお知らせ一件 ▼乱歩の「氷」シベリアで発展 19日 ▼地域社会から乱歩シーンへ ▼立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター 20日 ▼ゴーチエならびに宝塚 ▼怪人二十面相の棲む館 江戸川乱歩 |
|
本日は何のお知らせもありません。頭がぼーっとしているだけです。中日ドラゴンズファンのみなさんにはお祝いを申しあげます。阪神ファンのみなさんは残念でした。
|
本日はきのうに輪をかけてぼーっとしております。
あしたは多少すっきりしたいと思います。 |
けさもすっきりしてはおらんのですが、日本ハムファイターズファンのみなさんにお祝いを申しあげます。このところテレビのプロ野球中継につきあってしまうことが多く、しかも最近は(最近、という問題ではないのかもしれませんが)最後まで試合が生中継されますし、ゲームが終われば終わったでニュース番組が待っておりますから、おかげでもうへろへろ。 しかしさいわいなことにセパ両リーグの優勝が決まりましたので、これでしばらくはプロ野球をテレビ観戦することもなくなり、そうこうしているうちにあすはもう14日。立教大学池袋キャンパスで「読売江戸川乱歩フォーラム2006」が開かれる日なのですが、私は京都に赴いてあす初日を迎える「戸田勝久展 旅の手紙」をのぞいてこようかと考えていたのですが、それもできずに伊賀市の青山ホールというところでさるコンサートのリハーサルに立ち会わねばならなくなりました。本番で司会をやらされることになったからなのですが、本番というのが10月21日。ということは日本シリーズ初戦の日であって、ナゴヤドームで午後6時10分に試合がはじまるころには伊賀市桐ヶ丘にある中華料理屋でコンサートのうちあげか。べろべろのへろへろか。なんかへろへろだらけではないか。しかしそんなことよりあさって15日は伊賀市の大超寺で「寺子屋歴史講座」か。にもかかわらず何をどうおはなしすればいいのかいまだに決まっておらんではないか。それにああいかんいかん。ご来場のみなさんにお配りする資料がまだできておらんではないか。 毎日なーにやってんだか。ああもうほんとにへろへろである。
あしたの自分がまるで生まれ変わったみたいに立ち直ってすっきりしていますようにと私は天に祈りたい。やれやれ。やーれやれ。 | |||||||||||||||||||||||||
へろへろになりながらもあすに控えた寺子屋歴史講座「田中善助翁と『新しい時代の公』」の資料をつくったのですが、不運というか天罰というか、プリンタのトナーが切れてしまってきれいに印刷できません。まいった。しかたありませんから PDF ファイルにしてこの伝言板に掲載し、どこかよそのパソコンでダウンロードすることにいたしました。うまく行くのかしら。 そんなこんなでこのへんで。
|
なんか知らんがあわただしい。などとぼやいておってもどうにもなりませんが、けさはひたすら休養にあてたいと思います。しかし午前中に回復できるのか。
|
おかげさまで無事に済ませてまいりました。昨日付中日新聞の記事がこれなのですが。 この寺子屋歴史講座でのおはなし、おかげさまで無事に済ませてまいりました。寺子屋というくらいですから参加者はせいぜい三十人程度だろうと踏んでおりましたところ、大超寺というお寺の本堂いっぱいに聴衆のみなさんがざっと百二十人。私はいささか焦りましたが、二日酔いの勢いですっ飛ばしてまいりました。 しかし結局のところ、「田中善助翁と『新しい時代の公』」と題してしゃべろうと考えていたことの半分くらいしかおはなしできず(全部しゃべるには三時間ほど必要みたいでした)、せっかくおさらいしていったマックス・ウェーバーにも行基にも出番はまわってきませんでした。 つい最近刊行された三重県史編さんグルーブの『発見!三重の歴史』(新人物往来社)という本に田中善助が明治25年、帝国議会に提出した風景保護請願のことが紹介されておりましたので、まずそれをとっかかりとすることにして景観保全の問題をしゃべりはじめたのですが、いつのまにか明治時代の自然破壊の問題から南方熊楠による神社合祀反対運動に、さらには西洋人と日本人の世界観の差異の問題から横光利一の「旅愁」に登場する古神道のことにまで話題がおよんでしまい、内心いかんなこれは、お寺へお邪魔して神道の話をしておってはいかんではないかとか思いましたので、とにかくキリスト教的な人間中心主義を相対化できるのがアジアの森の思想なのである仏教なのである21世紀こそ日本人の出番なのであると、なんだか変なことを力説しているうちに時間がどんどん経過してしまいました。 当初の予定では10月13日付産経新聞三重版に掲載された「景観づくり条例、県が制定へ 平成19年度中に」という記事をとりあげ、田中善助が百年以上も前に訴えた景観保全の重要性にいまごろになって気がついておるのが三重県なのである、ていうかこの国なのである、しかもこの三重県は「新しい時代の公」などと適当なお題目を掲げて何をやっておるのか、「新しい時代の公」のモデル事業であったらしい「生誕三六〇年芭蕉さんがゆく秘蔵のくに伊賀の蔵びらき」たらいうあれはいったい何であったのか、みたいな方向に話を進めようかなとも考えていたのですが、プリントアウトして持参した産経の記事を紹介することも忘れてしまい、美しい国がどうのこうのいってるそこらの首相のことはなんとか話題にしたのですけれど、省みますればずいぶん暴走してしまったのかな。しかしとにかく仏罰がくだるほどの内容ではなかったことを素直に喜びたいと思います。 この講座では伊賀市上野寺町の大超寺に眠る郷土の先人がじゅんぐりに紹介されることになっているのですが、先人をひとわたりめぐり終えたら田中善助リターンズ、私をふたたび講師としてお招きいただくことがきのうの講座の好評を受けて急遽決定いたしましたので、そのときには「田中善助翁と『資本主義の精神』」と題してありがたいおはなしをしてまいりたいと思います。 大超寺の寺子屋歴史講座、2006年度の予定はかくのごとし。
お近くの方はお誘いあわせてお運びください。仏教徒以外にもひろく門戸が開かれております。末筆ながら、あなたにも御仏のご加護がありますように。
|
もう火曜日か。火曜といえば学校の先生をつとめねばならぬ日であって、こんなふうに寺子屋の先生になったり高校の先生になったりして地域社会のお役に立っていると自分がどんどん乱歩から遠ざかっているような気がしてぼんやりした不安をおぼえないでもないのですが、まあなるようになるであろう。ていうか授業の準備をいたさねば。
|
またしても地域限定の話題で恐縮なのですが、田中徳三さんの監督作品五本をフィーチャーした映画祭が名張市で開催されます。田中さんのトークもあり。お近くの方はお誘いあわせてお出かけください。
いまや私とおなじく名張市民でいらっしゃる田中徳三監督の作品にかんしましては、日本映画データベースのこのページ、今年3月から4月にかけて映画祭「RESPECT 田中徳三」を開催した映画館シネ・ヌーヴォのこのページ、といったあたりをご閲覧ください。 なんだかあわただしくて『江戸川乱歩年譜集成』のお仕事にはノータッチな明け暮れがつづいておりますせいで、あの町この町日が暮れる、乱歩がだんだん遠くなる、みたいな感じでしょうか。こんなことではいかんのだが。
|
本日はとくに地域限定のお知らせもありません。乱歩の話題に戻りたいと思います。 といいながらも先日、10月15日に伊賀市上野寺町の大超寺というお寺で寺子屋歴史講座「田中善助翁と『新しい時代の公』」の先生をつとめた話の後日談を記しておきますと、講座を聴講してくださったという方からメールを頂戴しました。その方のおじいさんもお父さんもともに左官屋さんで、善助さんにはたいへん可愛がってもらい、善助さんが携わったさまざまな建築工事にも職人として加わった、祖父と父からは善助さんの話をいろいろ聞かされている、といったことをお知らせいただいたのですが、伊賀上野のまちにはいまでも田中善助という先人のことが懐かしく語り伝えられていることに私は遅ればせながら気がつきました。 私はあくまでも文献に記された田中善助像しか知らないのですが、まちに語り継がれている生身の善助像といったものにも眼を向ける必要があるだろうなと思い返された次第です。しかしいまの私にはちょっと手がまわりません。いずれの日にか田中善助リターンズ、寺子屋歴史講座で「田中善助翁と『資本主義の精神』」についておはなしをする機会ができたなら、そのときにあらためて眼を向けることにしたいと思います。 といったところで乱歩シーンに眼を転じましょう。
私も一度この江戸川乱歩記念大衆文化研究センターをば訪れて、胸をときめかせつつ乱歩の蔵書をチェックしたいなと念じてはいるのですが、なかなか機会が得られません。 『探偵小説四十年』には、初刊時の余白の埋め草として「忘れられない文章」というエッセイが『わが夢と真実』から再録されています。「うつし世は夢、よるの夢こそまこと」とうフレーズのよって来たるゆえんを説いた短いもので、ポーとデ・ラ・メアの文章にもとづいていることが明かされているのですが、ポーの文章が「ベレニス」であることは調べるまでもなく判明しております。海外のサイトには原文を読むことができるところもあって── 四段落目にある文章がそれなのですが、しかしデ・ラ・メアのほうはとんと不案内。
乱歩はこれだけしか書いてくれておりません。ですから典拠を調べなければなりません。そこで私は『探偵小説四十年(上)』の358ページで「忘れられない文章」にぶつかったとき、試みにごくちょっとだけ調べてみました。立教のサイトで乱歩の蔵書を検索し、デ・ラ・メアの著作をリストアップしました。手許のメモによると── The connoisseur : and other stories(1926) Told again : traditional tales(1927) On the edge : short stories(1930) Best stories of Walter de la Mare(1942) これだけありました。普通に考えればこのなかの一冊に「わが望みはいわゆるリアリズム」うんぬんという文章を発見することができるはずなのですが、それは江戸川乱歩記念大衆文化研究センターで現物を閲覧してみなければかなわない。インターネットを利用してこれらの書物を海外の書店あるいは古書店から購入する、という手もあるにはあるのですが、私にはそんな芸当はとてもできません。ていうかそれ以前に、私の英語力でこれだけの本をチェックするのはまず至難、というより不可能と申してよいであろう。 それにもうひとつ、あれこれ調べているうちに── Behold, This Dreamer(1939) というデ・ラ・メアの著作がなんかあやしい、という気もしてきましたので(なにしろドリーマーってんですから)、この先いったいどうしたものかと悩みつつ、調査そのものはそのまま中断して現在にいたった次第です。ほんにどうしたものじゃやら。 | ||||||||||||||||||||||||||
9月25日付伝言でとりあげたテオフィル・ゴーチエの『モーパン嬢』が岩波文庫で気軽に読めるようになりました。10月の新刊です。版元の紹介ページをどうぞ。 「画家で詩人の青年ダルベールを虜にした騎士テオドールの正体は? 17世紀に実在した男装の麗人をめぐる熱烈な二重の恋の物語」とありますとおり、「リボンの騎士」風というか「ベルサイユのばら」的というか、そのあたりが乱歩をいたく興がらせた百七十年ほど前の作品が現代によみがえります。 「ベルサイユのばら」といえば宝塚歌劇団、宝塚歌劇団といえば「黒蜥蜴」と来るわけですが、8月19日付伝言でお知らせした来年の花組公演「明智小五郎の事件簿 黒蜥蜴」は── 宝塚大劇場 東京宝塚劇場 という日程で上演されます。私はおかげさまできのうになってようやく、宝塚大劇場へ「明智小五郎の事件簿 黒蜥蜴」をいっしょに観にいってくれるお姉さんを確保し、チケットの手配もすべて丸投げすることを得ました。前売り開始は来年1月だからとのんびりしていたのですが、いい席をゲットしようと思ったらいまからあらゆるつてを利用して東奔西走しなければならぬそうです。それぞれの道にはそれぞれの苦労がある、ということでしょうか。 宝塚歌劇団オフィシャルサイトから年間スケジュールのページをどうぞ。 チケットの入手その他あれこれ、どうにもよくわからなくてとおっしゃる方はお気軽にご相談ください。
|