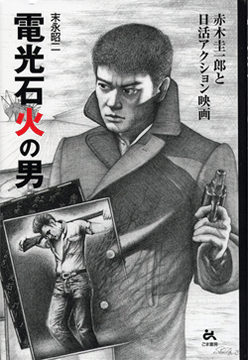|
2006年6月上旬
|
|
6月を迎えました。もう6月かとびっくりしつつ、本日は新刊のご紹介をお届けいたします。 末永昭二さんの『電光石火の男──赤木圭一郎と日活アクション映画』が出ました。版元はごま書房。同社のオフィシャルサイトを調べてもいまだ紹介されてはおらぬようなので、Google 検索でトップにひっかかってきた本やタウンのこのページをどうぞ。
とうに知命をすぎているというのに何なんだこの高卒の DQN の自己破産者は、と年甲斐のなさが2ちゃんねるでつかのま話題になって面目すっかり丸つぶれの私ではありますが、さすがに赤木圭一郎の主演作品をリアルタイムで見たおぼえはありません。しかし本書の第一章「ドキュメント──昭和三六年二月」を読み進むうち、子供のころの断片的な記憶が不意によみがえってくることを経験しました。この第一章では昭和36年2月14日、すでに日活の看板スターとなっていた赤木圭一郎が撮影所でゴーカート事故を起こして重傷を負い、2月21日ついに死を迎えるまでの経過が当時の週刊誌の記事やのちに活字になった関係者の証言などで立体的に構成されているのですが、私が思いだしたのはある漫画のことでした。 ネット検索で調べてみたところ、「少年サンデー」と「少年マガジン」はともに昭和34年の創刊で、ということは赤木圭一郎が死んだときにはもう世に出ていたわけですが、私の記憶にあるのは「少年画報」だか「少年」だか「ぼくら」だか、誌名はよくわからぬもののたしかに月刊誌でした。作者はたぶん堀江卓さんで、その漫画のなかでは赤木圭一郎のゴーカート事故を撮影したフィルムが映写され、登場人物がこの事故には不審な点が多い、赤木圭一郎は事故を装って殺されたにちがいない、といった主旨の謀殺説を展開していた。そんな記憶がいきなりまざまざとよみがえってきたのですけれど、前後の脈絡はまったく不明で漫画のタイトルもきれいに忘れ去っています。 水面にぽっかり浮かびあがるようにしてこんな記憶がよみがえってきたのは、赤木圭一郎の死とその周辺を日活ニューアクションさながらの乾いたタッチと畳みかけるようなテンポで描きだした第一章がもつ強い喚起力のせいでしょう。ごくわずかにでも昭和36年当時の記憶を有している人間であるならば、つまりは当時の大衆文化なるものをかすかながらも肌身におぼえている人間であるならば、この章はあれよあれよと一気に読み終えてしまうにちがいありません。そして巧みな導入にさそわれるまま最後のページまで読了し、何なんだこの本は、と首をかしげたくなるような気分を抱いてしまう読者もあるのかもしれません。 サブタイトルからも知られるとおり、これは「赤木圭一郎と日活アクション映画」をテーマにした本です。それにはまちがいありません。げんにこの本では、赤木圭一郎のおいたちから死までが手際よくまとめられ、前史を含めた日活無国籍アクション映画の歴史も簡潔に紹介されていて、それだけで読者を飽きさせることがありません。しかしながら、本書の白眉と呼ぶべきパートはそのあとに、サブタイトルに示されたテーマがまるでノルマをこなすようにしてひととおり語り終えられたあとから、あたかも満を持していたヒーローのように悠然と姿を現してきます。すなわち、著者の領域横断的個性が存分に発揮された赤木圭一郎出演全作のレビューが読者を楽しませてくれるわけなのですが、白眉はそこにさえとどまらないのである。 どこまで行くのか。驚くべし。なんと拳銃無頼帖シリーズの原作となった木戸禮作品(いわゆる貸本小説なのですが)をひっぱりだし、映画、台本、原作の三者を比較対照しながら赤木圭一郎主演作品の構造と魅力とを分析するという、これはもう日本推理作家協会賞評論その他の部門落選作品『貸本小説』の著者にしかなしえない文字どおりの独擅場、サブタイトルには語られていなかった本書の本質がここにあざやかに際立ち、読者をたっぷり堪能させてくれます。読み終えたあと何なんだこの本は、と思った読者は、やがて自分の首をかしげさせた逸脱にこそ本書の主眼があったという事実に気がつくことでしょう。 日活無国籍アクション映画と貸本小説とがぴたりとシンクロした地点に見えてくるのは、映画スターなるものの存在を可能ならしめていた大衆と呼ばれるものの存在でしょう。大衆という名の想像力がいきいきと息づいていた時代への遅ればせの挽歌とでも称するべきこの一冊、私が最後にトニーの映画を見たのはもう二十数年も前になるのか、大阪のどこかのビルにできたばかりの小さな映画館でのことであったと(かかっていたのは「拳銃無頼帖 抜き打ちの竜」でした)、そんな思い出も懐かしくよみがえり、じつに素直に楽しめる本であったとお知らせしておきます。気になるお値段は税込み千と五百円。興味を抱かれた向きはぜひお買い求めください。ていうか、電光石火で買いにゆくべし。知命をすぎていなくても全然OKです。
|
そんなこんなで『江戸川乱歩年譜集成』編纂のためのもっともベーシックな作業を鋭意継続しているわけなのですが、『探偵小説四十年(下)』をひらいて「戦災記〔昭和二十年度〕」と「探偵小説復活の昂奮〔昭和二十一年度〕」から必要と思われるデータをアウトラインプロセッサに入力し、乱歩における昭和20年と翌21年とはなんとか年表化することができました。 昭和20年からデータをとりはじめたのは、まず敗戦という区切りがあること、それからいつかも記しましたとおり、データのなかに反町茂雄の『一古書肆の思い出』に描かれていた昭和20年12月26日の乱歩の姿をフラグメントとしてちりばめてみるとどうなるかという興味もありましたし、さらに昭和22年に入ると「探偵作家クラブ会報」が発刊されており、乱歩をはじめとした探偵作家の動静がかなりくわしく記録されていることから、そのあたりの記述を『探偵小説四十年』にこき混ぜれば面白いのではないかというもくろみもあってのことであったのですが、あちらこちら欲張るのはまさしく二兎を追うことにほかならない、まずは『探偵小説四十年』一本とがっぷり四つに組むべきであると結論いたしました。 で、やっぱ頭から行ったほうがいいであろうと『探偵小説四十年(上)』の「処女作発表まで」からあらためて着手してみたのですけれど、基本的には砂をかむような作業の連続ですからいやになってすぐ投げだしてしまいます。しかしただ投げだしただけでは自分が意志薄弱でどうしようもない人間に思えてきますから(そうにはちがいないのですけれど)、何かと理由を見つけてほかの作業に逃避してしまうことになります。たとえばどんな作業かというと、これは一か月ほど前のことなのですが、背景となる時代相のことも勉強しておかなければな、とか思って(「勉強」こそは逃避におけるもっとも普遍的な隠れ蓑でしょう)北杜夫さんの『楡家の人びと』を再読しました。 再読といっても昔読んだ本(新潮日本文学の『北杜夫集』でした)は手許にありませんので、上下二分冊の新潮文庫を購入し、罪悪感めいたものを感じながら(どうしてそんなものを感じなければならんのか)読み進めてみましたところ、じつは内容をすっかり忘れていたことに唖然としてしまったのですけれど、そんなことはともかくとしてとにかく無類に面白い。ほんの端役というしかない登場人物にまで作者の愛情がそそがれているのが好ましく、みずみずしい自然描写、おおどかなユーモア、あくまでも市民の視点に立った歴史観などなどによって、ここには小説、それも長篇小説が本来有しているべき豊かさが確実に実現されているなと実感された次第です。 ひそかに期していたこともひとつだけあって、もしかしたら作中に乱歩ないしは怪人二十面相の名前が登場するのではないかとそこはかとない期待を抱いていたのですけれど、それはあっさりあてはずれ。ただし物語の終幕には、楡家初代から数えて三代目の周二という劣等生が敗戦の翌年、つまりまさしく昭和21年に図書館を訪れるシーンが描かれており(それは楡家の没落が決定的なものであることを暗示するシーンでもあるのですが)、そこにはこんなふうにして「探偵小説」が登場しておりました。
ここに出てきた「探偵小説」は、そのまま乱歩作品のことであると見なしてもさしたる支障はないでしょう。「かなり低級な探偵小説」は、さしずめ乱歩の通俗長篇か。少なくとも昭和21年の時点では、日本における探偵小説の社会的位置というか一般的認識というか、ひらたくいえば人の見る眼はこういったものであったかと想像される次第です。しかし実際には、作中の周二が思春期に敗戦を迎えた人間の虚無的な心情をもてあまして探偵小説のページをひらいていたのと同じころ、乱歩は探偵小説復活のたしかな予感に欣喜しながら海外作品の紹介などに没頭し、いっぽうでやはり敗戦の報に雀躍した横溝正史は「本陣殺人事件」を連載して乱歩の予感を裏づけていました。そしてその本陣は── あすにつづきます。
|
||||||||||||||||
きのう引用した対談「横溝正史の秘密」には、じつはカットされた箇所があります。というか、あるそうです。私はいまだ典拠を見つけられずにいるのですけれど、2003年8月に出た篠田秀幸さんの『悪夢街の殺人』(ハルキノベルス)によれば、横溝正史の対談相手だった小林信彦さんが横溝の死後、それを公表したといいます。 篠田さんの作品はむろん小説なのですが、語り手「私」の視点で記された「プロローグ」には、「本陣殺人事件」をめぐる作者正史と評者乱歩の確執が記されています。「私」は乱歩の「『本陣殺人事件』を評す」に「何やら不気味に冷たい視線」を感じてぞっとしたことを打ち明け、 ──どのように悪意に読んでも、『本陣殺人事件』は、江戸川乱歩が指摘するところの「不満」とやらを、読者に意識させるような書き方にはなっていない。 と評して、乱歩の指摘はことごとく「無いものねだり」だと断じます。きのう引いた対談における小林信彦さんの「『本陣』は江戸川先生の批評が出ましたね。あれがやっぱりぼくには、非常に印象が強かったですね。これでもう完全なものだという感じがありましたから」という言葉にも、「完全なもの」に見えた作品に乱歩がないものねだりめいた批判をつらねたことへの驚きや不審が読みとれるように思われます。 で、『悪夢街の殺人』の「私」はこんなふうに推測します。
この指摘は傾聴にあたいするでしょう。乱歩が「『本陣殺人事件』を評す」を執筆した時点でそれを認識していたのかどうか、それはわかりません。当人には意識されない悪意であったのかもしれません。しかし『悪夢街の殺人』に記された推測を否定することは、たぶん誰にもできないでしょう。
|
きょうも横溝正史です。 私のような世代にはかつて雑誌の誌面や新聞広告、ときには映画のスクリーンにも見ることのできたいかにも好々爺然とした風貌が印象的な横溝正史は、じつはどちらかといえば圭角の多い人間ではなかったかと思われます。何を根拠にそう思うのか、という説明は省略しますが(たとえば乱歩という作家に対して正史がどれほど激越な敵愾心を燃やしていたのかは、横溝亮一さんのエッセイでつぶさに知ることができるわけですが)、とにかくそのように判断されます。そうした人間は他人の言動にも圭角を見いだしてしまいがちなものですから、乱歩から「『本陣殺人事件』を評す」の原稿を送られた正史が「ナイフを送り付けられたみたいで、ぎくりとした」というのも、実際のところは被害妄想のようなものではなかったのかと考えることは可能でしょう。 しかし「『本陣殺人事件』を評す」という短い批評の紙背に、篠田秀幸さんの『悪夢街の殺人』で指摘されていた「大乱歩の悪意」をうかがうことだってやはり同様に可能であるはずです。もしもそうした悪意が存在していたのであるとすれば、『探偵小説四十年』出版のために雑誌の連載を読み返している最中、昭和21年の項から「本陣殺人事件」のことがすっぽり抜け落ちていることに気づいた乱歩は、執筆時に想起をさまたげた理由に思いをめぐらせ、「本陣殺人事件」に対して抱いたなまなましい感情を思いだし(その感情には悪意のみならず、というか悪意以前に敗北感のようなものが含まれていたのではなかったでしょうか)、そうした感情に無意識の作用が霧のようなベールをかけていたという可能性にフロイディズムの徒として思いあたったのかもしれません。そして追記を書きくわえることで連載時の不備を補いはしたものの、その不備がよってきたったところの心の動きにはいっさいふれることなく…… いやいや、どうもいけません。妄想に傾きすぎてしまったきらいがあります。私はこのところ猜疑心がいよいよ強くなりまさり、乱歩が述べているすべてのことに意地の悪い視線を投げかけるくせがついてしまっているようです。むろんそれも『江戸川乱歩年譜集成』の編纂にあたって必要なことではあるのですけれど、あまり度がすぎると可愛げというものがなくなってしまいます(可愛くなくたっていいんですけれど、ていうか、むしろ可愛かったりしたら気色が悪いわけなのですが)。どうやら私の圭角も、もしかしたら相当なものなのかしら。 いやはや。とりあえずお口直しをどうぞ。
|
しつこいようですが、きょうも横溝正史です。この手のことは思いついたときにやっておくのが一番であると私の経験が私に告げておりますので、連想のおもむくままに本日はこういったあたりを。
|
横溝正史の話ばかりではさすがに煮詰まってしまいますから、本日は趣向を変えてみることにいたしました。
ところで、「大衆文学月報」には第五号がふたつ存在しています。そのことを私は、野村恒彦さんから「江戸川乱歩集が有つ賑かな諸名士の好評」が掲載された第五号のコピーをお送りいただいてはじめて知りました。私が知っていた第五号は乱歩の「探偵小説壇繁昌記」が掲載されたもので、ほかにも乱歩の署名入りの「岩田準一君の挿絵」「江戸川乱歩略歴」「探偵作家一本参る話」などが収められています。 両者を照合してみましょう。かりにこちらをAとし──
こちらをBとする。
野村恒彦さんにご意見をお訊きしたところ、発行日が二箇所とも9月15日になっているAが第五号、Bは実際には第六号ではないかとのお答えをいただきました。 なるほど、Aに掲載された松崎天民の「沢田君に代りて」には「大衆文学全集の第五回配本として、『沢田撫松集』を見る」とありますから、そのことからもAは第五回配本の『沢田撫松集』に、そしてBは第六回配本の『江戸川乱歩集』に附された月報であろうという推測が成り立ちます。 とはいえ、AとBにつづくべきC(たぶん『直木三十五集』の月報です)が第六号とされたのか第七号になったのか、そのへんのことはいまだに不明です。というかこの先もずーっと不明なのかもしれず、世の中というのはじつにわからないことだらけなのですが、当サイト「乱歩文献データブック」ではとりあえずこんなぐあいに処理しておきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本日は『江戸川乱歩年譜集成』がらみの話題です。 『探偵小説四十年』に記された乱歩の昭和21年をじっくり丹念に眺めてゆくならば、そこには文字どおり「探偵小説復活の昂奮」に明け暮れした乱歩の姿があざやかです。その興奮は乱歩に何をもたらしたのか。 たとえば6月3日付の伝言に引いた対談「横溝正史の秘密」では、それはこんなぐあいに語られていました。
乱歩は小説執筆以外の「いろんなこと」を強いられ、というよりはみずから買って出て、「作家としては損」をする結果がもたらされたということでしょう。 6月6日付伝言でフラグメントをひろった「『二重面相』江戸川乱歩」では、正史はこんなことも回想していました。6日に引いた「いたってノンビリと小説を書いていた私は、人間が変る必要がなかったのである」につづく箇所です。
この随筆は乱歩の死のすぐあとに書かれたもので、全篇に乱歩追慕の念が底流してはいるのですが、それでもこのあたりのくだりには、「本陣殺人事件」一作によって乱歩を凌駕し去ったという昭和22年11月における正史の自覚、自負、勝利宣言、高らかな凱歌を推測させるに足るものがあるでしょう。乱歩が戦前から志向し「柘榴」の先に夢みていた「論理的本格探偵小説」、それをいちはやく実現したのはほかならぬ自分なのである、という誇らかな謙譲。作家として樋口一葉の「奇蹟の十四か月」にも比すべき期間に身をおいていた昭和22年11月の正史には、そうした思いがたしかにあったと思われます。 なにしろ乱歩に対する正史の敵愾心というのは相当なものであって、それを物語る疎開時代のエピソードは角川文庫の『姿なき怪人』と『風船魔人・黄金魔人』の巻末に収録されている正史ご遺族の座談で知ることができると記憶しているのですが、よく考えてみると私はこの文庫本を所有しておりませんから話になりません。まいったな実際。 それはそれとして、ならばいっぽうの乱歩はどんな思いであったのかというと、いやー、なんか横溝君に先を越されちゃってさー、みたいな太平楽なものではけっしてなかったことでしょう。いまや探偵文壇における実作の第一人者は横溝正史なのであるという厳然たる事実を直視した乱歩は、正史をして「ナイフを送り付けられたみたいで、ぎくりとしたね……」といわしめた「本陣殺人事件」評のことは措くとしても、自身が探偵文壇の頂点に君臨しつづけるための方途を見いださねばならぬという焦りを感じていたのではなかったでしょうか。 なんとも意地の悪い見方ではあるでしょう。当時の乱歩が手を染めていた「いろんなこと」、すなわち海外作品の紹介、探偵雑誌の企画、探偵作家の糾合といったことどもは、もとより「探偵小説復活」にかける無私で純粋な情熱のあらわれであったことはいうまでもありませんが、それでもやはり斯界の第一人者でありつづけるための活動という一面もあったのではないか。私にはそのように見受けられます。つまり乱歩にとって本陣一作こそが自身の喉もとに突きつけられた鋭いナイフなのであり、その切っ先を回避するためにも小説執筆以外の「いろんなこと」にいよいよ情熱を傾けなければならなかったのではないか。 ともあれここでは、「探偵小説復活の昂奮」とそれにともなう情熱とが、「おそろしく戦闘的になり強引になり、権柄ずくになり」と正史の随筆に記されていた「戦後の乱歩」を生みだしたのであると、とりあえずそんなふうに見ておきたいと思います。
|
それにしても私は、乱歩と正史の確執や乱歩におけるタクティシャンとしての側面を強調しすぎてしまったのかもしれません。むろん私がいかに猜疑邪推の限りをつくしてみたところで、両者の関係にしょせん余人には窺いえないものがあることは論をまたないわけですけれど、『江戸川乱歩年譜集成』のためのフラグメントを収集する作業において、収集者が勘ぐりに走ってばかりいてはフラグメントそのものにバイアスがかかってしまうことにもなりかねません。みたいな煩悶も抱きつつ、正史関連のフラグメントはひとまず本日で一段落ということにいたします。
|
本日は過去にさかのぼって補足説明を二件ほど。 まず5月16日付伝言。私は次のとおり記しました。
これはどうやら勘ちがいというか記憶ちがいというか、適当なこと書いてたらみごとにはずれていたというか、私が高校生のころに読んだ宇野浩二作品は「子を貸し屋」ではなかったみたいです。 といいますのも、中央公論社の『宇野浩二全集 第十二巻』に収録された「主要著書目録」によれば、私の家にあった新潮社版日本文学全集には宇野浩二単独の巻はなく、第二十一巻が『里見 またずいぶん適当なことを書き散らかしてしまったものですが、それならば(それならばというのもおかしな話ですが)私はたぶん「蔵の中」を読んだのでしょう。ですから上掲の宇野浩二作品の引用を次のとおり「蔵の中」の冒頭に差し替えたいと思います。
以下は上掲の引用のとおり、といいたいところなのですが、高校生であった私は小説の冒頭が「そして」という接続詞ではじめられていることをあるいは面白く思ったのかもしれません。そんなような不確かな記憶がよみがえってきたみたいな気もします。じつは私にはいまでも人の意表に出るこうした小説作法を興がるところがあるようで、最近の作品では、 ──しかし幸いなことに長く続いた夏の陽射しもようやく翳りを見せてうにやひとでややどかりや小魚たちがめいめいひっそり生きている静かな潮溜まりも薄明薄暗の中に沈みこんでゆくようだった。 という松浦寿輝さんの「半島」の書き出しにおける「しかし」に少なからぬ興趣を感じたものでしたから、「蔵の中」の「そして」にもあッ、と驚いたり感心したりしていたのではないかと推測される次第です。自分でいうのもあれですけど、結構スタイルというものに敏感な高校生ではありましたから。 とはいえスタイルに敏感な高校生であるがゆえに、やはり「なんと古めかしく、かつまた貧乏くさい書き出しであることか。それに何なんだ、このたらたらだらだらとした文体は」みたいなことは感じざるをえなかったのではないか。なにしろ当時の私にとって、あらまほしき小説の書き出しというのはたとえば、 ──コモン君がデンドロカカリヤになった話。 まずはこんなところであったのであり、高校生であった私にはこんなぐあいに始まる小説こそが超かっけーものでした。あるいは、 ──冬の太陽は僅かに乏しい光となって、層雲に蔽われたまま、白々と力なく、狭い町の上にかかっていた。破風屋根の多い小路小路はじめじめして風がひどく、時折、氷とも雪ともつかぬ、柔かい霰のようなものが降って来た。 みたいなものでもいいのであるが、しかし「蔵の中」はいけないと、私はやはりそのように感じて宇野浩二という過去の作家におさらばを告げたに相違ありません。ということにしておきたいと思います。 補足説明二件目。 5月29日付伝言から三日間にわたって記しました乱歩と春山行夫の『幻の女』をめぐるあれこれのことですが、乱歩がはじめてこのエピソードを筆にしたのは、「幻の女」が掲載された「宝石」昭和25年5月号に寄せた「『幻の女』について」(「江戸川乱歩執筆年譜」のこのあたり)であろうと思われると、最近なんだかこの伝言板にお名前が頻出している観のある野村恒彦さんからご教示いただきました。野村さんに深甚なる謝意を表しつつ、読者諸兄姉にお知らせ申しあげておく次第です。 「宝石」の現物はいまだ確認しておらず、というかいずれ『江戸川乱歩年譜集成』のために「宝石」の本誌別冊こき混ぜて全冊ひっくり返してみなければならぬのではあるけれど、それがいったいいつのことになるのかとんと見当もつきません。
|
||||||||||||||||||||||