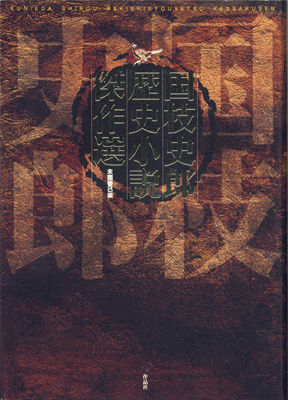|
2006年3月下旬
|
|
記憶とはまったくあてにならぬものだということがあらためて実感されます。「平凡パンチ」に掲載された「藤本義一村長と上方若手漫才師たち」という座談会は、リードに記されていた「若くて無名の『笑の会』メンバーは11月に25年ぶりの上方漫才東京進出を実現する」という東京公演のいわばパブリシティだったのですが、私はこの公演に浮世亭ジョージ・ケンジも帯同していたものと思いこんでおりました。しかるに、きのう引いた記事には「浮世亭ジョージ・ケンジ(解散)」とありましたから、解散していたのであれば東京公演に参加できたはずがありません。私の記憶には錯誤があったということになります。 錯誤といえば、私はそもそもこの座談会、藤本義一さんと漫才作家予備軍だけで行われたものだというふうにも勘違いしておりました。よく考えてみれば、いやよく考えてみなくたって、名もない漫才作家を何十人集めてみたところで週刊誌のネタになるはずがありません。したがいましてタイトルからも知られるとおり「藤本義一村長と上方若手漫才師たち」がメインになった座談会だったことは明白で、げんに収録された座談会の写真には演者と作家の双方が写っていますから、私の錯誤はいまや火を見るよりも明らかではあるのですが、だとすれば私の記憶ちがい勘違いはどういった心の作用によるものか。 ちなみに座談会に出席したコンビは、B&B、ザ・ぼんち、青芝まさお・あきらの三組。BBとぼんちはのちに大ブレイクして瞬間最大風速めいたものながら全国的な人気を獲得しましたが、まさおあきらはどうしたのかなと思ってネット検索を試みてみましたところ、この座談会の翌年、つまり1979年にコンビを解消してふたりとも芸能界から引退してしまったそうです。 そのころの上方芸能界における芸人の学歴は、落語家は高卒、漫才師は中卒、といったところが通り相場でした。その点まさおあきらのコンビは大学を出ていて(検索によって知ったところでは龍谷大学の落語研究会出身で、そういえばそうであったと思い出しました)、舞台衣装はアイビーリーガーズ風、ネタにもあえて知的な諧謔を織りまぜる芸風であったと記憶するのですが、ほとんど思い出せません。わずかにひとつ、ちょうど「ルーツ」というアメリカのドラマが日本で放送されて高視聴率を獲得していたころのことで、それはアフリカからアメリカにつれてこられたクンタキンテという奴隷の子孫がみずからのルーツすなわち祖先をたずねもとめるいったようなドラマであったのですが(私は一度も視聴したことがないのですが)、その「クンタキンテ」という名前を「金太君て」と間違えるという、こう書いてしまうとどこが知的かと思われるギャグをやっていたようなかすかな記憶がないでもないのですが、ともあれもう少し我慢辛抱をしておればあの空前の漫才ブームの波に乗ることができたかもしれぬものを。というか、大学まで出ていてつぶしが効く場合にはある程度才能のあるコンビでもさっさと見切りをつけてばたばたやめてゆくほど上方漫才界の低迷凋落はすさまじいものであったということなのかもしれません。 さて、察しのいい読者は先刻お気づきのことでしょうが、この「藤本義一村長と上方若手漫才師たち」には新進気鋭の、というよりは新進気鋭になるかもしれない若手漫才作家のひとりとして私も出席しておりました。いったいどんなことを発言しているのかといいますと、いきなり名前が誤植されていてなんだかあれなんですが、ともあれ引いてみましょう。
どうしておれがこんなところでぼんち相手に漫才をしておらねばならんのか。ゆうとらんゆうとらん。おれはこんなこと絶対にゆうておらんぞ。
|
||||||||||||||||
雑誌や新聞などの印刷メディアで座談会を活字化するに際しては、出席者がしゃべったままを文章に書き起こしてもそれだけではとても読めたものにはなりませんから、編集部によって多かれ少なかれ手が加えられるのが普通です。「平凡パンチ」に掲載された「藤本義一村長と上方若手漫才師たち」もその例に洩れず、ライターによって大幅に潤色された内容でした。 むろん私だって二十八年も前の座談会で自分が何をしゃべったのか、そんなことをいちいち記憶しているわけではないのですが、掲載誌が発行されて座談会を一読したときに、 ──あちゃー、こら全部古川さんの創作やがな。 と思った、ということを思い出しました。古川さんというのは記事の末尾に、 【構成・古川嘉一郎】 と記されている古川嘉一郎さんのことで、じつはこの方も大阪シナリオ学校の一期生、笑の会の東京公演を成功させるべく読者に知らせたいことアピールしたい点を要領よく盛りこみ、さらにはさすが先輩というべきか上方漫才のノリによる受けねらいのくだりまでちゃんと織りこんで(その素材として私がお役に立ったわけですが)、ここに一篇の座談会をよくお仕立てになったという寸法です。 しかしこうしてふり返ってみますと、上方漫才界のいかなる低迷混迷苦境逆境衰微衰退凋落没落に遭遇しようとも節を屈することなく斯道を邁進してさえいれば、私もいまごろは関西の放送界演芸界において大家とかドンとか巨匠とかボスとか大御所とかゴッドファーザーとか闇将軍とか、そんなような称号をたてまつられる存在になっていたのかもしれません。いやきっとそうなっていたであろうものを。じつに残念なことをした。
|
さてきのうまで、おそらくはそのかみの神事に発してもいるのであろう話芸の伝統に立ってかしこくも鋭い考察をめぐらせながら(何を考察していたんだか判然とはしませんが)、私はひとつの実験を試みてもおりました。ちょいと乱歩になってみる、あるいは『探偵小説四十年』を書いてみる、そういった実験です。 『探偵小説四十年』の原型となった「探偵小説三十年」の連載がはじまったのは昭和24年のことでした。その連載において大正12年のデビュー当時が回想されたのは昭和25年の「新青年」1月号あたり、つまり乱歩は1950年の時点で1923年のあれこれを述懐していたわけで、記述者と対象とのあいだには二十七年間もの時間のへだたりが横たわっていたことになります。そして私もまた、乱歩が「貼雑年譜』をそうしていたごとくたまたま出てきた一冊の「平凡パンチ」を座右におき、自身の過去を追想するという苦々しい行為にあえて挑んでみた次第です。 その結果、体験的に実感としてわかったのは、人は二十何年も前のことなんか明瞭に記憶しているものではない、記憶していたとしても修正や歪曲がほどこされている可能性が高い、といったこととあともうひとつ、いくら二十何年も前のことであっても恥ずかしいことは恥ずかしい、彼は昔の彼ならずなんてことなど全然なくて、いまの私は昔の私、自我の連続性はゆるぎなく一貫している、ということです。 さらに依拠した資料に関していうならば、活字になって残された文献にだって十全な信をおけるわけではありません。「平凡パンチ」の座談会における私の発言は、いやもうあれではなんだか藤本義一さんならびにザ・ぼんちのご両人をまきこんで単にぼけまくっているばかとしか見えぬ次第なのですが、もとより私はあのようなことを口にしたわけではなく、それでもいまあの記事を読んだ人がいたとしたら、 ──あのばかは昔っから場所柄もわきまえず受けねらいに走ってしまういちびりであったか。 とあっさり納得してしまうかもしれません。すなわち記述者側の何らかの意図に基づいて記述対象者本人には身におぼえのないことが記されていたり(私の場合でいいますと、上方漫才関係者が集まった座談会をいかにもそれらしい一篇の読みものに仕立てるために、という意図を構成者たる古川嘉一郎さんが有していらっしゃったということなのですが)、あるいは記述者の勘違いをはじめとした何かしらのミスによって事実とは異なる情報が録されていたり(これも私の場合でいいますと、私の姓が「仲」と誤植されていたことがそれに該当するでしょう)、そんなこんなで活字として残された資料も全面的に信用するわけにはとてもまいりません。 したがいまして結論としては、『探偵小説四十年』という長大浩瀚な一巻の自伝にはやはり相当に心して向き合う必要がありそうだなと、私は今回の試みを通じてあらためてそのように感じた次第です。そして乱歩自身の記憶の問題や乱歩のことを記録した記述者の意図の問題と同様に、いやそれ以上に大きな壁となって私の前にそびえ立っているのが乱歩その人の意図の問題です。 この点に関しては小説の形をかりた乱歩論でもある小林信彦さんの「半巨人の肖像」に克明に記されておりますので、それを引用しておきましょう。底本は1994年10月30日メタローグ発行の『回想の江戸川乱歩』。文中の「この一冊」は『探偵小説四十年』のこと、「鬼道」は乱歩のこと、「今野」は小林さんご自身のことであるとお思いください。
かくのごとく『探偵小説四十年』には乱歩自身の意図という越えがたい壁が存在しているわけなのであって、さすれば私はマルセル・エイメの小説の主人公か、でなければ中国の壁抜け少女にでもならなければなりません。
|
3月も25日を迎えました。本日、大阪では田中徳三さんの「RESPECT 田中徳三」が開幕、東京では石塚公昭さんの「夜の夢こそまこと」が最終日を迎えます。可能であればぜひどうぞ。 さて、『探偵小説四十年』に秘められた乱歩の意図、ということになると、ここまでは公開、ここから先は非公開、という線引きの問題以外に、公開された事実における粉飾や潤色の可能性も念頭におかなければなりません。 たとえば、1月13日付「本日のアップデート」に記した高木彬光の「刺青殺人事件」にまつわるエピソードがあります。乱歩に原稿を送ってみたところ「十日ほどのうちに必ず読む」という返事が届いたのだが、その十日が過ぎても音沙汰がなかったのでおおいにむかっ腹を立てた、というのが高木彬光の回想するところなのですが、『刺青殺人事件』に収録された乱歩の「序」には「私は直ちに三百余枚の原稿を一読した」と書かれてあって、両者が記している事実には齟齬が見られます。光文社文庫版『刺青殺人事件』の解説で山前譲さんは、 ──このあたりの食い違いは、よりデビューをドラマチックにしようとした乱歩による脚色だろう。 と推測していらっしゃるのですが、そういった「脚色」のたぐいはおそらく『探偵小説四十年』にもまぎれこんでいることでしょう。このケースにおける高木彬光の証言のような物証がない場合、読者は乱歩の自己演出をひとまずそのまま受け容れるしかありません。乱歩は演出なんかせずごくあけすけに書いてたんじゃないの、とお考えのあなた、あなたにはきっと洞察力というものが不足している。相手は乱歩です。タクティクスに長けたタクティシャンです。あの「陰獣」という乾坤一擲の自己劇化小説を書いた男です。かなり手強かろうて。ていうか、手強すぎるぞ。 やれやれ、考えれば考えるほど滅入ってしまって困ったものですが、そもそも私が毎日いったい何をあーでもないこーでもないと苦悩しているのかといいますと、もとをただせば脚註王のこのひとこと、 ──もしかしたら、もとの文体に戻れんかもしれません。 これがそれまで不定形だった私の不安をまばたきするあいだに結晶させ、私の心に雨雲のように黒い影を押しひろげていったのでした。私にはいまや、この言葉は脚註王から投げかけられた呪いの言葉であるようにも思いなされる次第です。 脚註王と同様の「話すように書く」文章作法に親しんでしまったいまの自分に、はたして『江戸川乱歩年譜集成』が綴れるものかどうか。それを確認するために私は苦悩し、煩悶し、助けを求めでもするように自身の文章を点検し、そこに抜きがたく話芸の伝統が存在していることを再確認しました。 ここで打ち明けてしまうならば私の文章上の師は安岡章太郎さんなのですが、安岡さんにもまた師にあたる存在があり、そのひとりである井伏鱒二は私にはあまり縁がありませんから、やはり梶井基次郎あたりか、おれは梶井安岡ラインか、安岡章太郎の弟子にして梶井基次郎の孫弟子なのかと、私はかねてそのように信じこんでいたのですが、どうやら梶井基次郎ではなくて太宰治であったか、というのも太宰治こそは傑出して話芸の伝統に立つ作家なのであって(そのあたりのことは三浦雅士さんの『青春の終焉』で的確に考察されていたと記憶します。興味をおぼえられた方はご一読ください)、しかしそうなるとおれは梶井じゃなくて太宰の孫弟子かよ、なんかかっこわりーなー太宰の孫弟子なんてなー、なーにが苦悩の年鑑か、と私はもうさっきから自分が何をいってるんだかよくわからないほどに苦悩の色を深めている。 その苦悩のついでに(どんなついでか)、いささか唐突なようではあれど、一冊の本を話題にすることをお許しいただきたいと思います。連想のおもむくまま話題が右往左往してしまうのが「話すように書く」文章作法の特色なのですが、作家の自己演出や自己劇化といったものを考えているうちにふと、私は最近読んだ西村賢太さんの『どうで死ぬ身の一踊り』を思い出してしまいました。今年の1月29日、講談社から出版された本です。表題作が芥川賞にノミネートされましたから、そのニュースに接して西村賢太という名前をご記憶の方もおありかもしれません。 といったところで、文字どおり右往左往しながらあすにつづきます。
|
まず告白しておくならば、私は当今のいわゆる純文学作品にほとんど接することのない人間です。どうしてそうなのかと尋ねられたら、いま世上にあふれているその手の小説はどれもこれも、網野善彦が「優等生」という言葉にネガティブな意味あいをこめて使用していた顰みにそのまま倣えば、まさしく優等生によって書かれた小詰まらぬものばかりではないのかという思いこみがあるからだ、と返答することになるでしょう。読みもしないでそんなことがどうしてわかるのか、といわれればそれはまったくそうなのですが、とにかくそんな気がするわけです。 で、西村賢太さんの『どうで死ぬ身の一踊り』。書店で手にとってみたところ、少なくとも優等生が書いた小説ではないらしいことが即座に知れました。実際に読んでみるとまさにそのとおり、それどころか劣等生、ていうかばか、こんなばか久しぶりで見たぞ、なんとも見あげたばかではないか、とうれしくなってくるくらい優等生から遠くへだたった書き手によって書かれた小説であったということをまずお知らせしておきます。 私がこの本を買った理由はふたつほどあって、ひとつには帯に配された久世光彦さんの作品評にそそのかされたのと、もうひとつは巻末の著者略歴に、 ──刊行準備中の、『藤澤清造全集』(全五巻別巻二)を個人編輯。 という一文を見つけたことでした。私はこの西村賢太なる作家が芥川賞にノミネートされたという事実は新聞記事で読んでおりましたが、個人全集の編纂を手がけていることまでは知りませなんだ。ついでに記しておきますと、少し前に金沢にある出版社から藤澤清造の作品集が出版されたことも耳にしてはいたのですが、作品はいずれも悲惨悽愴な私小説であるらしいとも聞き及び、そんなものいまさら読みたくもねーやと思って買い求めることはいたしませなんだ。 ここで附言しておくならば、藤澤清造という名前の表記において「清」は旧字が使用されています。つくりの「月」が「円」になった字です。いやいや、しかのみならずよく見てみれば「藤」も「造」も旧字であって、しかしネット上で使用できる漢字には制約がありますから「澤」以外は新字とするしかありません。その点をお断りしておきます。なぜかというと、この西村賢太という作家はそのあたりにすごくうるさい人間だという気がするからです。 久世光彦さんの作品評を帯から引いておきしょう。
『どうで死ぬ身の一踊り』一巻を読み終えた私は、久世さんのこの文章に微妙な違和感をおぼえました。この批評からは何かが欠落しているという気がしました。むろん小説の読後感など人によってそれぞれでしょうし、久世さんの批評眼に異を唱えるつもりも毛頭ないのですが、とにかく私にはそのように思われました。
|
このところ月曜日の朝には頭がずきずきしたり世界がぼーっとしたりということがつづいているようで、本日もその例に洩れません。ではまたあした。
|
|||||||||||||
『どうで死ぬ身の一踊り』には「墓前生活」「どうで死ぬ身の一踊り」「一夜」の三篇を収録。いずれも主人公イコール作者と見做しうる体の小説で、貧窮と錯乱のうちに芝公園で凍死した藤澤清造なる作家を鑽仰する主人公の日常が描かれます。日常ったって同棲相手をそこらのスーパーで働かせ、自身はいうならば藤澤清造オタクと化してほとんど信仰生活とも呼べる明け暮れ、その小心卑屈なるがゆえの尊大傲慢が「同棲している女に暴力を揮い、愛想を尽かした女が逃げ出すと、その前に土下座して涙を零して復縁を哀願する」結果を招いてしまうのは久世光彦さんの批評にあったとおりで、 ──西村のその姿は「根津権現裏」の藤澤清造に瓜二つである。つまり、西村は〈現代〉の実人生で、藤澤と同一化しようとしているとしか思えない。 と久世さんがおっしゃったのも、私は藤澤清造作品を読んだことがありませんから曖昧なものいいしかできないのですけれど、たぶんそのとおりではあるのでしょう。 早い話、「墓前生活」は『石川県人名事典 現代編八』に収められた「藤澤清造」の項目(執筆は西村賢太さん、つまり作家自身)の引用からはじまっており、そのおしまいのほうには、 ──長年の放埒な悪所通いによる精神の破綻が言行に表われ、警察に勾留、内縁の妻への暴行などがくり返されたのち失踪。芝公園内のベンチにて凍死体となっているのが通行人により発見される。 などと見えるのですが、ひきつづく作品の冒頭で藤澤清造の墓を訪れた主人公がいきなり過去を回想して、酔っぱらったあげく桜木町駅前近くの舗道の植え込みに全裸でぶっ倒れているところを巡邏中のパトカーに発見され、留置場にぶちこまれてさてそれからという主人公の経験が読者に提示されるあたり、ここに事典の記述と主人公の日常とを照応させようとする作者の意図を見出すのはじつに容易なことです。 主人公はいうまでもなく(ぬかりなく、というべきか)酒癖が悪く、「どうで死ぬ身の一踊り」では主人公の発起によって営まれた清造忌法要のあとの酒席において、心地よい酔いに包まれながらも副住職が洩らした「この『清造忌』も、もう少し人が集まるといいですね」という言葉を聞きとがめ、「でもこちとらは別に、名所づくりのイベントとしてやってるわけじゃないんだからなあ」とうっかり失言してしまいます。副住職が怒りをこめてそれに反論すると、主人公は内心「しまった」と思いながらも「ヘタに取り繕うよりは」と自説を述べ立てて──
主人公の卑屈な計算は私にはよく納得できるものですし、ここに述べられた見解にはおおいなる共感さえおぼえます。実際、「まるで行政レベルの、どこぞの教育委員会並みの意識」ほど名張市立図書館のカリスマたる私にとって鼻持ちならないものはなく、しかも当地ではそうした「思い上がり」にすぎぬものが官民双方に悪質なウィルスのごとく蔓延しているのですからたまりません。 ところでどこぞの教育委員会といいますと、われらが名張市教育委員会はレベルだの意識だのということになるとてんでお話にならぬのですが、それでも流行を追うことにかけては敏であるらしく、個人情報の流出という当節のトレンドには遅れることなくついていってくれてるみたいです。
みんなしっかりしましょーねー。
|
|||||||||||||||||||||||
読者諸兄姉はご存じないことでしょうが(私にしたところできのうの夜、名古屋ローカルのテレビニュースで知らされたのですが)、昨28日はいわゆる名張毒ぶどう酒事件が起きた日でした。いまから四十五年前、昭和36年のことでした。これも私は知らなかったのですが、事件の発生現場では3月25日、奥西勝さんの弁護団や支援者による現地調査が行われていました。Yahoo! ニュースに掲載された共同通信の記事をどうぞ。
この記事には記されておりませんが、テレビのニュース映像では弁護団側と地域住民側との押し問答というか小競り合いというか、おだやかならぬやりとりも映し出されていました。平和な山村に昔の悪夢をよみがえらせてくれるな、よそから来た人間に地域の安寧をかき乱す権利はない、といったあたりが地域住民のみなさんの主張なのでしょう。そしてくり返されるのは、 「奥西勝が犯人でないというのなら、いったい誰がやったのか」 という言葉です。テレビニュースでは、地域住民に阻止されたせいで弁護団や支援者が集落内を歩くことはできなかった、とも伝えられていたような気がするのですが、私はすでにして素面ではなかったせいでやや曖昧。それにしても、見あげたものだぜ農村構造、みたいなことは1月11日付伝言に記しましたのでこのあたりをどうぞ。事件のことは2月21日付伝言にも出てきますので、お暇でしたらこのあたりを。 ちなみに事件発生当時、現場にもっとも近い場所で開業していたお医者さんは往診中とあって連絡がとれず、名張警察署は管内の警察医に応援を要請しました。この警察医というのが誰あろう、乱歩生誕地碑建立に際して土地を提供し、除幕式の夜の宴席では乱歩の前で裸踊りを披露したといわれる桝田敏明先生でした。「迎えのパトカーを待たず、桝田は病院の救急車に乗り込んだ」と江川紹子さんの『名張毒ブドウ酒事件 六人目の犠牲者』にはあるのですが、桝田医院が救急車を所有していたという事実はありませんから、この記述はちょっとおかしい。 いやいや、そんなことはどうだってよろしい。重箱のすみをつっついてなんかいないで、見あげたものだぜ農村構造のあとは読んだことないぜ藤澤清造の話題だぜ。 『どうで死ぬ身の一踊り』を読んで私の頭に浮かんだのは、歴史はくり返す、というよく知られた言葉でした。 ──歴史はくり返す。一度目は悲劇として、二度目は喜劇として。 久世光彦さんによれば「西村は〈現代〉の実人生で、藤澤と同一化しようとしているとしか思えない」わけで、それはたしかにそうなのですが、むしろこの西村賢太なる作家において重要なのは、彼が自身の喜劇性を明確に認識している点であるでしょう。藤澤清造は悲劇の主人公であったが、他人がそれを再現しようとしても喜劇にしかなり得ない。そのあたりの事情をこの西村賢太なる作家は知りつくしていて、自分の役どころをよくわきまえたうえで自己劇化を進めている。私にはその点がおおいに面白く、また好ましく思われる次第です。
|
||||||||||||||||||||
西村賢太さんの『どうで死ぬ身の一踊り』では主人公と同棲相手の女性との格闘乱闘激闘がくり返し描かれ、しかもそれらはおおむね食いもののことに端を発してゴングが鳴らされるのですから、他愛ないといえば他愛なく、笑えるといえばおおいに笑えます。けちな喜劇を愚直に生きるという作者の自覚が、そこには見まがいようもなくうかがえます。 「どうで死ぬ身の一踊り」から引きましょう。
ばかなのかこいつらは、と私は思ったものでしたが、作者の周到な計算にも思いあたりました。そもそもこの作品には地の文と会話に明白なトーンのちがいがあり(たとえていえば、地の文は昭和、会話は平成、といった印象でしょうか)、その齟齬はもとより主人公のアナクロニズムを際立たせるために仕組まれたものなのでしょうけれど、その主人公に「便座上げとけって言ってんだろがっ!」と、つまり「だろうが」ではなしに「だろがっ!」と口走らせてしまう喜劇性の徹底ぶりに(いやこうなると、喜劇性というよりはコント性と呼ぶべきか。コントというのはもちろんそこらのテレビ番組で演じられている寸劇のことで、実際このへんのくだりはカンニングあたりがコントとして演じても面白いのではないかとすら思われます。読み進むうち私には、主人公と相手の女性とが息のあった漫才コンビであるようにさえ思いなされてきたほどでした)、私は作者の覚悟や面目といったものを見る気がいたします。 筒井康隆さんがどこかに、巧まざるユーモアなどというものは存在しない、という意味のことをお書きであったと記憶しますが、それはまさしくそのとおり。練りに練り、巧みに巧み、企みに企みぬいて仕掛けてみたところで、十ほど仕掛けたうちわずかひとつでも笑いがとれれば御の字であるというのがわれわれの世界なのであって(われわれというのが誰のことなのか、私にももうひとつ分明ではないのですが)、悲惨悽愴なはずの私小説を自覚的な喜劇性で裏打ちしてゆく作者の小説作法には、やはり侮りがたいものがあるように見受けられます。 今度は「一夜」から、ずわい蟹と鯖寿司に端を発した一戦をば。
こんな程度の痴話げんかやドメスティックバイオレンスなら、じつは当節どこにでも転がっていることでしょう。しかし作者にとってはこうした卑小な日常の作品化こそ、おそらくみずからの喜劇性を確認することによって憧憬の(あるいは、信仰の)対象である藤澤清造なる作家の悲劇性を高める行為にほかならないと推測されます。愚かといえば愚かな話ではあるのですが、珍とするに足る姿勢であることはたしかで、それどころかもしかしたら大賢は愚なるがごとし、この西村賢太なる作家はおおきに風変わりではあるけれど名のとおりの賢者なのではないかとさえ思われてくる次第です。
|
まずお知らせです。作品社から『国枝史郎歴史小説傑作選』が出ました。
あ。画像がちょっと大きすぎるか。しかしまあこの大きさは、五百ページを軽くオーバーする大冊のボリュームを二次元的に表現したものだとお思いいただきましょう。 昨年8月に出た『国枝史郎探偵小説全集』につづいて、単行本未収録の国枝作品が一巻にまとめられました。編者は末國善己さん。本体6800円。詳細は作品社オフィシャルサイトのこのページでどうぞ。 さて私は、西村賢太さんの『どうで死ぬ身の一踊り』を題材として作家の自己演出や自己劇化といったものを考察してきた次第なのですが、結論としてはどうもよくわからないということになります。早い話、私は西村作品における喜劇性の自覚とその実践について精緻な分析を試みたわけではあるのですが、そしてそれはそれで全然OK、ひとたび発表された作品は作者のみならず読者のものでもあり、それをどう読もうがそんなことは読者の勝手だ、森鴎外の昔から小説なんて何をどう書いてもいいんだというのが通り相場であるのだとすれば、それと同じ道理で小説なんて何をどう読んだってかまわないということにもなりましょうから、私が『どうで死ぬ身の一踊り』をどう読もうと全然OKではあるのですが、しかし私の心に一抹の不安があるのもたしかなことで、それはひとことでいえば、 ──もしかしたらこの作者、いわゆる天然なのではないかしら。 という一事です。私の眼には計算と映ったものが、じつはすべていわゆる天然の所産であったとしたらどうだろう。自己演出も自己劇化もまるで関係なく、作者は童子のごとくただ生き、ただ書いているだけなのだとしたら。 がーん。 がーん。がーん。 がーん。がーん。がーん。 私の頭にはいまや知恩院の鐘の音にも似た幽玄な響きがこだましている次第なのですが、いわゆる私小説でさえこのありさま、作品内に当然存在しているはずの自己演出や自己劇化の問題は畢竟、 ──どうもよくわからない。 という結論に逢着してしまわざるを得ないありさまなのですから、事実を淡々と記して所見感想を書き継いだだけに見える『探偵小説四十年』にどんな自己演出や自己劇化が秘められているのか、それを明らかにするのは至難でしょう。しかしそれがまちがいなくそこに秘められているということだけは、光文社文庫版全集『探偵小説四十年(上)』ではじめて明らかにされた草稿、 ──私の探偵趣味は「絵探し」からはじまる。 といきなり打ち明けられ、乱歩自身の手で筐底深く秘められてしまった草稿を知ってしまったいまとなっては、私にはすでにして自明であると思われます。みたいなあたりのややくわしいことは伝言録のこのあたりでどうぞ。
さて、3月も本日でおしまいです。 私はこれでもう三か月、つまりは年が明けて以来艱難辛苦をものともせず連日のアップデートに憂き身をやつしてまいりましたが、勝手ながらあしたからお休みをいただきます。期間としては、まあ一週間といったところでしょうか。遅くとも来週の土曜日、お釈迦様のお誕生日にあたる4月8日には復帰が果たせる見込みです。もうちょっと早くなるかもしれませんけど。 それではしばしのお別れですが、みなさんどうぞお元気で、天上天下唯我独尊。 |